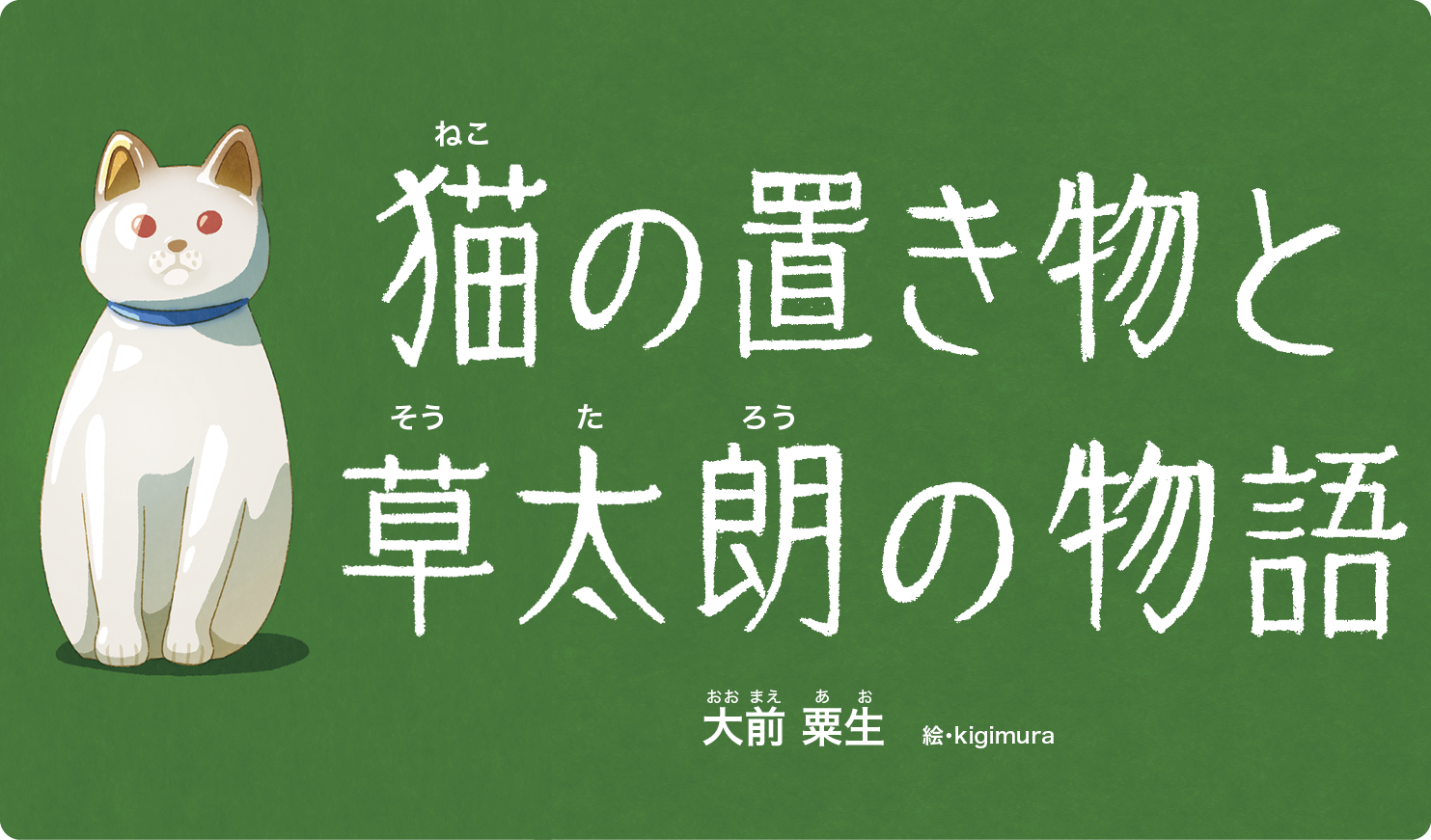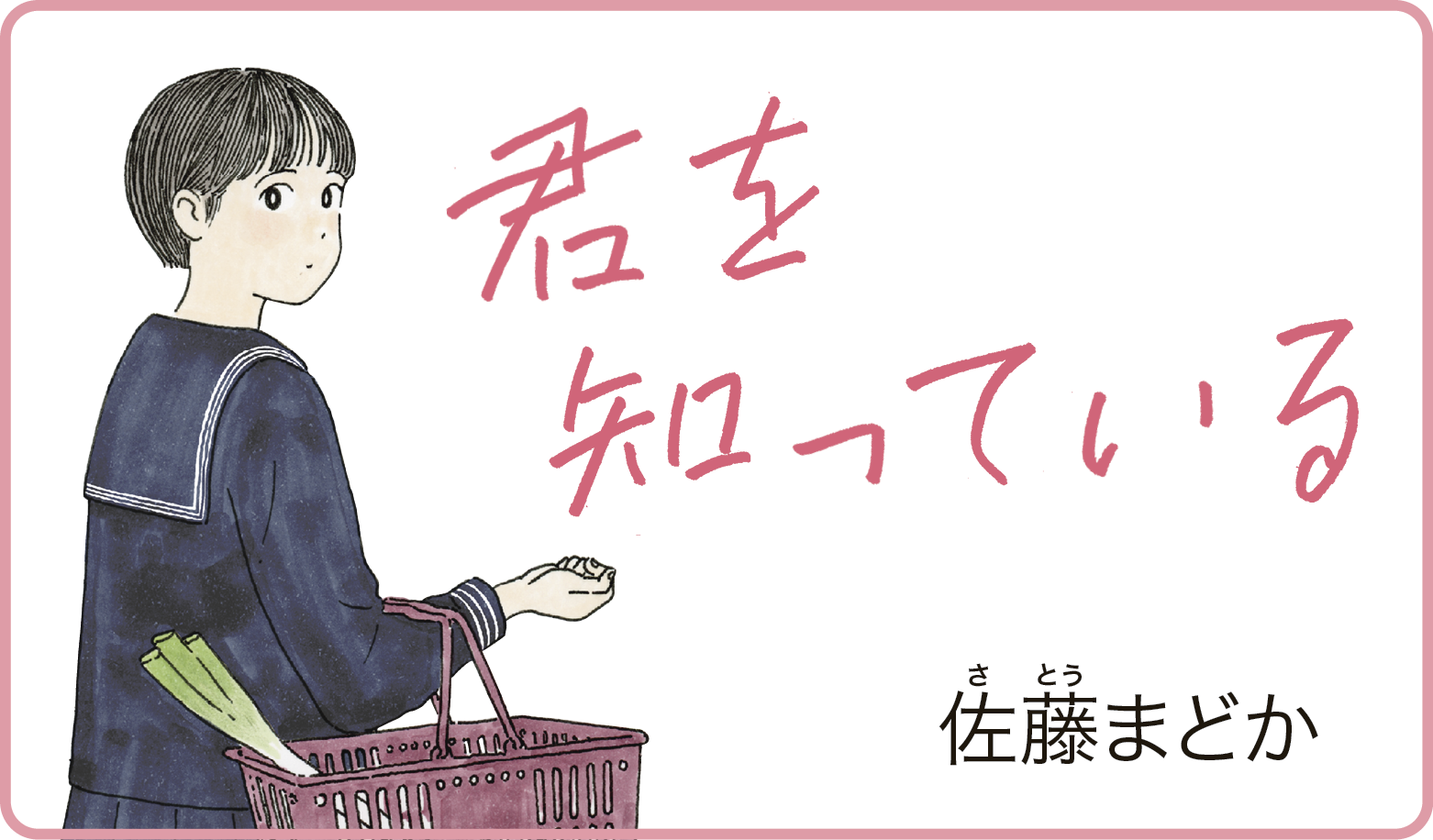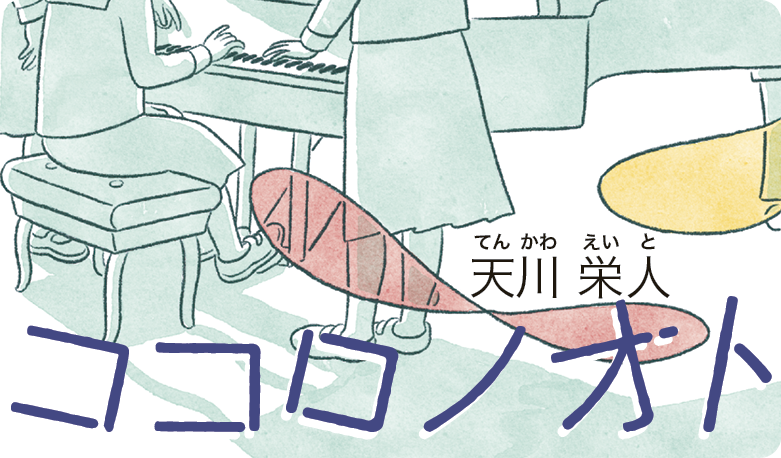おじさんは仕事で世界中を飛び回っていて、帰国するたびに草太朗にいろいろなお土産を買ってきてくれる。
例えばそれは、こんなものだ。トーテムポール。モアイ像のレプリカ。はにわのマスコット。トルコランプ。ノルディックセーター。オーストラリアの先住民族のブーメラン。ドリームキャッチャーという蜘蛛の巣に見立てられた飾り物。その他あれこれ。
お母さんとお父さんはおじさんのお土産の多さに正直困っているけど、それは不登校の草太朗をおじさんなりに元気づけるためだと二人とも分かっているから、家の中に奇妙なものばかり増えていくのをしぶしぶ容認している。
今日はおじさんが久しぶりに日本に帰ってくる日で、空港から自宅までの間にある草太朗の家に寄ってくれる。どんなお土産をくれるのか、草太朗は朝からそわそわしていた。
夜の八時過ぎに家のチャイムが鳴って、おじさんがやってきた。
不精ひげを生やしたおじさんは疲れた顔をしながらも、世界を旅してきたということの誇りを胸にたたえているかのように目を輝かせていた。お母さんとお父さんへあいさつを済ますと、おじさんは草太朗に「調子はどうだ。」と聞いた。
おじさんはほかの人と違って、何だかとても「自然体」な気がする。長いこと学校に行けていない草太朗に、あまり気を遣わないでいてくれているというか。
「まずまずだよ。」
草太朗はちょっと背伸びして答えた。
「そいつは何より。」
おじさんは低くてずっしりとしたバリトンボイスで言った。
「草太朗にお土産があるんだ。」
おじさんはいつものように言って、巨大なスーツケースの中から小さな木の箱を取り出し、その中でさらに厳重に施された包みを開け、草太朗の手のひらよりちょっと小さいくらいの置き物を取り出した。
陶器でできた、猫の置き物だ。
くりくりした目で正面を向いて、お座りをしている。
初め草太朗はその置き物を招き猫だと思ったけど、よく見ると猫の手は何かを招いているような感じではなかったから、招き猫によく似たものなのだと分かった。
おじさんの説明によるとこの猫は、草太朗の行ったことのないどこかの国で、子どもの魔よけとして根付いている民芸品らしい。
どうして「どこかの国」なんて言い方をするかというと、草太朗はその凛としたたたずまいの、りんごみたいに赤くて丸い特徴的な目をし、それでいて焼きたてのパンのようにふっくらと柔らかそうな耳をした猫のことがすっかり気に入って、おじさんの話をろくに聞いていなかったからだ。
「これ、おじさんがくれたお土産の中でいちばん好きかも。」
草太朗がそう言うと、おじさんは「そうか。そいつはよかった。」とやたらとうれしそうな顔をして、草太朗の頭をぐしゃぐしゃとなでた。
その夜、草太朗は猫の置き物を枕もとに置いて眠った。
いつも夜は、明日も学校があること、でも自分は行けそうにないのだと考え、そわそわと不安になってうまく眠れないのだけれど、その日はどうしてかよく眠れた。
学校に行けなくなった理由は、草太朗本人にもよく分からない。ただ、学校みたいに人が大勢いて、いろんな人が話しているところに行くと、自分のうわさ話がされているんじゃないかと考えてしまう。自分が責められているんじゃないか、何か悪いことをしちゃったんじゃないかと。そういうふうに考えすぎてしまうところがあって、今から半年前の小学四年の始業式の朝、草太朗は突然ベッドから出られなくなった。勝手に涙が出てきて、外に出るのが、学校に行くのがつらくなってしまった。
それ以来草太朗はほとんど毎日、家の中で過ごしている。
草太朗の部屋の中は、おじさんが買ってきたお土産でいっぱいだ。草太朗は朝起きると、本棚の上の、いちばん見映えのいい位置に猫の置き物を置いた。不思議な引力を感じて、目が離せない。お母さんとお父さんが仕事に行って、家に一人残されても、草太朗はご飯も食べず、本棚の前に座って、じっと猫の置き物を見つめていた。
家の中からは、チッ、チッ、と目覚まし時計の秒針が動く音以外、何の音もしない。マンションの外からも、何も聞こえてこない。
と、突然声がして、草太朗は震え上がった。
「腹が減ったよ~。」
誰かがそう言っていた。もちろんそれは、草太朗じゃない。
声は、猫の置き物からしたみたいに聞こえた。
まさか。そんな。
草太朗が猫の置き物にぐうっと顔を近づけると、
「そんなにじろじろ見ないでよ。恥ずかしいなあ。」と声がした。
「ね、猫の置き物がしゃべった!」
草太朗は思わず叫んだ。そんなに大きな声を出すのは、ずいぶんと久しぶりのことだった。
「そりゃあしゃべるよ。生きてるんだからね。」と猫の置き物は言った。「それよりさあ、腹が減ったんだけど。」
「ええっと、君は、何を食べるの? キャットフードとか?」
猫の置き物と会話しているなんて、これは夢にちがいない、と思いながら草太朗は言った。
「キャットフード? そんなのこのボクには似つかわしくないね。ボクが欲しいのはね、物語なんだ。」
「物語?」
「そ。ボクは、物語を栄養にすることで君たち子どもをよこしまなものから守ってるんだ。」
「ヨコシマなもの......。魔よけってこと?」
「そ。」
どうやら、口を少しだけとがらせて、「そ。」と言うのがこの猫の口癖みたいだ。
「早く物語をちょうだいよ。昨日、君はすぐに寝ちゃうし、ボクは飛行機の長旅でおなかがぺこぺこなんだから。」
うーん、と草太朗は悩んで、とりあえず、本棚にあった、サン・テグジュペリという人の書いた、「星の王子さま」という小説を読み聞かせてあげた。すると猫の置き物はこう言った。
「うん。悪くはないね。小さな星に住む王子がいろんな星を旅して、『本当に大切なものは目に見えない』って気づく、とってもいい話だ。でもね、その物語は世界中で読まれているから、実はボクはすでに味わったことがあるんだ。まあ、おなかはふくれたけどね。ふう。おなかいっぱいになったら、眠くなっちゃった。明日は、もっと別の物語を聞かせてね。」
そう言うと、猫の置き物は目を閉じて、それきりしゃべらなくなった。
変な夢だな、と草太朗は思った。けれど、いつまでたっても、草太朗自身の目が覚めない。そのうちにお母さんもお父さんも仕事から帰ってきて、草太朗は夕ご飯を食べて、お風呂に入って、ベッドの中で布団をかぶった。うとうとしかけてようやく草太朗は、猫の置き物がしゃべったのって夢じゃなかったんだ、とがく然とした。
次の日も、猫の置き物は物語を求めてきた。
いったいどうしてしゃべるのか、草太朗は気になって聞いたけれど、
「じゃあ聞くけど、君はどうしてしゃべるのさ。君はどうしてご飯を食べるのさ。」
と逆に質問をされてしまった。
その答えは、草太朗にも分からなかった。何だか、うまくはぐらかされてしまった。
この日、草太朗は、太宰治という人の書いた、「走れメロス」という小説を読み聞かせてあげた。
「ふーむふむ。『メロスは激怒した。』という印象的な一文から始まる、人を信じる心の尊さだったり、友情の大切さが詰まった名作だ。これは中学生で習う話だけど、君はよく知ってるね。ただこれもボクは食べたことがある。おいしいけれど、もっと変わった味をボクは味わいたいんだよね。そうだ。ねえ、草太朗くん、明日からは、君の物語を聞かせてよ。」
「僕の物語?」
「そ。」
「それって、何なのさ。」
「さあ。そんなのは、君の見つけることだよ。君だから見つけられるものなんじゃないかな。」
そう言うと猫の置き物は大きなあくびをし、また眠ってしまった。
草太朗は考えた。物語なんて言われたって、僕の生活には、何もたいしたことが起きたりしない。僕自身も、全然、たいしたやつじゃない。
困った草太朗は、その日の夕食のときに、お母さんとお父さんに、
「物語って何だと思う?」
と聞いてみた。猫の置き物がしゃべって、物語を聞きたがっているなんてことは、とてもじゃないが話せなかったけど。
答えはそれぞれ違っていた。
「どきどきさせてくれるものかなあ。」
とお父さんは言った。
「私は、自分自身に似た人をその話の中に見つけられるものだと思うな。」
お母さんは、少し難しいようなことを言った。
「ふーん。じゃあ、『僕の物語』って何だと思う?」
「草太朗の物語?」
お父さんは、うーん、と考え込んだ。同じように考え込んだお母さんが、夕食を食べ終わるときにこう言った。
「草太朗が何かの一歩を踏み出すことだったり、一歩を踏み出そうと思えるもの。それって、何でもいいと思うんだ。趣味でも、勉強でも、ほかの何でも。ただ、それをすることで草太朗が後悔しないこと。」
草太朗は、考え込みながらお風呂に入り、そして眠りについた。
朝起きても、まだ自分の物語とは何か考えていたけど、分からなかった。見つけに行かないといけないような気がした。
そして、ふとこう思った。
学校、行ってみようかな。
うん。お母さんとお父さんは、「無理しなくていいよ。」と言ってくれるだろうけれど、学校に行ってみよう。まずは、校門の近くまで。久しぶりに学校に行くのは、怖い。どきどきと心がゆれ動く、たいへんなことだ。もしかしたら、教室に向かわず、家に引き返してきてしまうかもしれない。教室に入ってみんなに元気よくあいさつをすることよりも、そのほうがうまく想像できた。それでも、僕にとっては大きな一歩だと思う。
そう、大きな一歩。
大きな一歩なのだから、それは、僕の物語なのかもしれない。
帰ったら、猫の置き物に聞かせてあげよう。
大前粟生
小説家。著書に「ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい」「物語じゃないただの傷」などがある。