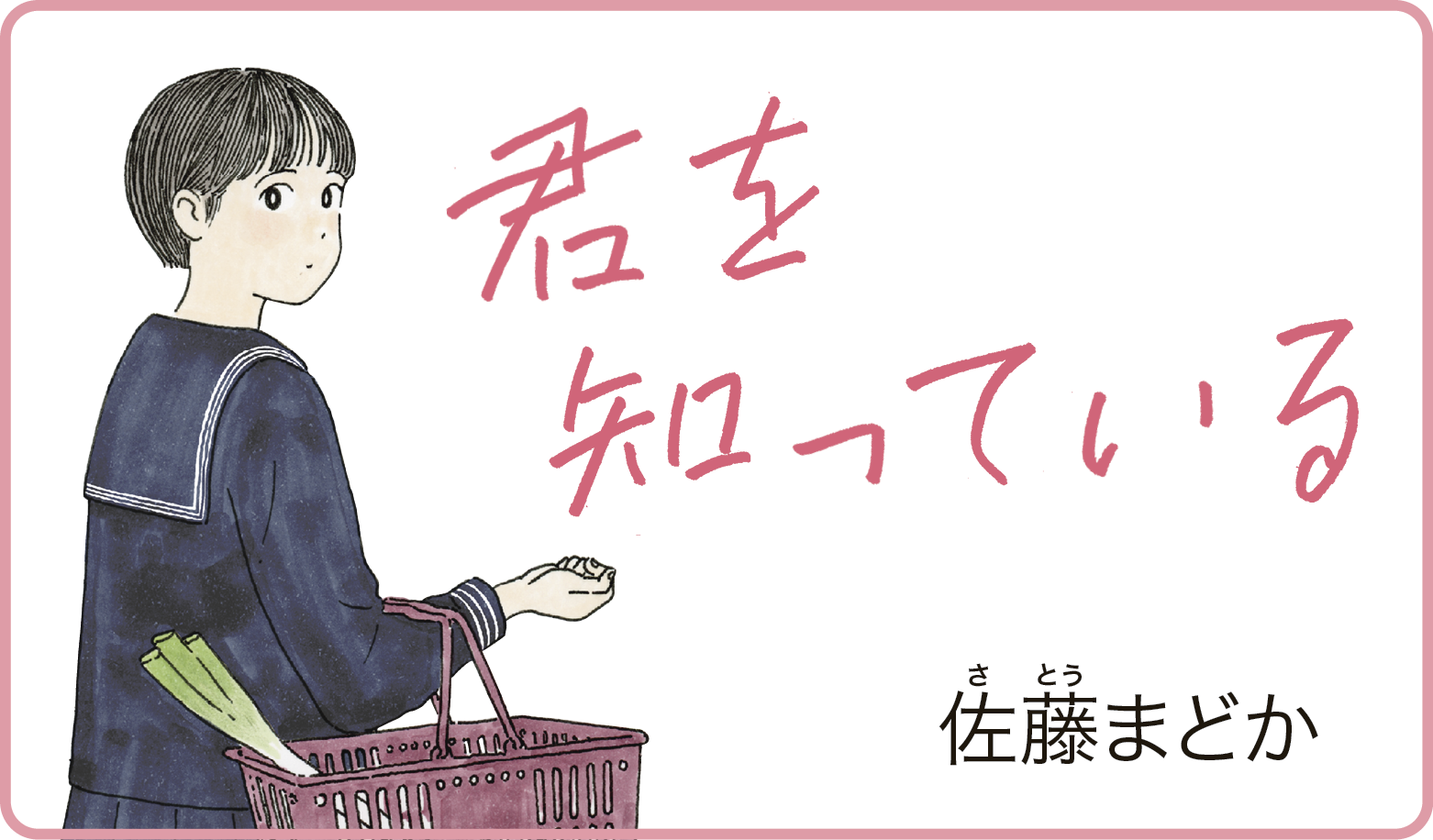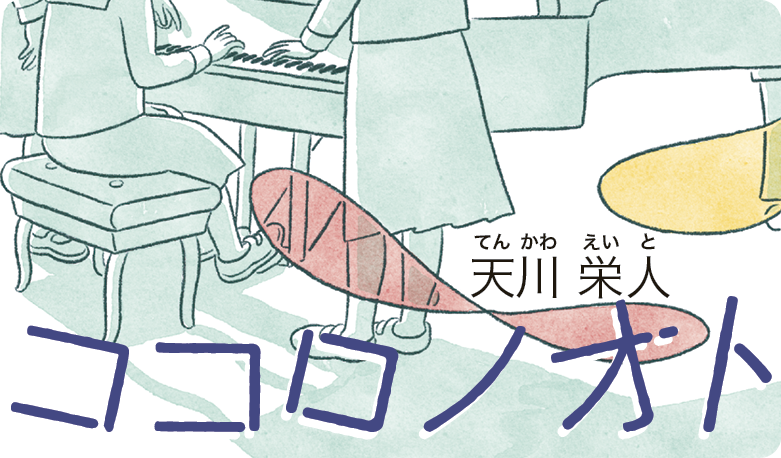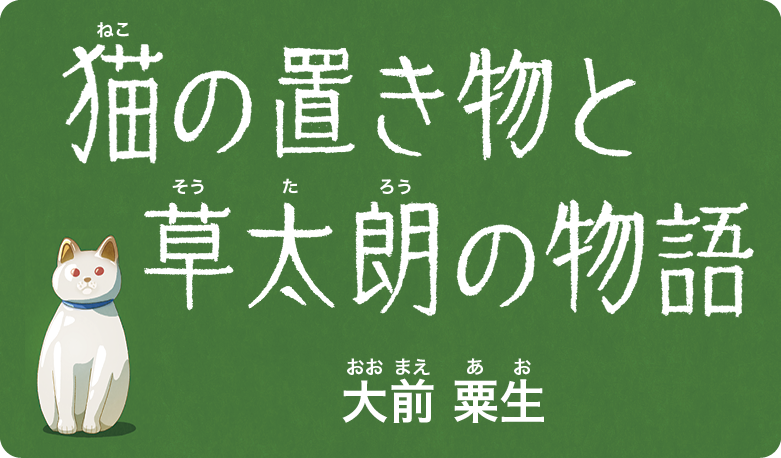月夜の散歩
町田そのこ
伴坂初音の家から帰ってきた父陸郎が、天斗に「出かけるぞ。」と声をかけてきたのは、夜の十時を過ぎたころだった。弟の海は祖父母といっしょにもう寝ていて、母の由美子を見ると「二人でどうぞ。」と言う。天斗は本当は行きたくなかったけれど、しぶしぶうなずいた。
外に出ると、ひんやりとした空気の中に土と草の匂いが混じっていた。ついこのあいだまでほこりっぽかったのに、みずみずしい。かすかに、虫の鳴き声も聞こえた。駐車場に止めた車の横をするりと抜けて道路に出た陸郎が「田んぼに、水が入ったな。」とつぶやいた。
「田植え前の匂いって、いいよな。」
陸郎がのんびりと言うが、天斗はそんなことどうでもよかった。「父さん、車で出かけるんじゃねえの?」とぶっきらぼうに聞いた。伴坂の家は、車でも十五分ほどかかる。陸郎は「行かない。」と短く言った。
「伴坂のところに、謝りに行くんじゃねえの?」
「それはもう、済んだよ。」
「おれ、謝ってないけど。」
思わず言ったものの、天斗は謝る気などさらさらなかった。昼間も、桧山先生や校長先生に何度も謝るよう促されたけれど、天斗は断固として、頭を下げなかった。「ごめんなさい」の「ご」の字も口にしなかった。
でも、謝らなきゃ済まない問題なんだろうなとも、天斗は思っている。伴坂に暴力を振るったのは、まぎれもない事実だ。自分のために謝りに行った陸郎が少し疲れたように見えるのはきっと、伴坂の家からこってり責められたからに違いない。本心からではないけど、頭を下げないといけないのだろう。
「悪いとはこれっぽっちも思ってないけど、それでも父さんが謝れって言うなら、うそで謝ってやるよ。」
心の中であかんべをしながら頭を下げてやる。顔を上げたときには、伴坂の顔を全力でにらみつけてやる。想像するだけで、天斗は血がぐつぐつと温度を上げていく気がした。
「まあ、暴力は、いけないな。」
陸郎が空を仰ぐ。その声に非難めいた響きがなかったから、天斗は「女の子を殴るなんて最低だって、言わないの?」と聞いた。桧山先生は「男が女に手を上げるのはかっこ悪いことなんだぞ。」と声を荒らげたし、校長先生は「男女なんて関係なく、手を出すこと自体が最低な行為だ。」と顔を厳しくした。
「あっちの方、歩こうか。」
天斗の質問に答えず、陸郎は広い国道ではなく田んぼが広がる方向を指した。天斗の返事を待たず、歩き始める。天斗は陸郎の思わくが分からないまま、その背中を追った。
空気が変わった理由が分かった。田んぼに水が流れ込んでいた。水路から、さらさらこぷこぷと水の音がする。いろんな匂いが濃くなり、カエルと虫の声がそこかしこから響いてくる。街灯の少ない道路だけれどやけに明るくて、見上げると大きな月が卵色の光を放っていた。
だんだんと、天斗は不思議な気持ちになってきた。ふだんは友達と自転車で通り過ぎるだけの場所が、全く別の顔をしている。生き物の気配がくっきりしていて、今まで聞き逃していた音が大きく聞こえる。先を歩く陸郎の背中が、やけに広く大きく見えた。
父さんはいったい、何のためにおれを外に誘い出したんだろう。
陸郎の考えていることが分からず、天斗はとまどう。お説教なら、家のリビングでもよかったはずだ。どうして、わざわざ外に出ないといけないんだ。
「伴坂さん、天斗よりずいぶんと背が高かったな。」
つぶやくように言った陸郎の声に、天斗ははっとする。「あー、うん。クラスでいちばんでかい。」と答えた。四月の身体測定で、伴坂は百六十五センチだった。天斗は、百四十二センチ。
「暴力はいけないことだけど、」
陸郎がぷつんと言葉を切る。それから「でも、勇気がいることだったな。」と付け足した。
「は? 意味分かんね。父さん、怒んないの? おれ、あいつのこと二回殴って、ケツも蹴ったんだけど。」
「怒られたいのか、君は。」
ふは、と陸郎が吹き出した。
「でも、覚えてるんだな。自分が人に振るった暴力がどういうものだったか。」
「別に、ただ、何となくだよ。」
本当は、違う。あの瞬間は無我夢中だったけれど、その後は自分が何をしたのか、何回も思い返したのだった。腕を振り回し、肩に一回、右腕に一回こぶしが当たった。伴坂が「ちびのくせに調子乗んな!」とつかみかかってこようとしたから、後ろに回って尻を一回蹴った。伴坂はそこで「ひどい!」と叫んでへたり込んで泣き始めた。いつもは偉そうに怒鳴り散らす伴坂が一年生の子みたいにめそめそ頼りなく泣く姿を見て、暴力を振るった自分に気がついた。両手も、右足も、痛かった。
「覚えてるのは、いいことだ。それが嫌な思い出であればあるほど、君はもう暴力を振るおうとは思わなくなるだろう。いい抑止になる。」
先を歩いていた陸郎が、くるりと振り返った。
「親として、二度と誰かを傷つけてはいけないよ、と君に言うよ。どんな相手だろうが、暴力に訴えるのはよくない。二度としてはいけない。」
ぴんと張り詰めた、厳しい声だった。陸郎はふだんはあまり怒らない人だから、その声の鋭さは天斗の胸にぐっさりと刺さった。立ち止まった天斗は、足もとに目を落とす。海とおそろいの黄色いスニーカーのつま先をじっと見つめた。
「でもな。海の家族としては、ありがとうって言いたい。」
陸郎が、声の緊張を解いた。天斗がちらりと目だけ向けると、陸郎は「海のために、戦ったんだよな。」と口角をそっと持ち上げた。
「......あいつは、海をばかにしたんだ。」
天斗の四つ下、今年小学一年生になった海は生まれつき足に障害があって、左足を引きずって歩く。その歩き方がおかしいと言って、伴坂は海の前で誇張した歩き方をしてみせたのだ。
最近、海が泣きそうな顔をしていることがあったのを、天斗は知っていた。まだ学校に慣れないのかな、友達とけんかをしたのかな、くらいに思っていたけれど、本当のところは全然違ったのだ。
下足箱の所で、伴坂が海に話しかけている姿を見かけたとき、奇妙な気持ちがした。上級生が下級生に声をかけて面倒を見たり遊んだりすることはよくあることだけれど、そういう雰囲気じゃなかったのだ。隠れて見ていれば、伴坂は海の前でぐねぐねと歩いてみせて「こんなふうに歩いてるんだよー?」とへらへら笑った。海の顔が泣きだしそうにぐっとゆがんだ瞬間、目の前が真っ赤になって、体の奥がぼっと燃えあがる気がした。気づけば、駆けだしていた。
「おれ、知ってるもん。海が三歳になって初めて歩いたとき、みんなでお祝いしたよな。母さんとばあちゃんがめっちゃ泣いて、じいちゃんは神社にお礼を言いに行ってくるって言って。じいちゃん、海が歩けるようになりますようにって、毎日お参り行っててさ。雨の日も、台風の日も。そういうの、ちゃんと知ってるもん。」
みんなで一致団結して海を応援して、祈って、みんなで喜んで、みんなで泣いて。そんなだいじなことが一気によみがえって、それらが全部、伴坂に踏みつけられたような気がした。
海とは、いつもけんかをする。生意気だし、口が悪いし、欲張りでわがままで泣き虫だ。海にはみんな甘くて、それが腹立たしくてたまらない日はいくつもあった。大好きな弟とはとうてい言えなくて、一人っ子だったらよかったのにと思ったことだってある。
でも、悔しかった。耐えきれないほど、怒りが湧いた。
そうだよな、と陸郎がうなずいた。
「おれは、天斗は海だけじゃなく、おれたち家族のために戦ってくれたんだと思う。家族のために立ち向かってくれた君を、おれは誇りに思うよ。」
陸郎が、天斗の手を取った。今もまだ少し痛む右手の甲にそっと触れる。
「家族のために勇気を奮ったことを、おれは𠮟ったりできない。」
大きな手のぬくもりに、天斗は少しだけほっとする。陸郎が事情を全部分かってくれたことが、うれしかった。しかしそこで、はっと気づく。
「待って。どうして父さんが知ってんだよ? おれ、先生たちにも、母さんにも、伴坂が海に何をしたのか言わなかったんだぞ。」
事情を話してごらんと言われたけれど、天斗は話さなかった。それは、海が嫌な思いをすると思ったからだ。先生たちに歩き方を笑われていたなんて話せば、海も事情を聞かれてしまう。それはとても悲しいことだろう。
「それはね、伴坂さんが謝ってくれたからだよ。」
え、と天斗は無意識に声が出る。
「謝罪した後にあちらのご両親とお話をしていたらね、私が悪かったって、彼女から話してくれたんだ。」
伴坂は両親と陸郎に、泣きながら告白したのだという。からかうと目を涙でいっぱいにする顔がかわいくて、それで何度も近づいていったこと。自分の中では「遊んでいる」つもりで、意地悪だとは思わなかったこと。
「話が大きくなってしまって、怖くなったみたいだったよ。でも何よりも、ふだんはおっとりしている天斗が怒ったことが、ショックだったんだって。」
「......先生たちに何があったのか話しなさいって言われたとき、伴坂は一言もしゃべらなかったんだ。」
海の歩き方をばかにしていたとは言わず、しかし天斗が悪いとも言わなかった。泣き疲れた顔で、唇を一文字に引き結んでいた。天斗はそれを、体の小さな自分に泣かされたことが悔しくてしゃべらないのだと思っていた。
「彼女は明日、海にきちんと謝ると言ってくれた。それを見てから、君も謝罪をするかどうか考えればいい。」
「......分かった。」
伴坂が本当に謝ってくれるか、分からない。でも、海のために謝ってほしいと天斗は思う。そんな気持ちを察したのか、陸郎が「大丈夫だよ。」と言った。
「彼女はちゃんと分かってくれてる。そうじゃなきゃ、自分がしたことを話してくれるわけないだろう。」
うなずこうとすると、ぐわあ、と大人の男の人のげっぷのような声が田んぼから響いた。大きなカエルがいるらしい。天斗と陸郎は同じ方向を見る。
「見てごらん、天斗。月が二つある。」
陸郎が指差す先を見る。高い天と、水面が鏡のようになった田んぼの両方に、月が浮いていた。やさしい光がきらめいている。
きれいだ、と天斗は思ったけれど言葉として出てこない。身近な場所に、目を奪われる瞬間があるなんて思ってもみなかった。
「おれも子どものころ、友達を殴ったことがある。君みたいに家族を守るためじゃなくて、自分のプライドの問題だったんだけどさ。」
陸郎が頭をかいた。
「じいちゃんにこうして連れ出されて、𠮟られた。そのときおれに、じいちゃんが言ったんだよ。自分のために戦おうとした気持ち自体は、否定しないって。正しく怒れる人間になれよって。」
「正しく怒る?」
「そう。怒る気持ちは、なくしちゃいけない。今回、君は怒り方を間違えたけれど、気持ちは間違いなく正しかった。だからこれからは、正しい怒りを正しく伝えられるようになってほしい。」
天斗は陸郎の顔を見上げる。それから、目の前の二つの月に視線を戻した。
「......覚えておく。」
陸郎が、天斗の右手をぎゅっと握った。
「人に手を上げて、怖かっただろう。正しく怒るのは難しいことだし、しんどいもんさ。よく、頑張ったね。」
強く包まれた手が熱くて、痛い。「力が強いんだよ。」と文句を言おうとした天斗だったが、しかし口から漏れたのは嗚咽だった。
本当は、怖かった。本気で誰かを殴ったことが恐ろしくてならなかった。とんでもないことをしたと、思ってた。
声を上げて泣く天斗の手を、陸郎は離さなかった。
二つの月だけが美しく輝く夜の中で、天斗の涙は陸郎以外誰も知らない。カエルたちが、天斗の声を隠すように高らかに鳴き続けた。
町田そのこ
作家。福岡県在住。著書に「52ヘルツのクジラたち」 「宙ごはん」 「夜空に泳ぐチョコレートグラミー」などがある。