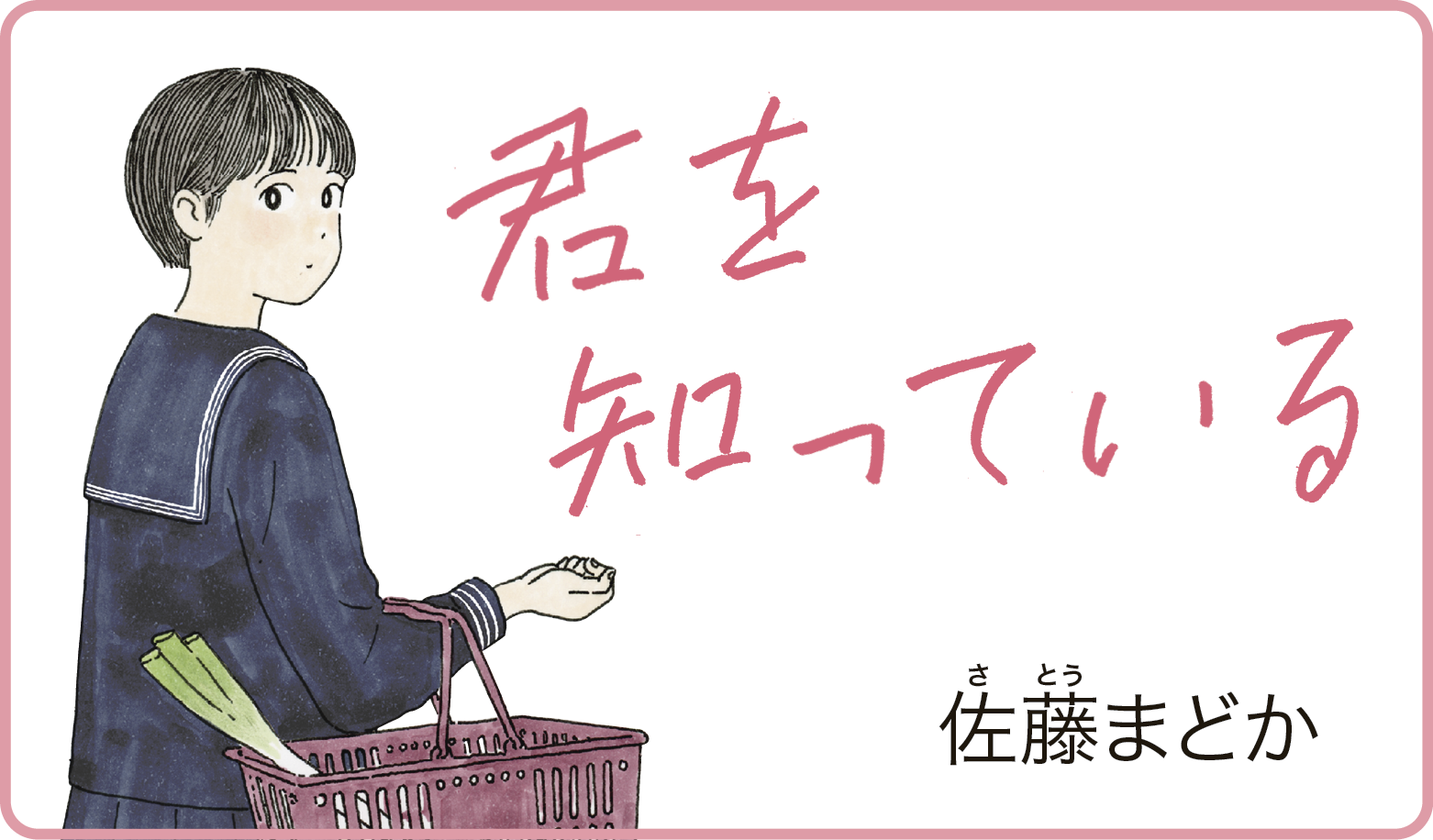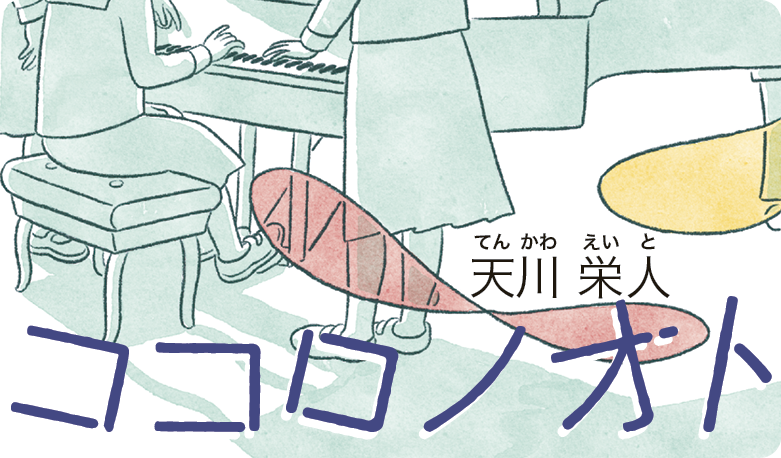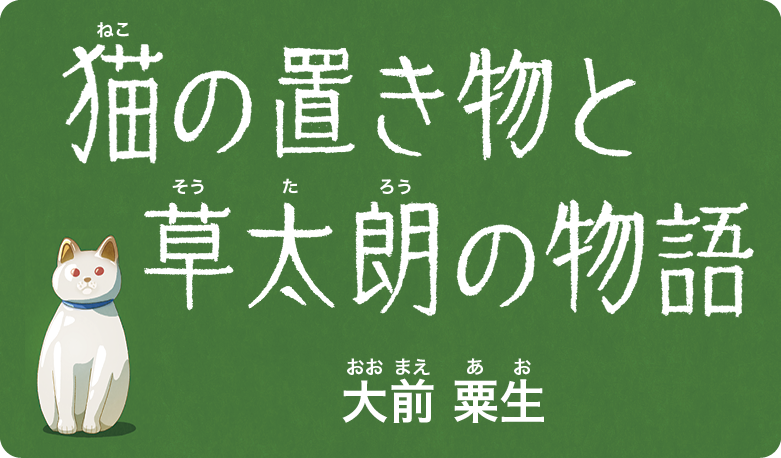グループワークをした余韻 もあって、教室内は騒がしい。後ろの席に陣取っている目立ちたがり屋の男子三人トリオが大きな声で笑って、みんなをあおっている。理科の先生はゆるいから、調子に乗っているのだろう。律哉は、ふうっと息を一つ吐き出してから立ち上がった。
「おい、静かにしろよ。先生の声が聞こえないだろ。」
声を張ると、三人トリオの中心である翔太が律哉に目を向けて、「悪い悪い。」と手刀を切った。翔太が黙ると、ほかの二人も静かになった。先生が、助かったよ、みたいな笑顔をよこす。教室内は落ち着きを取り戻し、その後、理科の授業は滞りなく進んだ。
中学デビューした翔太は、小学生の頃とはだいぶ変わってしまったが、どういうわけか律哉を慕ってくれる。翔太に限らず、ちょっととんがった生徒たちも、「律哉が言うなら。」と一目置いてくれる。
律哉は小さい頃から優等生だった。勉強も苦じゃなかったし、スポーツも得意だ。先生からの覚えもめでたく、親に反抗するという気持ちも湧かず、うるさいことを言われても、まあ一理あるな、と思うタイプだ。小学生の頃からずっと学級委員だったし、中学二年の後期からは生徒会長に任命され、今に至る。サッカー部では部長だった。
先生や親が自分に期待しているのも知っているし、友達からの信頼が厚いことも自覚している。あらゆる場面で、みんながどういう気持ちでいるかも瞬時に理解できるし、そのときに自分がどう言えばいいか、どう振る舞えば正解なのかも自然と分かる。
律哉自身、そんな自分を持て余しているかというと、そんなことはなく、何事もスムーズに事が運ぶのでかなり満足している。
「谷岡、ちょっといいか。社会のレポート出てないの、谷岡だけなんだけど。」
教科ごとに係が決まっていて、律哉は社会科係だ。先週の宿題だった、自分の好きな戦国時代の武将についてまとめるというレポートを、谷岡だけが出していない。
「ああ、あれかあ。」
「今、出せる?」
律哉がたずねると、谷岡は首を振った。
「おれ、好きな戦国武将なんていないから。」
「は?」
「いないから出せない。縄文時代だったらいいんだけどなあ。」
そう言って、シャープペンに芯を入れる作業を始める。
「谷岡は、縄文時代の歴史上の人物を知ってるのか?」
「いや、知らない。でもさ、戦国時代の武将より、縄文土器を作った人のほうがすごくない?」
「縄文時代の人物の記録や文献はないだろ?」
律哉が質問すると、「あーあ。」と情けない声を出した。シャープペンの芯が一本折れたらしい。
「ん、文献? そんなのあってもなくても関係ないよ。いいよなあ、縄文時代。平和だし、身分制度もないしさ。 あこがれる。」
律哉は、谷岡に気づかれないように細く息を吐き出した。
「オーケー。じゃあ、レポートは出さないってことでいいんだな。」
「いいよ。」
谷岡悠 。三年で初めて同じクラスになった。顔は見たことはあったけれど、話したことはなかった。谷岡は、何というのか全くつかめない生徒だ。社会科のレポートだって、好きな戦国武将がいないからって、提 出 しないなんてありえない。実際、律哉だって、武田信玄のことなんて特に好きなわけではない。会ったことも話したこともないんだから、あたりまえだ。
中学生最後の夏休みはあっという間に終わって、これからは受験一色となる。中三の内申書がだいじなのは、みんな十分に分かってる。これまで課題をサボって提出しなかった連中も、今は進学のために必死だ。それなのに、谷岡だけは変わらない。お気楽というか、危機感がないというか、社会性がなさすぎるというか......。
谷岡は決して勉強ができるわけではないし、運動が得意という印象もない。クラスでは目立つこともなく、かといって大人しいわけでも暗いわけでもない。ひょうひょうとしているけど、変わり者というわけでもない(変わり者はほかにもいる)。はっきりいって、ふつうだ。
ふつうのクラスメートは、律哉にとって最も話が通じやすい。律哉の意見に何でも賛成してくれて、さらにはありがたがってくれるから、大いに助かっている。
けれど、谷岡だけはちょっと違う。律哉はたいてい誰のことも好きだが、ひそかにこのクラスメートだけは苦手なのだった。
体育の授業は持久走。男子はグラウンドを十周、三キロを走る。律哉は、短距離は好きだが長距離があまり得意ではない。今日は十七人中、五位以内を目指したい。
「ようい、スタート。」
先生が笛を吹いて、一斉に走りだす。陸上部の光喜とバスケ部の綾斗がツートップだ。三番手は翔太。律哉は今のところ、七番手につけている。このままのペースで行けば最終周でスパートがかけられる、と頭の中で算段しながら先頭集団についていった。
光喜と綾斗はペースを落とすことなく一位と二位を維持しながら、四周目で最下位の生徒を一周分追い越した。
あと三周。ふくらはぎの筋肉がちぎれそうだ。サッカー部を夏休み前に引退してからは、走り込むこともなくなっていた。努力を惜しんだ自分をだらしないと律哉は思う。 前にいた翔太が順位を落とし、後方に流れていく。ラスト二周。
そのとき、後ろから誰かが来て律哉に並んだ。谷岡悠だった。涼しげな顔をして足を繰り出している。そういえば谷岡は持久走が得意だったと、ふいに思い出した瞬間、こいつにだけは負けたくないと思った。律哉は、渾身の力でスパートをかけた。谷岡の姿が視界から消える。
律哉は最後の力を振り絞ってゴールした。ゴール前で並んだ生徒と同時ゴールだったが、僅差で律哉が四位になった。
そのままドサッと倒れ込んで、天を仰ぐ。秋の太陽の光が、閉じたまぶたに降り注ぐ。息が苦しい。体中の毛穴から汗が噴き出す。体操着はぐっしょりとぬれている。
次々と、苦しそうな顔がゴールしていく。律哉は息を整えて体育座りになり、クラスメートたちに拍手を送った。
「......あれ?」
思わずつぶやいた。谷岡が今、ゴールしたのだ。順位はおそらく後ろのほうだろう。ずいぶん遅い。みんなが息を切らしている中、谷岡だけはさわやかな表情だ。ゴール後、座り込むこともなく、立ったまま顔を空に向けて、気持ちよさそうに風に吹かれている。
最下位の生徒が息も絶え絶えにゴールして、みんなから大きな拍手で迎えられた。最終周はほとんど歩いていたけど、汗だくで必死にゴールを目指す姿はちょっと感動的だった。
授業が終わり教室に戻ろうとしたとき、谷岡が先生に呼ばれた。律哉は気になって、近くで様子をうかがうことにした。
「谷岡、二年のときよりタイムが落ちてるじゃないか。本気で走ったか? まだまだ余裕があったように見えたけど、どうだ。」
先生の口調が厳しい。谷岡は何か考えているような顔だ。
「......はい。本気で走りました。」
そう答える谷岡を、先生が不審そうな顔で見る。律哉から見ても、谷岡が本気で走ったようには思えなかった。
「最大限の努力はしたか? みんな、倒れ込んでゴールしてたぞ。」
先生が質問を続ける。谷岡は顔をかしげて、また何かを考えるようなそぶりを見せた。
「倒れ込んでゴールするってことが、最大限の努力ということですか?」
きょとんとした顔で、谷岡が質問を返す。おちょくっているというわけではなく、先生の言っている意味が本気で分からないようだった。
「みんなそれほどに、懸命に自分の実力を出したってことだ。お前は実力を出しきったか?」
しばらくの沈黙の後、谷岡は、今日の自分の実力を出しました。」と言った。先生は、そうかと小さくうなずき、二人の話はこれで終わりとなった。
律哉は、何だかいらついていた。谷岡が意味不明だからだ。天然を気取っているのか、それともがんばるのは愚かだという、今どきの風潮 をまねした浅はかな考えの持ち主なのか。どちらにせよ、おもしろくなかった。先生の質問をのらりくらりとかわして、自分は間違っていないという態度が鼻についた。
最後の生徒会集会。十月からは、二年生が中心となって生徒会活動をしていく。現生徒会長の律哉は、大取りを任された。最後だから、きっちりと締めたい。
まずは、一年間の活動に協力してくれたお礼と、律哉が指揮を執って改善した校内ルールなどについてしゃべった。この後は、今後の抱負を述べて終わりにする。
「ぼくたち三年生にとって、中学校生活も残すところ、 あと半年となりました。来週は中学校最後の運動会があり、来月は最後の文化祭があります。最終学年として残された日々を、下級生たちの手本となるよう、勉強にスポーツに励んでいきます。そして、その先に待っている高校受験に向けて、努力に努力を重ね、自分の力を出し きって、自信を持って臨むことをここで約束します。義務教育課程最後である中学生でいられるのも時間の問題です。カウントダウンはもう始まっています。ぼくたち三年生は、今後の行事全てに、『中学生最後』が付きますが、だからこそ悔いのないよう、一日一日を精いっぱいがんばりたいです!」
大きな声で言うと、いいぞ、とやじが飛んできた。きっと翔太あたりだろう。
「これまで、本当にどうもありがとうございました!」
深々と頭を下げると、大きな拍手が届いた。生徒会会長として、きれいにまとめられた。 教室に戻るとき、ちょうど体育館のトイレから出てきたやつがいた。谷岡だった。
「どうだった? おれの挨拶。」
思わず口から出ていた。そんな質問をした自分に驚く。なぜこんなやつに感想を聞いてしまうのか、律哉自身全く分からなかった。
谷岡はぽかんとした後、律哉を見て、
「最後、最後って言ってたね。」
と言った。
「そりゃ、そうだろ。おれたちはもう最終学年だから。 先生たちもよく言ってるし。」
「最後じゃなくて、新しい、だよ。」
「はあ?」
谷岡が何を言っているのか理解できず、一瞬パニクる。
「新しい運動会に、新しい文化祭だよ。これから経験することは、みんな新しい。」
「どういうこと?」
「だって、こうして話してる今も、新しい経験でしょ。同じことなんて一つもないよ。時間はいつでも新しいから、どんな瞬間も全部初めてで、新しい。」
そう言って、行ってしまった。
「何だよ、それ!」
谷岡に向かって、律哉は叫んだ。谷岡は、聞こえていないのか、スルーしているのか、振り向かずに歩いていく。
「くそっ。」
何が新しいだ。何が初めてだ。あいつはばかなのか。 どう考えても自分のほうが論理的じゃないか。それなのに、なぜか大きな失敗をしでかしたような気持ちになっている。律哉は、自分をそんな気持ちにさせた谷岡がひどく憎たらしかった。
小さくなっていく谷岡の後ろ姿を見つめながら、唇をかむ。
「......新しい今。」
谷岡が消えていった渡り廊下の先を見据え、律哉はつぶやいた。思わず床を蹴ると、うわばきの底がキュッ、と音を立てた。
やっぱり、あいつのことは好きじゃない。
椰月美智子
作家。神奈川県在住 。著書 に「十二歳 」、「しずかな日々」、「14歳の水平線」などがある。