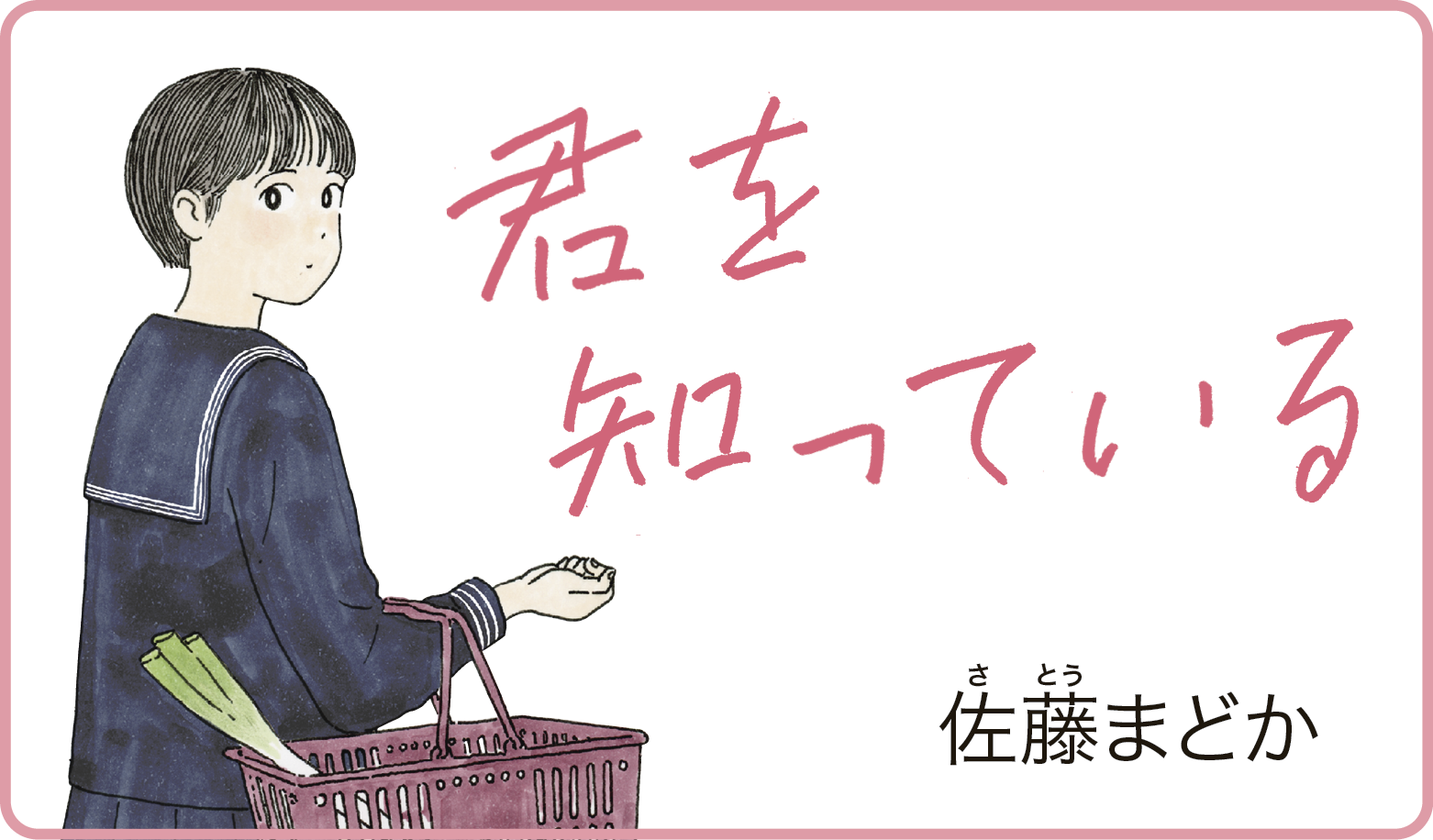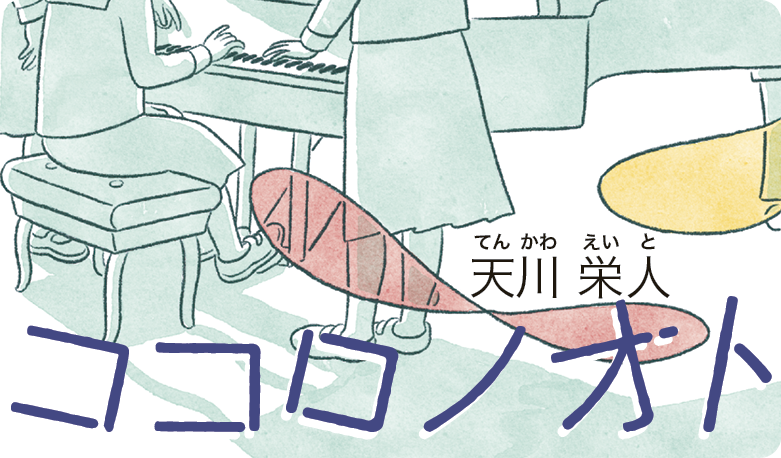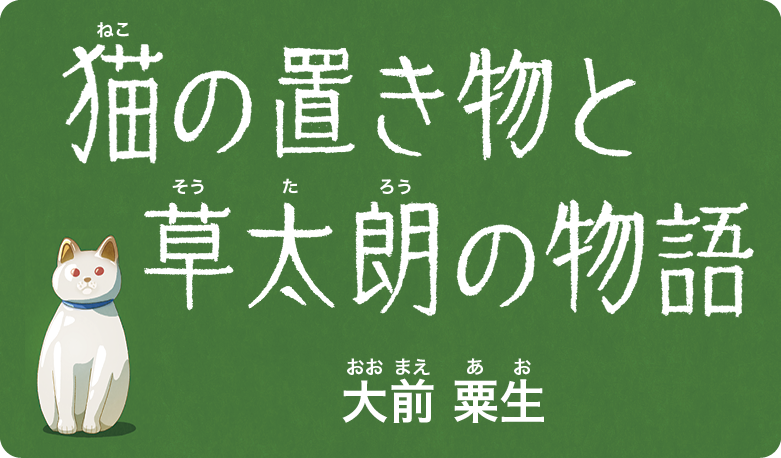パラソルが作る楕円の影の下で、坂井青波は動画を眺めていた。さっきから繰り返し再生しているのは、バレー部の仲間からのメッセージ。一人一言の挨拶の後、最後は部員全員が声をそろえて「青波、これからもずっとずっと友達だよ!」と励ましてくれている。
「青波、泳がないの? せっかく海に来たのに携帯ばっかりいじってるじゃない。」
隣に座る母が、非難めいた口調で画面をのぞいてくる。小さなレジャーシートに二人並んで座っているのだが、母の大きなお尻が半分以上を占領していた。
「海きれいだよう、透明感半端ないよう、ねえ青波、どうしてそんなに機嫌悪いの?」
七月一日付けで父が転勤になり、青波は一学期が終わる三週間前に海があるこの町に引っ越してきた。でも海にも、海がある町にも、正直言って興味はない。
「機嫌? 悪くなるに決まってるじゃん。中二の七月に転校って、ひどくない? 夏季大会の前だよ? それに私、三年生が引退した後はレギュラーになれる予定だったのに......。」
やばい、泣きそうだ。青波はそれ以上の言葉を飲み込み、海の一点を見つめた。本当なら今頃、体育館でバレーボールの練習をしていたはずだ。今のチームはみんな仲が良くて、雰囲気も最高で、できることならあのままずっといっしょに......。
「こんな中途半端な時期に転校させたことは、お母さんも悪いと思ってる。でもお父さんと相談して、今はまだ家族いっしょに暮らそうって決めたのよ。青波が高校に入ったら、もう転校はさせない。お父さんに単身赴任してもらうから。だから今回だけは......。」
「もういいっ。分かったからっ。」
父は保険会社に勤める転勤族だ。まだ幼くて住んでいた記憶がない土地も含めると、仙台、名古屋、浜松、前橋、東京と、青波はこれまでも転々としてきた。小学校は三回転校したし、中学では今回が初めてだけれど、今後もどうなるか分からない。青波だけではない、五歳年下の小三の弟、泳斗も被害者だ。
「新しい学校でバレー部に入れば? あるんでしょ?」
「入らない。できあがったチームに今更なじめないし。」
母には言ってないが、転校先の中学校のバレー部の練習を、ちらりと見学したことはある。体育館は前の学校と同じ油とほこりの匂いがしたが、あたりまえだけどそこにいるのは知らない人ばかりだった。青波が練習を見ていたら、バレー部員の一人が「何か用?」と近づいてきて、思わず無言で逃げてしまった。「私も入れて。」と無邪気に歩み寄った小学生の頃とは違う。
「でも部活に入れば仲良しの子ができるでしょ。友達作りのためにもバレー部に入ったら?」
「だからもういいって。部活はしない。バレーなんかやったって、大人になっても何の役にも立たないし。」
「そんなことないよ。頑張ってきた時間はちゃんと力になってる。生きるための強さになって、いつか自分や、自分の大切な人を守ってくれる。」
「ないない。そんなわけない。現にお母さんにしても、シンクロやってた意味あんの? お母さんなんて、何の取り柄もないじゃん。お菓子ばっか食べてるせいで体重増加も半端ないし。はっきり言ってそのはでなラッシュガードも恥ずかしいから。何でピンクとか選ぶかなあ。もっと黒とか紺とか地味なのにしとけばいいのに。お母さんがピンクなんて着たらブタだよ、ブタ。おばあちゃんの家にあるピンクのブタの貯金箱そっくり。」
言い過ぎだ、と思ったが止まらない。だって、このいらだちをぶつけられる相手は母しかいないから。
「それ言われたらきつい。確かにシンクロやってたときから比べると、十キロ近く体重増えたからなあ。あ、今はシンクロって言わないんだった。アーティスティックスイミングだ。」
へらっと笑いながら水平線に視線を移す母を、青波は横目で見ていた。母は九歳から大学四年生までの十三年間、シンクロナイズドスイミングをしていたらしい。現役の頃は百メートルもの距離を潜水したり、体におもりを付けて立ち泳ぎを続けたりハードな練習をしていたというが、今は見る影もない。普通のぽっちゃり太ったおばさんだ。
「ほらね。だからさあ、部活なんてやっても意味ないんだって。実際に......ちょっと、私の話、聞いてる? ねえ、お母さんってばっ。えっ、どうしたの?」
目を細めて水平線を眺めていた母が、突然立ち上がった。青波の左側に小さな風が巻き起こる。
「あそこ......人が溺れてる。青波、すぐにライフセーバーの人呼んできてっ。早くっ。」
母が早口でまくし立て、砂を蹴って海へと走りだした。
まっすぐ、ものすごい速さで海に入っていくその背中を、青波は全身を硬くしながら見つめていた。
「お母さんっ!」
やっと声が出たときはもう、母は海の中に消えていた。
「......青波、どうした?」
肩をぽんとたたかれ、我に返る。
「あ、お父さん......。」
「かき氷買ってきたぞ。青波はレモン味でよかっ......。」
「お父さんっ! 人が溺れてるんだってっ。ライフセーバーを呼んできてっ。急いで、早くっ。」
父に向かってそう叫ぶと、レジャーシートの上の浮き輪を手に取った。さっきの母のように砂を蹴り、海に向かって思いきりダッシュする。まっすぐに。お母さん、お母さん......と胸の内で母のことを呼びながら。
波の音も人の声も、もう何も聞こえない。
お母さんを助けなきゃっ――。
青波は頭から浮き輪をかぶり、水しぶきを上げて浅瀬を走ると、そのまま勢いをつけて海に飛び込んでいった。
浜辺から二十メートルほど離れると急に足が着かなくなり、それ以上沖に進むのが怖くなった。体を反転して、海底に足が届く場所まで戻る。すると青波の後を追うかのように黄色いボートが近づいてきた。ボートには高校生くらいの男子が乗っていて、今にも泣きだしそうな顔で必死にオールを動かしている。
「すみません、こっちの方に女の人が泳いでこなかったですか?」
波に体を持っていかれそうになりながら、青波はボートをこぐ男子に尋ねた。
「い...... 今、あっちに......。友達が、溺れて沈んで......。そしたら女の人が泳いできて、『私が助けるから大丈夫よ。』って潜ってくれて......。」
色を失った唇をぶるぶると震わせながら、男子がオレンジ色のブイが浮く方を指差す。潜っていると聞き、青波は十数メートル先に目を向けた。だが目を凝らしても銀色の海面があるだけで母の姿は見えない。
「その女の人、私のお母さんなんです。」
そうつぶやくと、唇を震わせていた男子の目から涙がこぼれ落ちる。その泣き顔は子供のように幼くて、青波は下唇を強くかみ締めた。
「青波っ。」「青波っ。」と自分の名前を呼ぶ声が聞こえ、振り返ると父と泳斗が手で合図をしているのが見えた。浜辺に戻ってこい、と叫んでいる。二人が呼んできたのかライフセーバーが、細長い浮き輪――ライフガードチューブを片手に持ち、浅瀬を一気に駆けてくる。
「あそこですっ。あのオレンジ色のブイの辺りで、私のお母さんが潜っていますっ。」
砂浜に戻る途中、すぐそばを走って通り過ぎようとしたライフセーバーに向かって、青波は叫んだ。
「分かりました。危ないから、君は戻って。」
ライフセーバーが水をさくようなクロールで母の元に向かったちょうどそのとき、波に漂うオレンジ色のブイが大きく揺れた。
「お母さんっ!」
母が水の上に顔を出している。間違いない、あれは私のお母さんだ。青波はその場に立ち尽くしたまま、母を見ていた。目を凝らせば母が両腕で人を抱え、立ち泳ぎをしているのが分かった。
「青波っ!」
「お姉ちゃん!」
いつのまにか、父と泳斗が青波の近くまで来ていた。二人とも不安げな顔を沖の方に向けている。
ライフセーバーはすでに母の所にたどり着いていた。母に抱かれていた人影が、ライフセーバーの手に渡る。ライフセーバーが、溺れていた人の体にライフガードチューブを巻き付けるのを、母が立ち泳ぎのまま手伝っている。
「お母さ―――ん!」
互いの顔がはっきりと分かるくらい近づくと、青波は母に向かって大きく手を振った。母は青白い顔で立ち泳ぎをしながら、青波を見て笑ってみせる。すでに連絡を入れていたのか、海岸にはライフセーバー以外にも警察や消防の人たちが集まってきていた。
「お母さんっ、大丈夫?」
母が浅瀬にたどり着くと、青波は膝で水を蹴って駆け寄っていった。後ろから泳斗と父もついてくる。
「平気よ。でも風が......風が強くて流されるかと思った。青波、ライフセーバーを呼んでくれてありがとう。」
肩で息をしながら、母が手を伸ばし青波の髪をなでてくれる。水中にいたからか、手が氷のように冷たい。
「助かるといいんだけど......。」
救助された男子が、担架に乗せられ運ばれていく。母は「気道を確保しながら運んできた。」と言うが、男子の顔は紙のように真っ白だった。
「お母さん、もうこんな危ないことしないでよっ。」
本当はもっと別のことを言いたいのに、声がとがる。心配でたまらなかったから、その分声が荒々しくなる。
「ごめんね、もうむちゃはしない。」
本当は、よく頑張ったね、と言いたかった。自分より背の高い男子を抱えて海面に現れた母は、まるで人魚のようだったから......。
優しくてタフな人魚。
力強く泳ぎ続けるピンクの人魚は、涙が出るほどかっこよかった。
「海水浴場で溺れていた高校一年生の男子生徒(16)を素潜りで引き揚げて救出したとして、遠見市沢区の主婦、坂井渚さん(38)に遠見海上保安部が、感謝状を贈った。坂井さんはシンクロナイズドスイミングの経験があり、大学時代にはライフセーバーの資格を取得していたといい――」
母のこの救助劇は、数日後の新聞の地方版に大きく取り上げられた。新聞の記事によると、男子高校生は海岸から四十メートル離れた、水深二メートルの海底に沈んでいたという。救助された後ドクターヘリで病院に運ばれ、その後意識を回復したらしい。
「お母さん、新聞に載るなんてすごいね!」
泳斗が母の写真が載った新聞記事をはさみで切り取っている。父は同じ新聞をあと十部ほど買って帰るからと言い残し、仕事に出かけていった。
「恥ずかしいなあ。感謝状はいただいたけど、本当はものすごく怒られたのよ。」
二次被害につながりかねない行為ですよ、と確かに母は厳しく注意を受けていた。それでも救助した男子の両親からは「あなたがいてくれてよかった。」と涙を流してお礼を告げられた。誰もができることではない。男子を救助したライフセーバーにも、母はそう褒められていた。
誰もができることではない――。
青波もそう思う。十三年間シンクロナイズドスイミングを続けてきた母だから、できたことだ。
「お母さん、これ書いて。」
通学用のリュックに入れたままになっていた「入部届」と印刷されたプリントを、母に手渡す。入部先の「バレー部」と「坂井青波」という氏名はすでに書いておいた。あとは保護者名を記入するだけだ。
「夏休み中も練習あるみたいだから、今日早速行ってみる。十時開始だし、そろそろ出かけなきゃ。」
バレーボールを続けることに、何の意味があるかは分からない。でも今やりたいのなら、頑張るほうが断然かっこいい。
そしていつか大人になったら、私は言うのだ。
頑張ってきた時間はちゃんと力になってる。
生きるための強さになって、いつか自分や、自分の大切な人を守ってくれる。
藤岡陽子
作家。京都府在住。著書に「跳べ、暁」、「金の角持つ子どもたち」、「リラの花咲くけものみち」などがある。