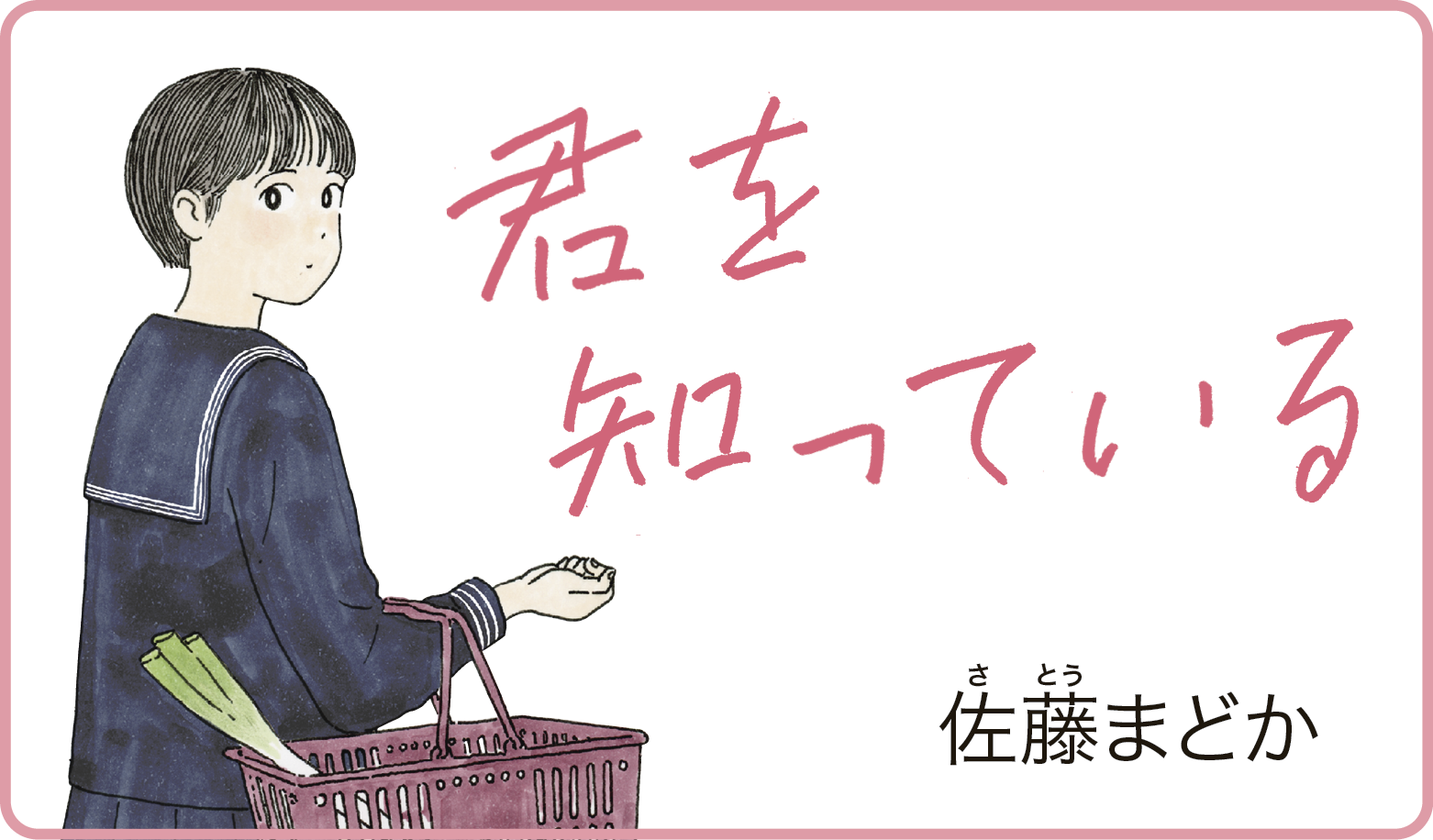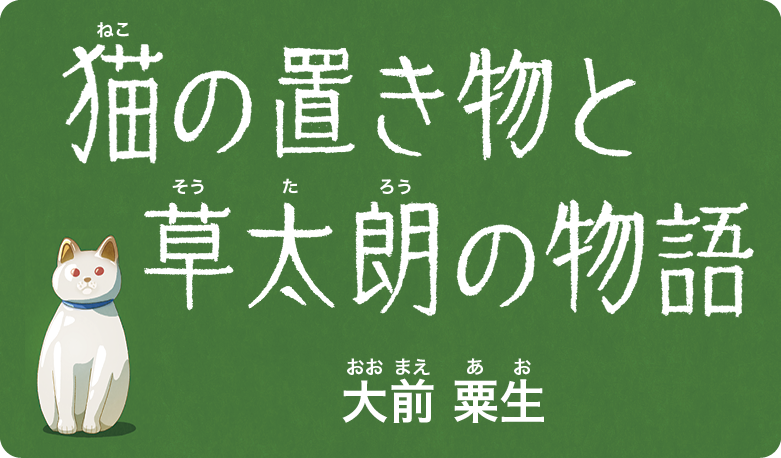詩織には、人の心の音が聞こえる。
相手の考えていることが読めるわけじゃない。ただ、音が聞こえる。詩織はそれを、心の音と呼んでいる。
心の音は、一人一人違う。
例えば、おばあちゃんの音は、シだ。
詩織のおばあちゃんは、隣町でピアノ教室をやっている。詩織も少しだけ習ったことがある。おばあちゃんは穏やかで優しくて、でも指導はしっかり厳しかった。
そんなおばあちゃんのシは、りんと澄みきっていて、美しい。おばあちゃんらしい音だ。心の音は、その人自身を表すのだと思う。
去年亡くなったおじいちゃんの音はミで、おばあちゃんのシと、きれいに響き合っていた。元バイオリニストのおじいちゃん。二人は本当にぴったりのペアだった。
そう、音には相性がある。
例えばドとソのペアは安心感があるけど、ファとシだと、きれいだけど少し不穏な感じ。ドとド#になると、かなり不快な、耳障りで濁った音になる。
だから、周りの人の心の音を聞けば、何となく相性が分かる。この二人は親友になるかも、とか、この二人はうまくいかないな、とか。まあ、詩織は別に友情アドバイザーとかではないので、口には出さないけど。
というか、こんなこと人に話せっこない。
何より困るのが、自分自身の心の音は聞こえないってこと。そのせいで、詩織は今、悩んでいる。
佳奈美の音はドで、唯の音はレだ。
佳奈美は、詩織が一年のころクラスで初めて仲良くなった友達だ。バレー部で、えりあしを刈り上げるくらい髪が短くて、歯に衣着せぬ豪快な性格。
佳奈美のドは、ラッパみたいな、楽しい音。
対して唯は、詩織と同じ美術部で、いつでも冷静な秀才タイプだ。背筋をぴんと伸ばし、長いポニーテールを揺らして歩くさまがかっこいい。
唯のレは、お琴のような、潔い音。
佳奈美も唯も、詩織の大切な親友だ。二年になって、偶然三人とも同じクラスだったから、自然と三人でつるむようになった。でも......。
佳奈美の音はドで、唯の音はレ。
ちょっと弾いてみれば分かるけど、隣り合うこの二音の組み合わせは、とても座りが悪い。お互い主張し合って、調和しない感じだ。
この二人もそう。
佳奈美に言わせると、唯は「気取っててえらそう」だし、唯にとっては、佳奈美は「子どもっぽくて付き合ってられない」らしい。けんかするほどではないけど、佳奈美と唯は、いつも小さなことで言い合っている。
だから、詩織は最近、いつもぴりぴりしている。
佳奈美とくだらない冗談を言い合いたいけど、唯にあきれられるかな、とか。唯と昨日読んだ本の話をしたいけど、佳奈美にかしこぶってるって言われるかな、とか。それぞれと二人きりのときはこんなこと思わないのに、三人いっしょになると、どう振る舞っていいか分からなくなるのだ。
で、ついに、ある日の放課後。
「詩織、うちらといっしょにいて楽しい? 最近の詩織、何かつまんないんだけど。」
佳奈美にずばっと言われて、詩織は、動けなくなった。まるで心臓が止まったみたいに。
「佳奈美、そんなふうに言うことないでしょ。」
唯の言葉もまた、鋭くとがっていた。
「は? 唯だってそう思ってるくせに。」
「それにしたって、言い方があるでしょ。」
「うるさいな、唯は黙っててよ!」
二人は大声で言い合い始めた。止めたいけれど、どっちの味方をすればいいんだろう。結局何も言えない。
そこで、ふと気づいた。
もしかして、三人がうまくいかないのは、私のせい? 二人の心の音の相性が悪いのだと思っていたけれど、実は私のほうこそ、調和を乱す存在なのでは?
「あの、えっと、ごめん!」
そう言い残し、詩織は逃げ出してしまった。
「あらあら、それはたいへんでしたね。」
詩織の足は、自然と、おばあちゃんちに向かった。
心の音のことを知っているのは、おばあちゃんだけだ。ほかの家族にも話したことはあるけど、真面目に取り合ってもらえなかった。おばあちゃんだけが「似たような人を知っていますよ。」とうなずいてくれたのだ。
おばあちゃんちのピアノの部屋。グランドピアノの前のソファに座り、詩織はつぶやく。
「私、何かちょっと疲れちゃった......。」
すると、おばあちゃんは立ち上がり、
「どうやら、詩織には調律が必要みたいですね。」
そう言って、誰かに電話をかけ始めた。
「調律の相談を頼める? 今すぐ。ええ、今すぐ。......ふふふ。何度も言わせないで。今すぐよ。」
受話器の向こうで誰かの焦った声がしたけれど、おばあちゃんは謎の迫力で抑え込み、電話を切った。
で、数十分後。
「緑子さん、困りますよ!」
汗だくでやってきたのは、くたびれた作業着を着た男性だった。肌は生白く、髪はぼさぼさ。大学生のようにも、四十代くらいにも見える。おばあちゃんを緑子さんと呼ぶなんて、いったいどういう関係なんだろう。
「詩織、このかたは調律師の神崎さんです。神崎さん、こちら孫の詩織。」
おばあちゃんは簡単に紹介を済ませると、
「じゃあ、よろしくね。」
と言って、別の部屋に引っ込んでしまった。
ピアノの調律なら、詩織も一度見たことがある。調律師さんがやってきて、音のずれや、鍵盤のタッチを調整してくれるのだ。でも、それって楽器の話でしょう?
詩織が戸惑っていると、神崎さんは耳に手を当て、小さな音を聞くようなしぐさをした。そしてやぶから棒に、
「あー、ずれてるね、確かに。」
「えっと、ずれてるって、何が?」
「音。君の。」
どきっ。この人、今、何て言った?
神崎さんはチューニング用のハンマーを取り出すと、手のひらをたたいて調子を取りながら、尋ねた。
「何があったか、聞かせてもらえます?」
詩織はまごつきながら、これまでのことを簡単に話した。心の音のことも。
神崎さんは詩織の話を疑ったりしないで、素直に聞いてくれた。まるであたりまえのことみたいに。そして詩織が話し終わると、
「ふーん、なるほどね。」
神崎さんはおばあちゃんのピアノの前に座り、人差し指で鍵盤を押さえた。
ド。佳奈美の音。
それから、レ。唯の音。
最後に二音を同時に......うっ。やっぱり、嫌な響き。思わず渋い顔になる詩織に、神崎さんは言った。
「ソね。」
「え?」
「君の音。ソ。」
「あ、え、そうなんですか。」
あまりにあっさり言われるから、拍子抜けする。やっぱりこの人にも、心の音が聞こえるんだ。
「ま、自分の音はね。分かりにくいよね。」
神崎さんは、次に、三音を順番に重ねて弾いた。
ド、レ、ソ......。
「あれ?」
詩織は、ぱちぱちまばたきした。
佳奈美と、唯と、詩織の音。
ちょっと緊張感はあるけど、二音だけのときよりずっと座りがいい。暗闇から明るい方へ抜けるような音。何かが始まりそうな音。
「悪い組み合わせじゃないよ。ミとかシが加わるとさらにいい感じになる。」
神崎さんはその五音を奏でた。ド、レ、ミ、ソ、シ。Cメジャーナインスという和音らしい。
「ドとレ、レとミ、ドとシはそれぞれ不協和。だからこのコード全体も、分類としては不協和音ってことになる。でも、きれいでしょ。」
「はい。」
まるで天使が降り立ったみたいな、心地のいい和音だ。これが本当に不協和音なの?
「相性が悪い音どうしの組み合わせでも、間に別の音が入るだけで安定することがあるってこと。人間も同じ。」
神崎さんはピアノの蓋を閉じ、詩織を見た。
「その子たちも、二人きりだとうまくいかないけど、君がいることでバランスが取れてるんじゃない?」
「え、でも......。」
詩織はそうは思えなかった。最近の詩織たち三人は、明らかにがたついている。さっき聞いたみたいな安定した音を奏でているとは、どうしても信じられない。
「だって、ずれてるもん。君の音。」
神崎さんはまたハンマーを取り出して、詩織を指す。
「ほかの二音に引っ張られて、中途半端にずれちゃってる。君の本来の音が出てない。」
「あ......。」
確かに。最近の詩織は、二人の顔色をうかがってばかりで、全然言いたいことが言えなくて。そんなだから、いつのまにか自分の音がずれていって、三人の音が合わさったとき、きしみが生じていたのかも。
「ま、濁った響きが悪いわけでもないんだけどね。」
神崎さんはハンマーで自分の肩をたたきつつ、
「プロペラみたいにバリバリした音の組み合わせや、ガシャンと割れるような不協和音だって、考えようによっちゃ刺激的でおもしろい。そう思わない?」
詩織がうなずくと、神崎さんは続けた。
「人間関係って、仲がいいと悪いの二種類だけじゃないでしょ。大好きなのに、いっしょにいると疲れるとか。気が合わない相手だけど、ペアを組むとなぜか仕事ははかどるとか......ほんと複雑。でもだからこそ、おもしろい。ばっちり気の合う相手だけが正解じゃないよ。」
神崎さんの言葉は、ちょっと難しかった。でも詩織は真面目な顔でうなずいた。
「いずれにせよ、君の音のずれを正すためには、一回ちゃんと本音を話してみないとね。三つどもえの大戦争になるかもしれないけど。」
詩織はプッと吹き出した。
「それが調律なんですか?」
「そうだよ。」
でも神崎さんは大真面目だ。
「無理してずーっと弦を張り詰めてたら、疲弊して、あるとき、ぷつんといっちゃうよ。」
神崎さんは最後、ちょっとだけ笑って、言った。
「頑張ってね、詩織さん。」
次の日の朝。佳奈美と唯が二人して頭を下げるから、詩織はびっくりしてしまった。
「詩織、昨日はごめん。二人で話し合って、ちゃんと謝ろうって......。」
佳奈美が素直に謝るなんて、珍しすぎる。それに、二人で話し合ったって......。
詩織は唾を飲むと、勇気を出して、言った。
「私のほうこそ、ごめん。なかなか本音を言えなくて。二人に嫌われたくなかったの。」
すると、佳奈美は気まずそうに頭をかき、
「やっぱ、うちらのせいで無理させてた?」
「え?」
「心配しなくて大丈夫だよ。うちら、これでもそれなりに楽しくやってるから。」
「え......そうなの?」
てっきり、お互いぎすぎすしているのかと。
唯はポニーテールをたらんと揺らし、言った。
「詩織がいなかったら、佳奈美みたいなタイプの子と付き合うことなんてなかった。」
「それな。けっこう新鮮っていうか、おもしろいよ。」
「たまにむかつくけど。でも、友達でしょ。」
唯と佳奈美がほほ笑むと、詩織の胸が暖かくなった。
緊張が緩み、心に風が吹き抜ける。詩織は自分の心の中で、澄んだソの音が鳴るのを聞いた。
天川栄人
小説家。著書に「おにのまつり」、 クガコー天文部シリーズ、「わたしは食べるのが下手」などがある。