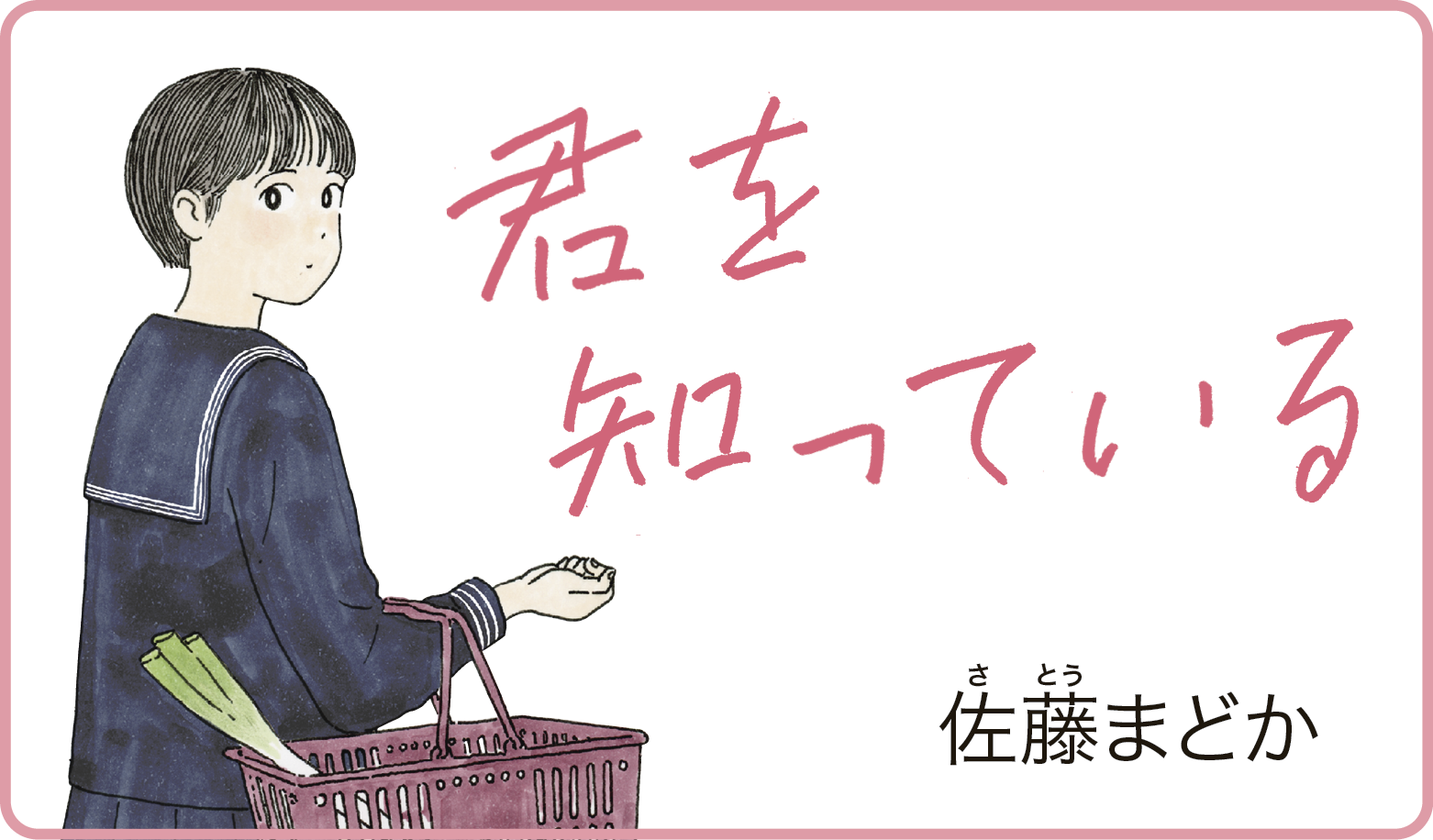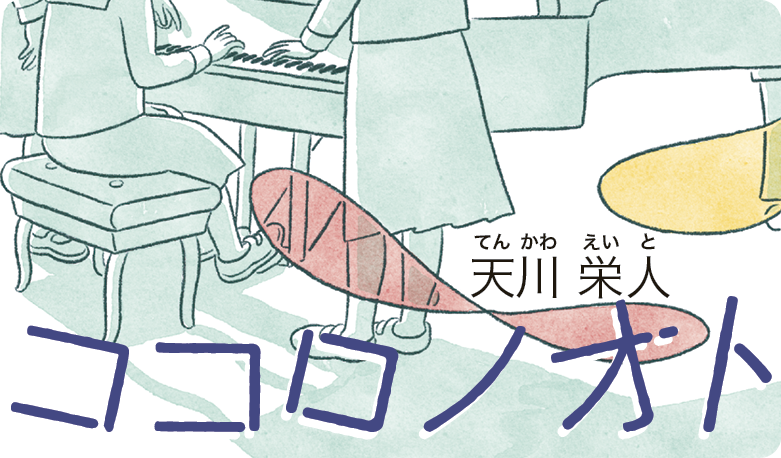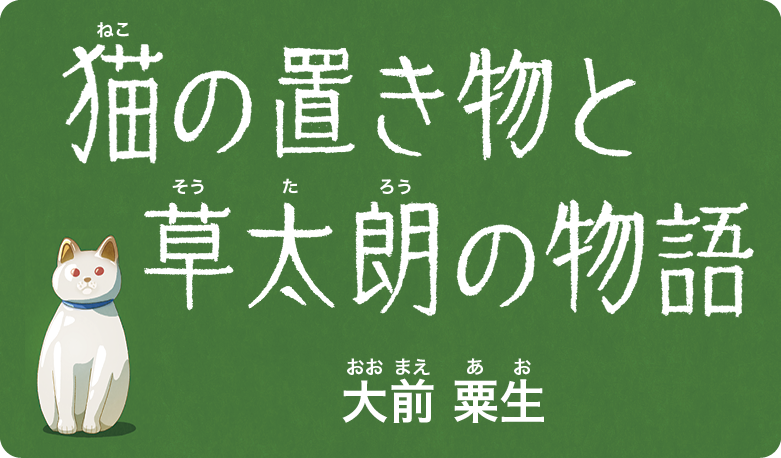「コーポむらい」の二階のつきあたりの3LDKに、ミリとミリの両親はもう14年近く住んでいる。ミリが生まれた年に引っ越してきたというから、そういう計算になる。妹のサラは4歳だから、ここに住んで4年だ。コラルド・フェルナンデスの居 住歴が何年であるかは、よく覚えていない。
「悪いけど、お願いね。」
玄関の鏡に向かってあわただしく髪を整えながら言う母に、ミリは返事をしなかった。返事をしないことで、遺憾の意を表明したつもりだった。日曜日の朝から留守番を頼まれた。友達との約束があったにもかかわらずだ。今日はミリの誕生日で、サラは熱を出してねこんでいる。遺憾でないほうがどうかしている。
友達3人が誕生日を祝ってくれるはずだった。みんながお金を出し合って買ってくれたケーキを食べ、プレゼントをもらう予定だった。ミリが彼女たちの誕生日にそうしてきたように。行けなくなったと連絡したとき、みんなはなぐさめてくれた。しかたないよ。大丈夫、来週の日曜日に延期しようよ。そう言ってくれはしたが、来週の日曜日はミリの誕生日ではない。
父は病院に勤めていて、日曜日に休めることはめったにない。母は働いている会社は基本的に土日休みであるのだが、しょっちゅう「急な仕事」というものが発生し、呼び出されて出かけていく。
「ねえ、お母さんのイヤリング見なかった? 片方ないの。」
母は玄関で靴をはいている。ミリはキッチンに移動しながら「知らない。」と声を張り上げた。
「オパールの、楕円形のやつなんだけど。」
「知らないってば。」
うんざりしながら、朝食のシリアルを皿にぶちまける。「いってきます。」に続いた「ごめんね。」は、聞こえなかったふりをした。皿を持って居間に移動すると、ソファーに放り出されたコラルド・フェルナンデスが丸い目でミリを見上げていた。
コラルド・フェルナンデスはパペットだ。手を入れて、口をぱくぱくと開閉させられるようになっている。スナップボタンで取り外しできる黒い帽子に丈の短いはでなジャケットという、闘牛士風の衣装を身に着けている。ジャケットにはビーズやスパンコールや鏡を丸く小さく切りぬいたものがみっちり縫いこんである。口ひげをたくわえているので、コラルド・フェルナンデスはおじさん人形と呼ばれるときもある。買ったものなのか、もらったものなのか、なぜコラルド・フェルナンデスという名なのか、それが元から付いていた名なのか、はたまた両親のどちらかが付けた名なのか、ミリは知らない。ミリが知らないのだから、サラも知らないだろう。
幼児であることを差し引いても、ミリの目には、サラがあまりものを知らない、かしこくない子に見える。サラはテレビの中の人にもこちらの声が聞こえると思いこんでおり、熱心に話しかける。そうかと思えば突然「お姉ちゃん、ジュースにお水を入れたら、いっぱい飲めるんじゃない?」と言いだしたりもする。味がうすくなるだけだからやめときなよというミリの制止をよそにサラはりんごジュースのコップを片手にキッチンに突進し、何をどうしたものかそこら一帯を水浸しにして、なぜかミリが母にしかられた。
サラには自己主張が強すぎる一面もある。ミリが父や母と話しているとき、必ずと言っていいほど割りこんでくる。サラが生まれる前の話でもおかまいなしに「知ってる、それはね。」などと言いだすのだ。
この家では「痛いの痛いの飛んでいけ。」というおまじないが使われない。誰かがけがをしたときや腹痛を起こしたときは、父も母も「痛いの痛いの、ぱくぱくぱく。」と言いながら、コラルド・フェルナンデスの口を動かす。誰かが失敗して落ちこんでいるときや苛立っているときなどもそうだ。悪いものは全部、コラルド・フェルナンデスが食べてくれる。
ミリは、サラに会話に割りこまれるたびに苛立つ。でもその気持ちはうまくかくしているつもりだ。いちおう姉ですので、という思いがミリにはある。でも両親は気づいているらしい。ミリの苛立ちを察知するたびにパペットを持ち出す彼らは、でも、そんな茶番がもうとっくにミリに通じなくなっていることにはいまだに気づいていない。
朝食をものの5分で食べ終え、ミリはサラの部屋に向かう。水色のカーテンが数センチ開いていて、そこから差しこむ日光が床に散乱するぬいぐるみやクレヨンをくっきりと照らし出していた。踏まないようにつま先立ちでベッドに近づき、のぞきこむ。サラは枕を片頬に押し付けるようにして眠っていた。いちばん熱が高かったときには赤い顔をしながらも元気に遊んでいたのに、少し熱が下がった昨晩からはずっと眠り続けている。じっと見ていたら、ぱっちりと目を開けた。「ご飯食べてお薬飲もうか。」と声をかけると、首を横にふる。
「おかゆ、いや。」
そこから、怒涛の「いや」が始まった。パンもいや、スープもいや、ミリちゃんいや、ママがいい。
「そんなこと言わないの。」
きつい口調で言ったつもりはなかったのに、サラはびくっと体を震わせ、それから声を上げて泣きだした。ミリはその様子をながめながら、途方に暮れる。
サラはずるい。
部屋を散らかしても、台所を水浸しにしても、いやいや言っても、全然おこられない。
ミリは再びつま先立ちで居間に取って返し、ソファーに転がっていたコラルド・フェルナンデスを連れてきて、サラのいやいやを食べつくした。茶番だと知りながらも、ミリはほかに妹を落ち着かせる方法を知らない。
「ほうら、サラちゃんの悲しい気持ちを、全部食べちゃうぞ。ぱくぱく。」
言いながら、ばかみたいだと思った。こんな芝居がかった作り声を出したりして。もし誰かに聞かれたらはずかしくて3日は部屋から出られない。
それから何とかサラにりんごジュースを飲ませ、ミルクプリンにしのばせた薬を服用させた。歯みがきをさせてベッドに連れ戻すころにはミリはもう疲労困憊の状態で、サラの隣にごろりと横になる。
ああ、いやだ。「姉」なんて何にもいいことがない。コラルド・フェルナンデスは腹が立たないのだろうか。他人の肉体的な痛みやネガティブな感情ばかり食べさせられて、いいかげんうんざりしているのではないだろうか。ミリならとっくに逃げ出しているところだ。
でも、コラルド・フェルナンデスは逃げられない。だって人形は自力で動けないから。ミリがこの家の長女という立場から降りられないように、コラルド・フェルナンデスは人形であることから降りられない。
「サラはずるいよ。」
言葉が勝手にこぼれ出た。ぱちぱちとまばたきをしたサラは「ミリちゃんのほうがずるい。」とつぶやく。変なことを言う子だ。そんなわけがあるか。
「なんで。」
サラは答えない。なんで、なんで、ねえなんでなんで、としつこく質問を重ねて、ようやく「だって」という言葉を引き出した。
「だって、パパとママとミリちゃんはサラの知らない話ばっかりして、ずるい。」
どうしてもすぐに返事をすることができずに、しばらく黙っていた。
ミリには両親との3人きりの時間が、10年分ある。先に生まれた。ただそれだけのことが、もしかしたら妹の目にはとてつもなく良いものに見えるのかもしれない。
サラはやっぱりあんまりかしこくないんだな、と思った。サラだけじゃなくてたぶん私も、とも。かけぶとんの上に転がっていたコラルド・フェルナンデスを持ち上げると、いつのまにかスナップボタンが外れた帽子から、何かが転げ落ちた。
母が探していた、オパールのイヤリングだった。
「サラがここにかくしたの?」
「サラ、知らないもん。」
とぼける妹の頬をつんと突く。やわらかくて、少し冷たかった。もう熱はすっかり下がったようだ。
出産のため入院していた母が無事退院し、サラを連れて帰ってきた日のことを、ミリはよく覚えている。頭も手も何もかも全部小さくて、でも何もかもが、完璧にそろっていた。かわいいサラ。私の妹。サラが生まれた日のことを、ミリは覚えている。でもサラはミリが生まれた日のことを知り得ない。

オパールは不思議な色の石だ。乳白色のもやに包まれたその奥に、さまざまな色をかくし持つ。ミリが手をかたむけると、オレンジ色がかっていた部分が黄から緑に変化し、カーテンのすき間からもれる光に当てると、青みがかって見えた。早朝や真昼や夕暮れや、そんないくつもの空を少しずつ切り取って、雲でくるんで結晶にしたみたいだ。
「ねえ、見て。」
サラが天井を指差す。丸い光が、右から左にちらちらと動く。コラルド・フェルナンデスのジャケットに縫い付けられたかざりが、日光を反射している。サラはオパールではなく、そちらに夢中になっていたらしい。
「きれい。」
サラは手をのばして、光をつかまえようとしている。小さいな、すごく小さい手だなと、毎日見ているのに、今初めて見たようにミリはおどろいた。
「つかまえた?」
「つかまえた!」
サラがぐっとにぎりこんだ手をコラルド・フェルナンデスの前でぱっと開いたから、ミリは急いで、彼の口を動かした。「わぁ、うれしいな。」と言ってみる。芝居がかった作り声ではない、本物の自分自身の声が出た。
そのうちにサラはまた眠ってしまったけれども、ミリは居間にも自分の部屋にも戻らなかった。あおむけになったまま、サラのやわらかい髪に自分の頬をくっつけて、天井の小さな光をいつまでも見つめていた。
作家。佐賀県出身。著書に「夜が暗いとはかぎらない」「水を縫う」などがある。