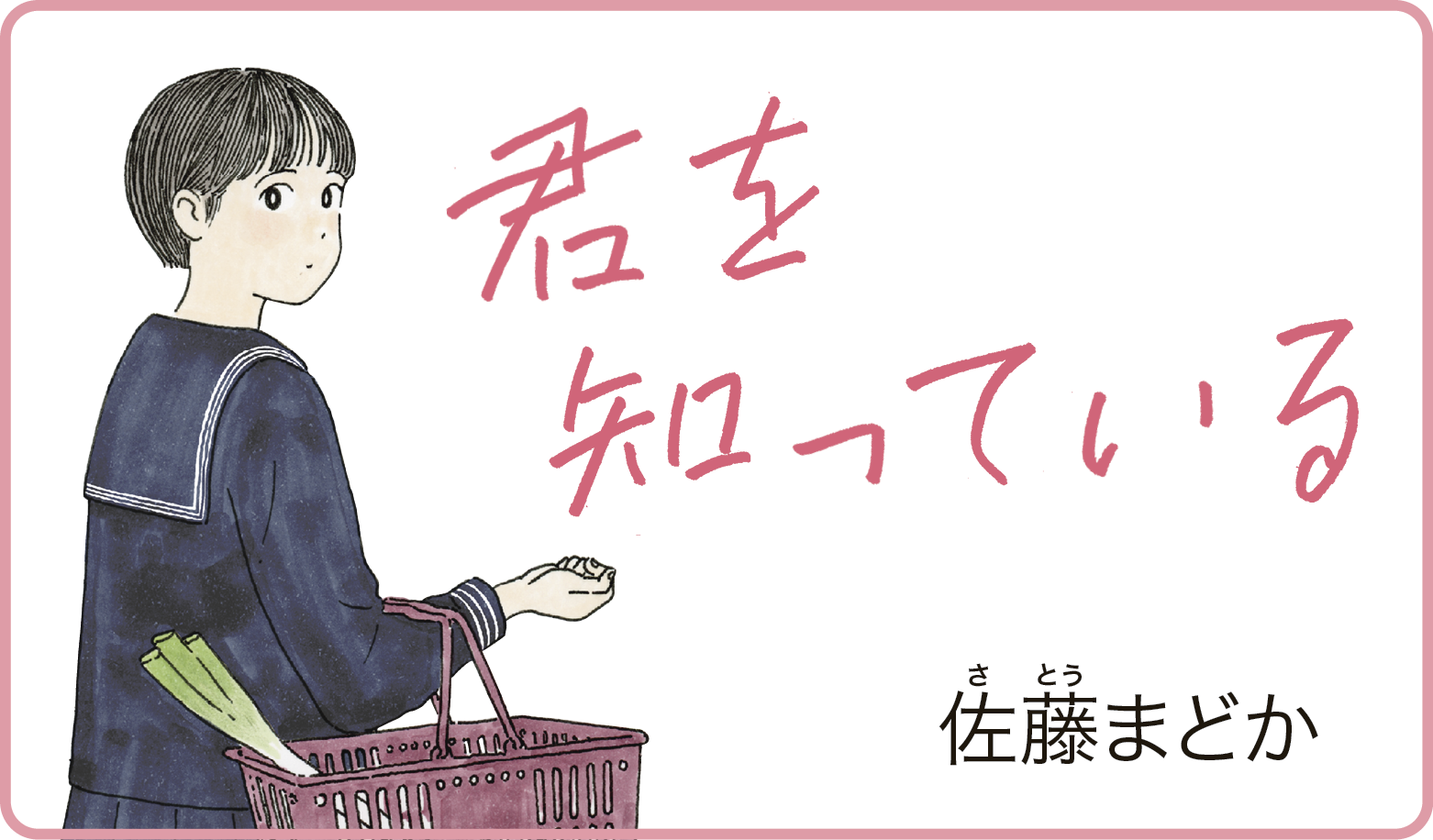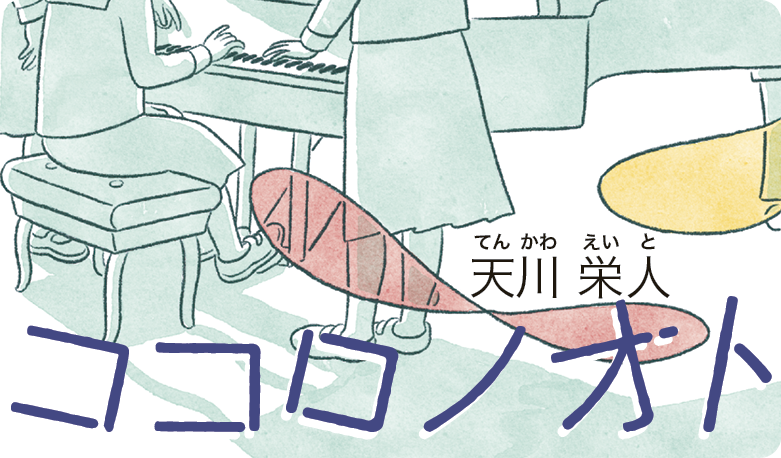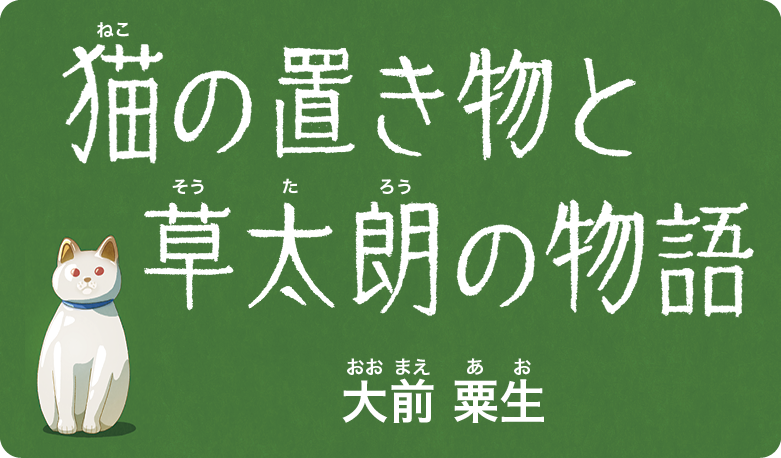ピッ。三百九十八円。
スーパーのレジで働いている
夫の
しかし仕事を終えた時間に、目当てのイチゴは売り切れていた。真由美は、
帰りの
アパートに着いて、ドアを開けると、
「ただいま。翔太。帰ってんの?」
返事がない。
「返事がないから入るよ。」
真由美は、わざと
ベッドにうずくまっていた翔太が顔を上げた。その目は真っ赤だった。
「勝手に入んなよ!」
真由美は立ちつくす。
息子の背中に手をそえる自分を
学校で何があったの?
答えは分かっている。大丈夫。ほっといて。
いつのまにか、子供の心の中が見えなくなった。
何と話しかけようかと思っていると、玄関から「ただいまあ。」と元気な声がした。結愛が、学童から帰ってきた。
「ねえ、お母さん、聞いてる?」
結愛にシャツを
「危ない!」
まな板で野菜を切っていた真由美は、つい
学童から帰宅した結愛は、真由美の
カレーの
「今からちょっと買い物に行くから、
と、結愛に言った。
「
「自転車でちゃっちゃと行っちゃうから、結愛は家にいて。ユーチューブ見てていいから。」
そう言うと、結愛はだまる。
「七時からご飯ね。」
真由美は、翔太にも聞こえるように大きな声で言うと、
夕食前の店内は
買い物かごを手にするのももどかしく、真由美は足早に果物のコーナーを目指す。
あった。ほっとして、残っていたイチゴのパックをそっと手に取った。安いイチゴは早い時間に売り切れてしまったが、高級ブランドのイチゴはまだ残っていた。その値段に
自転車のペダルをこぐと、夜風が
――何かが起こってからじゃ、
ふと、スーパーで働く人たちがこの道について話していたのを思い出す。ガードレールを付けてくれればいいのにね。
どうしてなんだろう。
真由美は思う。あれを聞いたのは一年以上前のことだ。 どうしていまだにガードレールは付いていないのだろう。
「カレーだよ。」
真由美が陽気な声を出すと、
「やったあ! カレーだ! おいしい!」
結愛がはしゃぐ横で、翔太はもくもくと食べている。
翔太の
「翔太、どう? カレーの味は。」
結愛のおしゃべりをさえぎり、真由美は、ずっとだまっている翔太に問いかけた。翔太はどこか
「お兄ちゃん、ぼんやりしすぎ!」
結愛が笑う。
「うるせえな。」
言い返すその声にも、いつもの張りはない。
食事を終えた後、真由美は結愛に「向こうの部屋に行っていて。」と言い、それから翔太に「ちょっと話すよ。」 と声をかけた。
「は?」「ええ、なんで?」
子供二人の不満げな声が重なった。
「お兄ちゃんに、だいじな話があるの。」
部屋にいたがる結愛に「ユーチューブ見てていいから。」 とタブレットをわたした。ようやく翔太と二人きりで向き合う。
「あのさ、学校で
真由美は
「え、なんで?」
翔太がきく。
「顔を見てれば分かるよ。」
翔太は
「いつもスマホばっかり見てるけど、そんなに何を見てるの。」
そうきくと、
「何でもないよ。」
「翔太。言ってくれなきゃ、何も分からないよ。」
「だから、何でもないって言ってるし......。」 と言って、そのまま出て行こうとした翔太に、
「お母さん、帰り道、こわかったんだよ!」 と、真由美は言った。
は? というふうに口を少し開けて、翔太は母親を見下ろす。真由美も、口をついて出た自分の言葉におどろいていた。翔太を引き止めたくて、何か言わなくちゃと思ったのだ。
「スーパーに行く道だよ。前に話したよね? せまいのに、すごく飛ばす車があるって。さっきもお母さんの横を、すごい勢いで車が通ってって、転びそうになった。」
「え、大丈夫だったの?」
翔太が心配そうな目をする。それは、久しぶりに見た、息子の本当の顔に思えた。
「あんなに危ないのに、小さな子も通るのに、あの道、ガードレールが付いていないんだよ。みんな、ガードレールを付けるべきだって言ってる。でも、ずっと付いてない。どうしてだと思う?」
翔太は少しだまってから、「予算がないんじゃね?」 と言う。予算......予算ね。そんな
「お母さん、明日仕事に行く前に、役所に電話してみようと思う。」
と、真由美は言った。
さっき思いついたばかりのことだった。どうしてずっと思いつかなかったのだろうとも思った。
「やめときなよ。そんなの、意味ないよ。」
「意味ないかどうかなんて、分からないよ。こういうことは、自分だけで
すると、翔太がスマホをいじりだす。
「ちょっと。聞いてるの?」
「......それなら、こういうほうが。」
と言って、翔太は何やらスマホの画面を真由美に見せた。役所のホームページ内にある、「
「何、何。」
「えらい人に
「へえ......。」真由美は感心した。「そうか。じゃあスーパーの仲間たちにも声をかけてみるか。ありがとう、翔太。」
真由美の言葉に、翔太は照れくさそうな顔をする。でもその表情はまたすぐ暗くなる。無言で部屋を出て行こうとする。
「待って、翔太。」
真由美はあわてて引き止めた。
「あのさ、本当に言いたかったのは......。」
あんたが心配で心配でたまらないんだよ。
「子供の悩みを知らないことが、大人はとてもつらいってこと。」
真由美が言うと、翔太はうつむいた。
「きついこと、ずっと一人で
息子は何も答えない。
「でもさ、いつまで抱えてく? きついことがあったときに、誰かに頼ることって、だいじな方法だと思うよ。弱さじゃないよ。お母さんじゃ頼りにならないって思っているのかもしれないけど、だったら学校の先生とかほかの大人とか、話せそうな人はいない? 大人に頼らないと
途中でさえぎられるかと思ったが、息子は静かに最後まで聞いていた。
「お母さんも、いつでも話、聞くよ。」
小さくうなずいた息子を見て、真由美は何だか泣きたいような気分になった。
「はい、終わり。さて今日はイチゴがあるんだ!」
明るい声で言いながら、
「結愛もおいで。イチゴだよ!」
真由美はふすまを開けた。
結愛はタブレットを見ていなかった。和室の
「あれ、結愛? どうしたの?」
呼びかけると、結愛は小さく
真由美は近所を気づかい「しーっ!」と言った。
しかし結愛は泣きやまなかった。それどころか、いっそう
「お母さんなんか! お母さんなんか......!」
ふりしぼるような声で「お兄ちゃんばっかり。」と言われて、真由美は気づく。私は今日、この子の話を一度でもちゃんと聞いたのか。
真由美は思わず結愛を
作家。東京都出身。