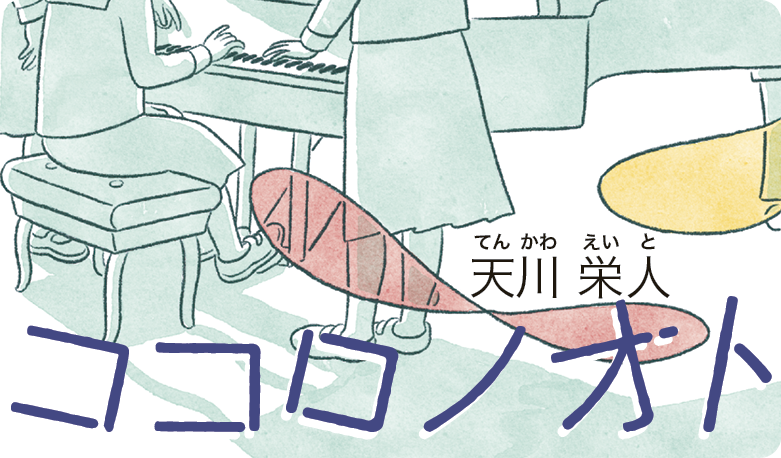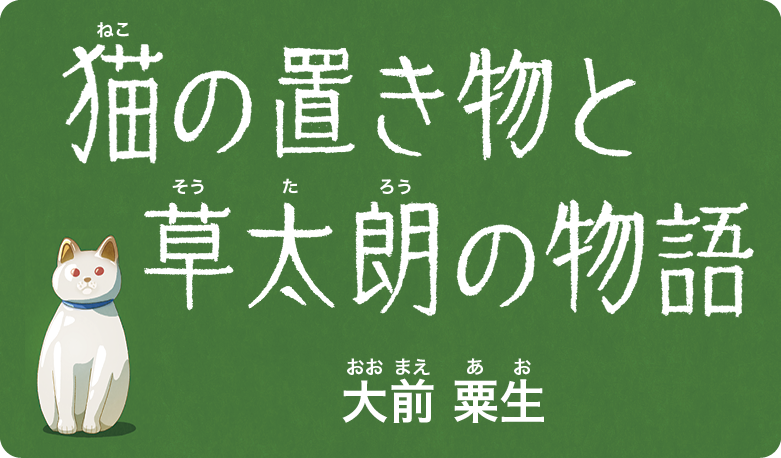転入生の名は五十嵐翔。
だれかが「芸能人みたい。」と言うと、みんな一斉に笑った。
「翔」というのは人気の名前だからよく聞くけど、「五十嵐翔」は本当に響きがよい。
新学期に合わせて大阪から転入する予定だったが、事情で二週間遅れた。
そう説明したのは先生だ。当の本人はずっとうつむいたままで、最後に「よろしくお願いします。」とだけ、つぶやくように言った。
「大阪のわりには、めっちゃ暗いやつだなあ。」と、後ろの席から聞こえてきた。
ざわざわしたカラフルな教室で、五十嵐くんのところだけが白黒みたい。空いていたとなりの席がやっと埋まるから楽しみにしていたけど、話せるかどうか自信がなくなってきた。
五十嵐くんは黙ったまま、となりの席に座った。
ちらっと横を見たら、目が合ってしまった。
長い前髪の奥に隠れたこの目、だれかに似ているような気がする。
とりあえず、「大島友梨奈です。」と、あいさつしておいた。
「五十嵐です。」
小さな声が返ってきた。
昼休みになっても、転入生はだれとも話さない。
私は絵里と窓際に行くと、そんな五十嵐くんを遠目にちらちらと見る。
「ねえねえ、おとなりさんと話せた?」
「ううん、あいさつだけ。さっきからずっと本を読んでいるよ。」
「友梨奈、けっこう楽しみにしていたのにね。」
「まあ、ただの人見知りかもしれないけど。」
それから数日たっても、五十嵐くんはだれともしゃべらず、いつも本を読んでいる。でも、読書好きというだけで、仲間という気がしてくる。私と絵里も読書が好きだ。感想を言い合うのが楽しい。
みんなは、五十嵐くんのことを暗いとか社交性がないとか言うけど、席で目が合うと少し頭を下げてあいさつしてくれるし、静かに読書をしていて、平和でいいと思う。
同じ翔くんでもえらい違いだと、急にあいつのことを思い出した。
小学校三年生のときのクラスに、すごくいやな翔くんがいた。
自称テニス焼けをしていて、おしゃれで、勉強もできて、いつもいばっていた。掃除当番のときも自分だけやらず、人を奴隷のようにこき使っていた。私も「うざい。」とか「きもい。」とか「働け!」とか言われていた。
何だっけなあ、あいつの名字。あ、思い出した。笠井だ。
その日の夕方、私は頼まれていたものを買いにスーパーへ行った。母が仕事帰りに行くと、タイムセールが終わってしまうのだ。
魚売り場で、五十嵐くんを見かけた。金目鯛のお頭が三つ入ったパックをじっと見ているみたいだった。私は、本日の目玉商品のそれを買いに来たのだ。
彼も金目鯛をねらっているのかな? 何も陣取らなくてもいいと思うけど。
店員さんがタイムセールのシールを貼り始め、金目鯛のほうに近づいてきた。
「すみません、前を失礼します。」
店員さんにそう言われても五十嵐くんは一ミリも動かないから、私はおせっかいをする。
「ねえ、じゃまみたいだよ。」
五十嵐くんの腕を軽くたたくと、彼はひえっ! と声を上げて、ホラー映画でも見るような目でこっちを見た。
「そんなにびっくりしなくても。もしかして、金目鯛に恨みでもあるの?」
ちょっと彼をからかいながら、パックにシールが貼られるのを待っていると、おばさんたちが突進してきて、私は押しのけられてしまった。
「ああっ、金目鯛が!」と、思わず叫んだ。
すると五十嵐くんが、群がるおばさんたちの隙間から、シール付きの金目鯛を一パック取って、私に渡してくれた。その間ずっと無言だった。
「ありがとう! じゃ学校で!」
ほかの買い物を済ませ、レジに行く。
振り向くと、トイレットペーパーのパックだけを持った五十嵐くんが私の後ろに並んだ。
「あれ、金目鯛は買わなくていいの?」
もしかして、私に一パックくれたせいで、自分の分はもうなかったのかもしれない。
「いらない。目が怖いから。」
意外な返事に驚いた。その気持ちはちょっと分かるけどね。
「怖いなら、何でじっと見つめていたの?」
「いや、見つめていたのではなくて、にらまれて動けなくなっていた。」
私は思わずププッと笑った。個性的な人だな。
かごの中の物をマイバッグに入れていると、会計を済ませた五十嵐くんが寄ってきた。
「あのう、大島さん、実は......。」
五十嵐くんが、もじもじしている。
「あの、ぼくは......君のことを知っているんだけど......君はぼくのこと、分からない?」
どきっとした。私のことを知っている?
「ううん、その目っていうかまつ毛、どっかで見たことがある気もするんだけど。」
五十嵐くんが眉間にぎゅっとしわを寄せた。
「ぼく、前は、その、笠井という名字だったんだ。」
急に五十嵐くんが頭を深々と下げた。
「え、笠井? 笠井って、あの笠井翔? うっそー!」
私は大声を出していた。
肉付きのよい日焼け男で、自信たっぷりで、えらそうだったあの笠井くんが、今はひょろひょろと背が高くて、青白くて、自信なさげだ。分かるわけがない!
「まるで別人じゃん! 信じられない。そうか、あの笠井くんなのか。何となく、目がだれかに似ていると思ったら。よくきもい、うざいって言われたの覚えてるよ。それに、いつも掃除当番をサボって、私たち女子にやらせていたでしょ?」
五十嵐くんは頭を下げたままだ。
おばさんたちが、同情した目つきで五十嵐くんを見てから、責めるように私をにらむ。
さっき私を押しのけておいて、善人ぶらないでください。
上体を起こした五十嵐くんは、血が上ってしまったらしく、顔が真っ赤になっていた。
「大島さんにいつばれるかと思って、びくびくしていたんだ。でも、いつかはばれちゃうだろうから、もう自首しました。」
自首って......。
「そっちは、ただからかって遊んでいたつもりかもしれないけど、私はあの頃、家族のことでたいへんだったのに、学校でも居心地悪くて、毎日つらかったんだよ。」
ああ、これ、ずっと言いたかったこと。
でも、四年生でクラス替えがあり、笠井くんを学校で見かけなくなった。転校したといううわさも聞いた。まあ、あの頃の私に文句を言う勇気はなかったけれど。家族のことが落ち着いて、学校が楽しくなって、中学では親友もできて、自分に自信がついた。だから、今は言えたのだと思う。
「ごめん。あれからいろいろあって、自分がしたことをすごく反省した。」
そう素直に謝られると、拍子抜けしてしまう。
「あのえらそうな人が、四年間でこんなに謙虚な人になったの? どっちがほんと?」
笠井、いや五十嵐くんは、くちびるをぎゅっとかんで目を伏せた。
目の前の人があの笠井くんなのか疑いたくなるけど、このやたらに濃くて長いまつ毛は、確かに記憶に残っている。
「どっちもぼくだけど......あの頃は、女子をからかって自分のストレスを解消していた。本当に、本当にすみませんでした。」
そのあと、スーパーの前で立ち話をした。
五十嵐くんの話によると、四年生のときに肘を痛めて以来、テニスはもちろんスポーツはやめた。両親が離婚して名字が変わり、前に住んでいた家にお母さんと二人で戻ってくることになったが、いろいろな事情があって、引っ越すのが遅くなってしまったらしい。
「前の家に戻れてほっとしているけど、みんなに身元がばれるのは怖い。」
いつも憂鬱そうな五十嵐くんが、ますます憂鬱そうな表情でそう言った。
「二年A組であの頃のクラスメートっていうと、横川さんと笹塚くんだけかな。班が違ったから、掃除の奴隷にはなっていなかったけどね。でも、ほかのクラスの子にも、いずればれるんじゃない?」
「だよね......どうしよう。」
「きもい、うざいはまだしも、掃除で悔しかったことは、そう簡単には忘れられないかも。」
本音を言った。
「分かるよ。実はぼくも大阪の学校で......。」
ああ、そういうことなのか。
「それでやっと、やられる側の気持ちが分かったってわけね。」
五十嵐くんが大きなため息をつくから、私もつられてため息をついた。
まるで、私が五十嵐くんをいじめているみたいな気がしてきた。
「もういいよ。自首してきたし、時効成立! でもさ、びくびくしているより、みんなにも白状してちゃんと謝ったほうが、五十嵐くんにとってもみんなにとっても、いいんじゃないかな。それに、毎日憂鬱そうだと、こっちまで憂鬱になっちゃう。となりの席なんだし、たまには笑ってよ。」
五十嵐くんは泣きそうな顔になって、うなずいた。
「うん、分かった。」
作り笑いをした五十嵐くんの顔がおかしくて、私は爆笑してしまった。
五十嵐くんも笑った。
今度は本当の笑顔だった。
佐藤まどか
作家。イタリア在住。著書に「一〇五度」、「アドリブ」、「スネークダンス」などがある。