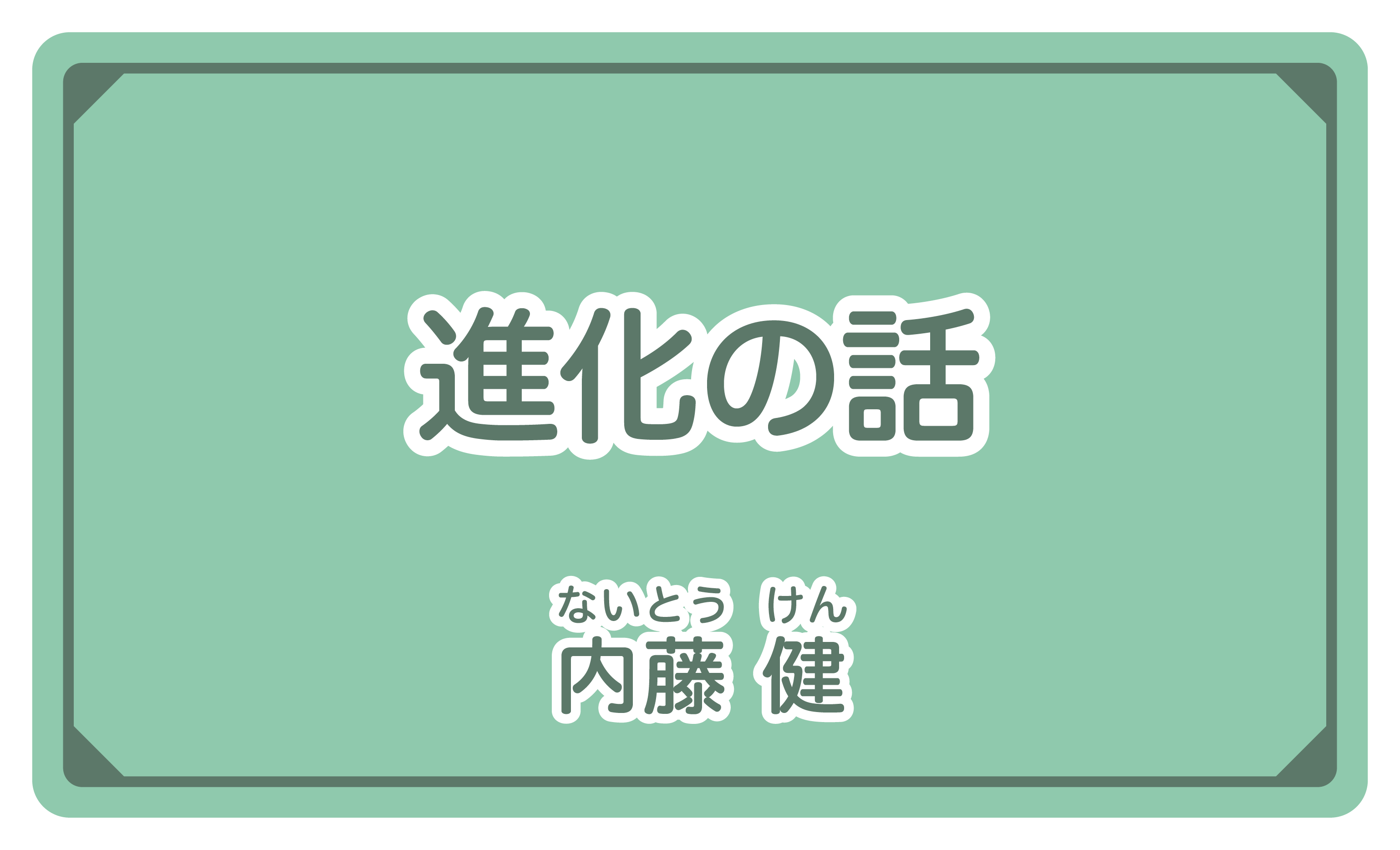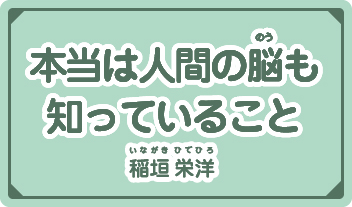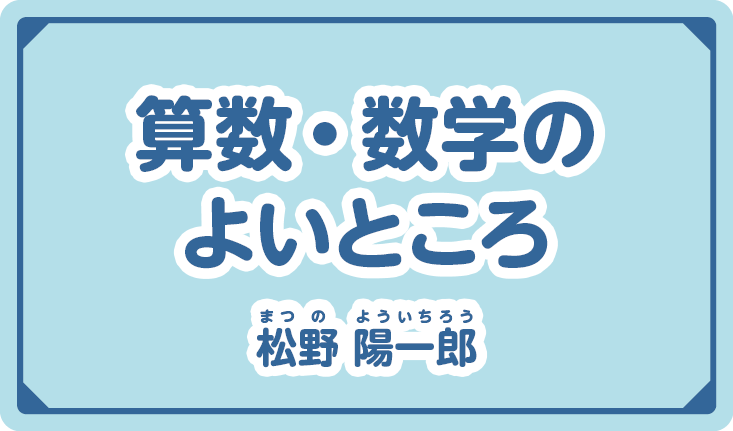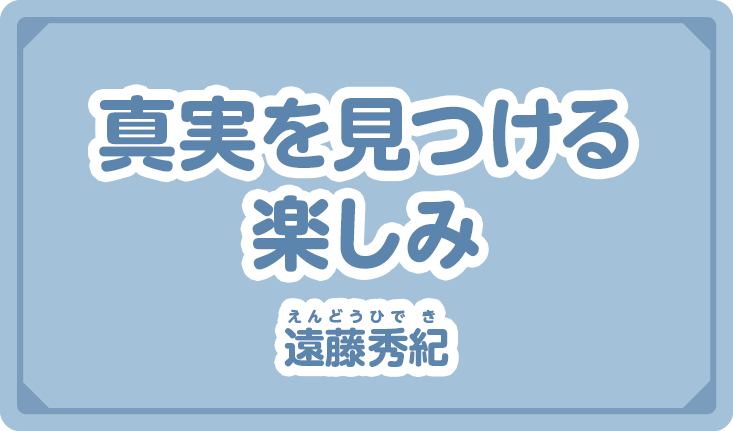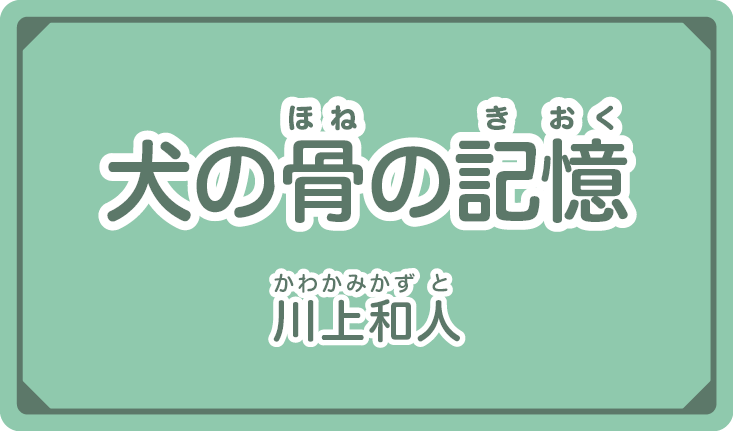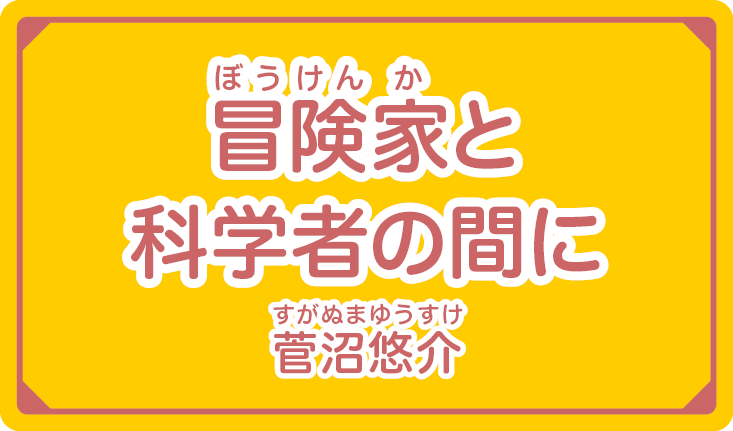こんにちは。私は大学の教員をしていて、魚の遺伝子のはたらきを調べ、それを日常生活に生かせるように研究しています。そして研究成果を活用して作った魚が一般に販売されるようになりました。こんなふうに思っていることが現実になり、研究者として充実しています。
でも、私は小さいときから「研究者になりたい」と思っていたわけではありません。小さいときから思い描いていた「将来」のとおりになったのではないのです。というか、将来のことは全然考えていませんでした。今日は、そのお話をしたいと思います。
家族が犬やねこが好きで、私が物心ついたときから我が家にはペットがいました。いつも何匹かの犬やねこがいて、ご飯をあげたり、散歩に行ったり、いっしょに眠ったり、生き物の世話をすることを楽しみながら、どんなことをすればペットが喜ぶのか観察していました。ねこはなでられて気持ちがいいと喉をゴロゴロ鳴らしますが、ねこによって気持ちのいい場所が違っています。それから、小学校の頃には友達と網を持って川へ行き、ドジョウやフナを捕まえていました。でも、釣りは好きではありませんでした。というのも魚の口に刺さった針を外すとき、魚の口が裂けたり、死んでしまったりするのが嫌だったからです。
それから、機械を分解するのも好きでした。父親の動かなくなった電気かみそりのねじを一つずつ外して、中はどんなふうになっているのか、どんな仕組みでかみそりの刃が動いているのか、どんな順番で組み立てられるのかなど自分で確かめるのを楽しみにしていました。もちろん、元どおりに戻すことはできず、ばらばらになったものはごみ箱行きでしたが。
複雑な機械だけでなく、祖父母や母親が昔ながらの方法で日常的にやっていることの中でも「なるほど、うまくできている」というのを見つけることも楽しみでした。例えば、勝手口の扉にほうきがぶら下げてあるのですが、ほうきの柄の部分に空いている穴に枯れ枝を通し、それを扉の格子に引っ掛けているのです。今ならS字フックを使いますが、身近にあるものでできてしまうのです。大人になった今でも、「工夫がいっぱい」という点でNHKのピタゴラスイッチは大好きな番組です。
こんなふうに子どもの頃は、生き物も機械も自分で観察して、その中で生かされている「工夫」を見つけることが好きでした。
大学を選ぶときは「生き物に関わるのがいいかな」という程度の理由で農学部を選びました。理科系の研究室なので、日々実験をします。実験をして結果が出ると「どうしてこうなるんだろう」という疑問が出てきて、また、実験をします。そのとき、こんなふうに実験すると結果が分かりやすいのではないかと考えを巡らします。やっぱり、小さいときと同様に、工夫を凝らし楽しむ毎日でした。大学と大学院では、魚の筋肉成分に関する研究をしていたのですが、大学院を修了する頃に「分子生物学」というDNAや遺伝子に関する研究がどんどん発展し始めました。ある生物の遺伝子をまとめたものをゲノムといい、ゲノムは生物の設計図といわれています。つまり、遺伝子は生物の設計図の一部で、それを調べることで「生き物の特徴はどんなふうに作られているのか」が理解できます。遺伝子のはたらきを調整することで「特徴を変えていく」ことができるようになり始めたのです。この技術を使って「社会に役立つことをしたい」と思うようになりました。
そこで、私はメダカを使って魚の遺伝子の研究を始めることにしました。遺伝子のはたらきを調べるためには、受精したばかりの卵に調べたい遺伝子を注入する必要があります。でも、当時その方法が確立されていませんでした。まず、その方法の開発から始めました。どうしたら受精したばかりの卵を効率よく集められるか、どうやって卵を動かないように固定しようか、注入するための針はガラス製で手作りなので針の太さはどのくらいがいいのかなど、試行錯誤を繰り返して方法を開発していきました。魚の種類によって卵の形や性質が異なっていますが、メダカでの経験を生かして、今では多くの魚の卵に注射することができるようになりました。そして、遺伝子情報を活用して魚の特徴を改良し、筋肉(人が食べる部分)が多くなったマダイや成長速度が早くなったトラフグなどを販売できるようになりました。
私の場合、子どもの頃からしっかり将来の目標を立てて進んできたわけではなく、「楽しみ」「興味」で続けてきた「自分で調べる、自分で確かめる、そして工夫して何かを作る」が今の自分になっています。 みなさんも「楽しいこと」を見つけて続けていってください。きっと楽しい人生になると思います。
「肉厚マダイ」(左)と通常のマダイ(右)
下の写真の「肉厚マダイ」は、通常のマダイのDNAの一部を除いてつくられた、筋肉が増えたマダイである。

木下政人
分子生物学者。京都大学大学院 農学研究科 准教授。著書に「22世紀からきたでっかいタイ ゲノム編集とこれからの食べ物の話」がある。