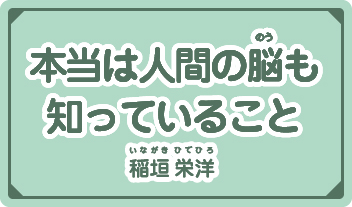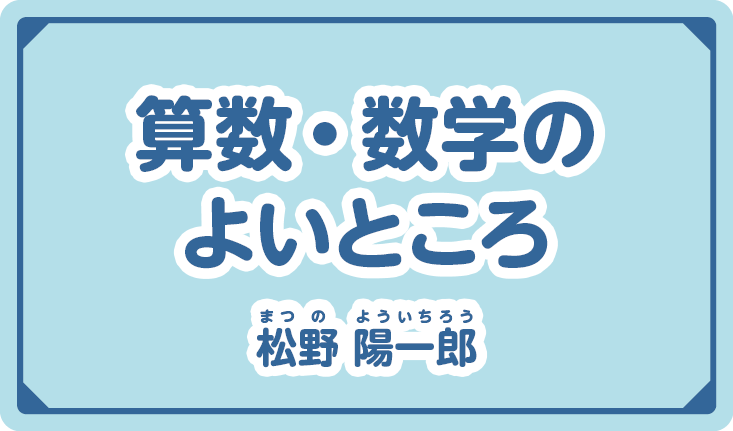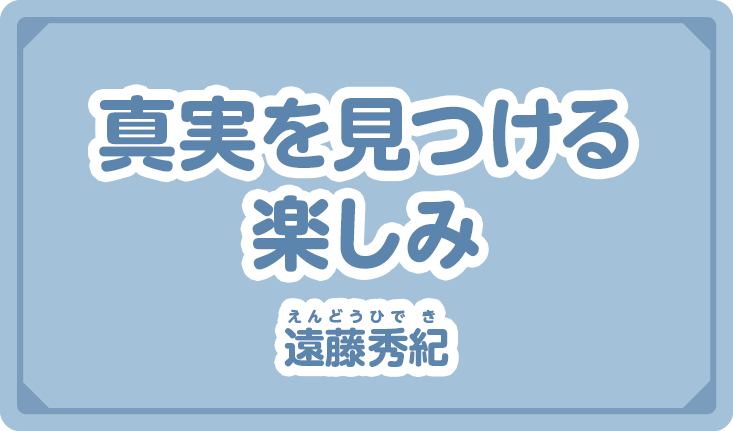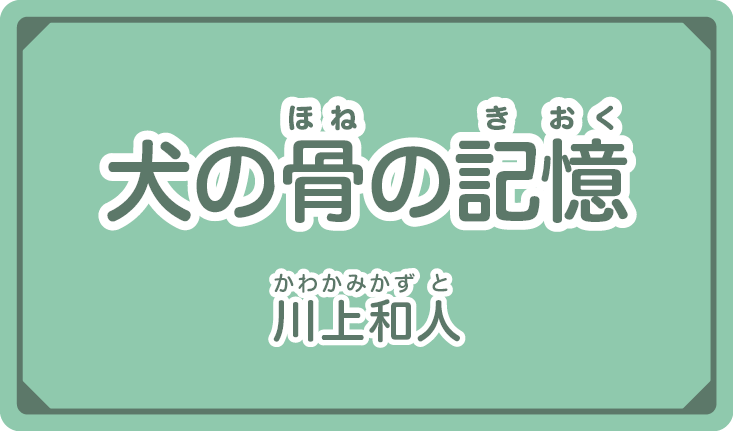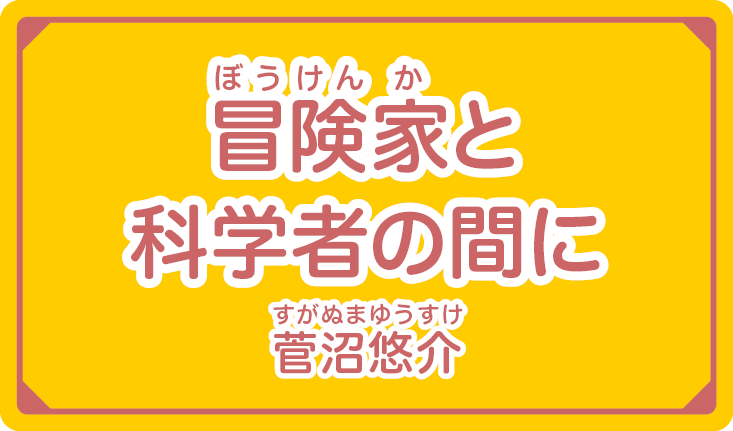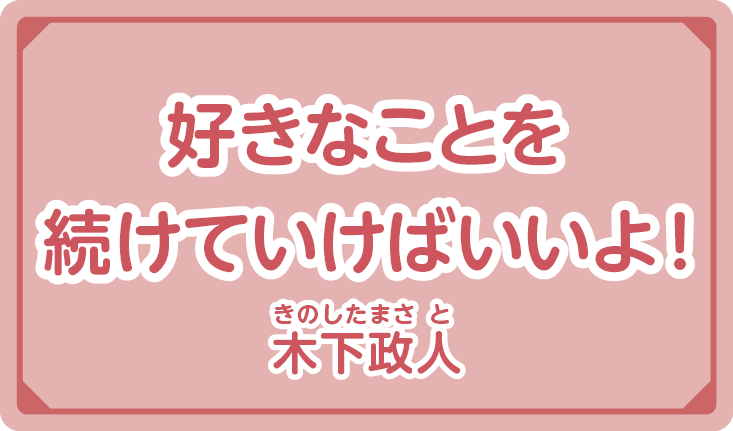この世界は奇跡でできている。別に神様や宗教の話ではない。進化の話だ。
キリンの首はなぜ長いのか。多くの人は、高い木の葉っぱを食べるためだと言う。まるで、高い木の葉っぱを食べるという目的のために、キリンが自ら進化したかのように。だが、ここで少し立ち止まって考えてみよう。キリンの祖先は、首の短い動物だった。その祖先動物が「あの木の葉っぱを食べてみたい。いつか絶対食べてやるんだ。」と精いっぱい首を伸ばす努力を重ねたから、キリンの首は長くなったのだろうか。祖先動物のお母さんが「私の子どもにはあの葉っぱを食べさせてやりたい。」と願いながら生んだから、キリンの首は長くなったのだろうか。もう分かっただろう。そんなことあるわけないのである。
親より首が長い子どもが偶然生まれたりするのは、別にキリンの祖先に限った話ではない。人間を含め、どんな動物にだって起きることがある。でもたいていの場合は下手に首が長くなっても地面の草を食べたり水を飲んだりするのに不便だし、バランスも悪くなって素速く動けなくなる。つまり餌や水を得るうえでも、敵から逃げるうえでもほかの仲間より不利になり、生き残って子孫を残す可能性は低くなる。キリンのほかに首の長い動物がほとんどいないのはそういうわけだ。
ただ、それなりにたくさんの木が生えていて、しかもその木の葉っぱを食べる動物があまりいないサバンナのような場所で、首の長い動物が生まれたら? そうなったらもう食べ放題である。別に努力の結果でも何でもない。ただこの世に長い首を持って生まれ落ち、立ち上がってみたら、目の前に餌となる葉っぱがいっぱいに広がっている。じゃあそれ食べよう。ほかのみんなは地面の草を奪い合ってるみたいだけど。ねえ、どうしてみんなは木の葉っぱを食べないの? え、届かない? へえ、たいへんだね。──といったところだ。
もちろん、一夜にして高さ六メートルにも達するキリンが生まれてきたわけではない。初期のキリンは比較的低い枝に届くくらいの高さしかなかっただろう。だが、それでも餌には困らないし、生き延びて子孫を残す可能性は高くなる。そして背の高い個体からは背の高い子どもが生まれやすいため、背の高い個体が増えていく。数が増えれば、そのうち低い枝の葉っぱは食べ尽くされてしまう。そうなると、今度はキリンどうしでの競争が始まる。競争といっても、努力したものが勝つ、という競争ではない。同じ親から生まれた人の子でも身長に違いが出てくるように、キリンの兄弟にもほかより背の高いものや低いものが生まれてくる。他の仲間が届かない高さに届くものは、より高い枝の葉を食べられるため生き残りやすく、子孫も残しやすい。そうやって世代を重ねるごとに、より首の長いものが選抜されていく。キリンはこうして進化したのだ。
改めて念を押しておくが、環境に適した子どもが突然生まれることは狙って起こせるようなものではない。ただでさえめったに起きないようなことが、よりによってそれがマッチするような場所で起きるという奇跡のような出来事の繰り返し。それが生き物の進化というものなのである。あなたの手がものをつかめるというたったそれだけのことも、進化という視点で考えてみれば驚くべきことなのだ(シーラカンスのひれからヒトの手が進化するのに必要な変化の過程を想像してみてほしい)。それどころか、理科の授業に出てくる動物や昆虫や植物のあらゆる特徴が、全て進化によって生まれたものなのだ。虫を呼ぶ植物の花も、空を飛ぶ鳥の翼も、獲物を切り裂くライオンの牙も、敵を投げ飛ばすカブトムシの角も。そろそろ最初の言葉の意味が分かってもらえただろうか。この世界は奇跡でできているのである。
さて、私はアズキの研究をしながら生きている。それは生き物の進化の中でもアズキの進化に心を奪われたからだ。アズキの仲間には、厳しい環境の中で生き延びているものがたくさんある。水が少ない砂漠。海水をかぶる砂浜。土がほとんどない岩山。水浸しの湿地。どれも、多くの植物にとっては生きていくのが困難な過酷な環境だが、それぞれの環境に適した特殊能力を持つアズキが進化して、繁栄しているのである。他の人と同じことをしたくないという私の心に、このアズキの特徴がぶっ刺さってしまったのだ。
しかも、アズキの特徴は役に立つ。他の植物が生きていけない環境で生きられるということは、その特徴を生かした作物を作れば、今農業ができない土地でも育ってくれるかもしれないのである。暑さによって作物がやられてしまうという最近増えてきた問題も、暑さに強いアズキが解決してくれるかもしれない。アズキに起きた進化という奇跡が、巡り巡って人類にとっての奇跡を起こす。そんな日を夢に見つつ、日々を研究に費やしている。
内藤健
植物遺伝学者。野生に生きるアズキの仲間たちを初めて目にしたときの感動が、研究の原動力になっている。