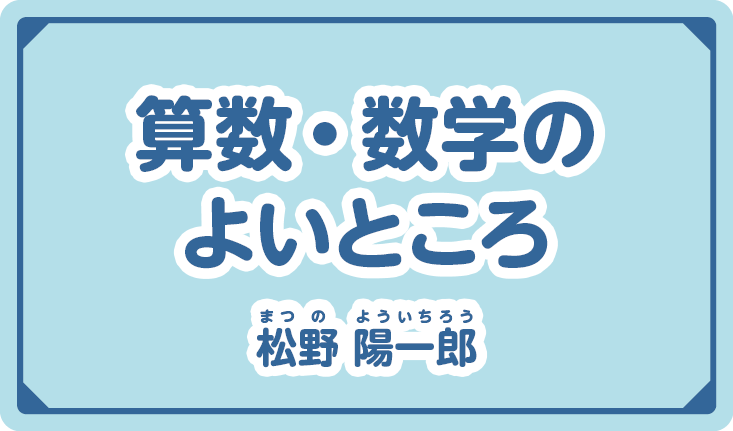あれは小学三年生の頃だったと思う。学校行事で遠足に出かけた。行く先は墓地公園である。
墓地公園は小高い丘の斜面に広がる市営の墓地だ。今から考えると墓地が目的地というのも珍しい気もするが、当時は特に疑問はなかった。この墓地の下からは弥生時代のお墓が見つかっている。つまり、二千年以上にわたり墓地であり続けている由緒正しい墓地なのである。
私たちは墓地でお昼ご飯を食べ、墓地で自由時間を遊んでいた。そのとき友達が、全身の骨が残るきれいな犬の白骨死体を見つけた。最近は野犬を見かける機会も減ったが、当時は住宅地でも野犬がうろついていた。ときには小学校の廊下をてくてく歩いていた時代だ。墓地公園の片隅に犬の死体があっても不思議ではない。
これはすごいものを見つけてしまった。
そう思った私たちはめいめいに骨を手に取りリュックにしまった。そのときその骨は宝物にしか見えなかった。手に入れたのは七、八人ぐらいだったと思う。私は何だか誇らしげな気持ちになった。
先生にばれるときっと怒られる。皆がそう考え、骨を拾ったことは誰も口にしなかった。しなかったつもりだが、すぐにばれた。
「犬の骨を持っている人、すぐに出しなさい。」
怖い顔の担任にそう言われ、みんなしぶしぶ骨を元の場所に返した。しかし、私は出さなかった。別に抵抗したかったわけではない。何となくタイミングを逃したのだ。
みんなが素直に返すとそれ以上の追及はなかった。しかし、家に帰り着くと急に恐怖と嫌悪に襲われた。先ほどまで宝物だった骨が、死体の一部なのだという実感がわいてきたのだ。私は骨を庭の端に埋め、そこは私にとって近づいてはいけない場所になった。
大人になった私は鳥類学者となり、研究のために骨の標本を集めるようになった。ときには化石を発掘し、ときにはネコのふんの中身を調べる。そこから見つかる鳥の骨と見比べるためだ。
鳥の死体を拾い、解体し、洗い、きれいな標本にする。かつての嫌悪感はもうない。野生の世界では死もまた自然の一部だと理解できたからだ。毎年たくさん動物が生まれ、同じ数だけ死んでいく。死体はカラスやネズミやアリに食べられて分解される。骨は土の中で溶けていく。死体は生態系の中に取り込まれ、生きている動物や植物の栄養になる。
小学生の頃に抱いた嫌悪感は今も忘れていない。それはそれで正常な感覚だったと思う。しかし、当時の恐怖は今では敬意に変わっている。たくさんの骨を見比べることで、骨というものが何千万年もの時間をかけて進化した無駄のない美しい形を持っていることを強く感じるようになったのだ。
あの骨を拾ったときに誇らしく思ったのは、もしかしたらその美しさに魅力を感じていたからかもしれない。これがその後の私の研究に連なる最も古い記憶である。
川上和人
鳥類学者。著書に「鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。」ほか、監修書に「講談社の動く図鑑MOVE 鳥」などがある。