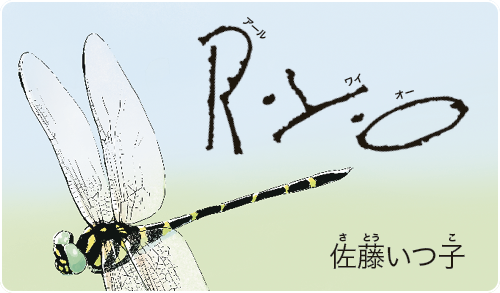五時間目は図工の時間だった。図工室にただよう、水彩絵の具の匂い。
みんなは、それぞれのタブレットと画用紙を机に置き、交互に見ながら絵を描いている。何か写真に撮ったものを、描いているようだった。ちらりと見わたしたけど、うまいと思える絵は一枚もない。
僕は、机にうつぶせになって目を閉じた。やはり保健室で、寝ていたほうがよかったと思う。
ウクライナから日本に避難してきたのは、春だった。戦争はどんどんひどくなっていた。ミサイルが飛んできたり、爆弾が落とされたりした。病院にも、教会にも、発電所にも。
そして、僕の大切な場所も破壊された。黄色に実るはずだった、父さんの小麦畑は黒焦げになり、通っていた学校も、将来入りたかった学校も灰色のがれきになってしまった。
父さんは兵士になって、戦いに行った。
「なあに、こんな戦争、すぐに終わらせてやるさ。」
そう言って笑顔で戦場に行き、最初はビデオ通話もできたのに、そのうち連絡が来なくなった。
「心配ない。父さんは今、電波のない遠い場所で戦っているだけだから。」
母さんはそう言った。
「でも、しばらく帰ってこられないから、わたしたち、日本の大おばさんの所に避難しない?」
大おばさんは、母さんのおばさんだ。日本人と結婚して日本に住んでいる。小さなときに一度だけ会ったきりで、顔も覚えていないけど。
「それがいちばんいいと思うの。ね、イーゴリもルダも、安全に暮らせるわ。」
「やだー! ルダはここがいい。どこにも行かなーい!」
そう言って泣く四歳の妹を、僕はなだめた。「陽気なイーゴリ」と友達に呼ばれていた僕は、小さい子をあやすのが得意だった。
「ルダ、兄ちゃんも母さんに賛成だな。日本では爆弾の代わりに、すしが落ちてくるんだぞ。」
「しかもその、すしってやつは、舌がとろけるほどおいしいんだ。」
「食ったらアニメのヒロインみたいに、かわいく変身できるんだぜ!」
おどけたポーズでそう言ってやると、ルダは泣きやみ、ちょっと笑った。
そうして僕ら三人は日本へ来て、とりあえず、大おばさんの家の二階に住むことになった。
あの頃の僕は、まだ「陽気なイーゴリ」だった。なぜって希望があったからね。
そのうち戦争は終わり、僕らはウクライナに帰り、また父さんともいっしょに暮らせるようになる。そしたら小麦畑は復活するし、通っていた学校も目標にしていた学校も、そのうち建て直される。そう信じていたからね。
けれど戦争は終わる気配もなく、さらに僕は、信じたくもない事実を知ってしまったんだ。
「あなたはデニスが亡くなったことを、いつまで秘密にするつもり?」
夜中にトイレに行こうとして、大おばさんの声を聞いてしまった。デニスとは、父さんの名前だ。
「わからない。」と、母さんは泣いていた。
「わたし自身、まだ本当のことだとは思えなくて......。」
僕は足音を忍ばせて部屋にもどると、布団を頭からかぶった。
大好きな父さんは、戦死していた。もう二度と会えない。小麦は二度と実らない。
日本に来ることをいやがっていたルダは、意外にもここになじみつつある。
おいしいお菓子攻撃、人気アニメ見放題攻撃、好きなキャラクターの、カプセルトイ攻撃。
大おばさんによる平和な攻撃の数々に、ルダはだんだん明るくなった。保育園にも行き始め、最初は泣いていたけれど、日本の歌や折り紙を教わって、機嫌のいい日も増えてきた。
けれど僕の心は闇だった。歩いて二キロほど先にある、小さな小学校。ここは日本でも田舎のほうらしく、各学年一クラスしかない。みんなが幼なじみという六年のクラスに、日本語もわからない僕が入っていくのだ。ひたすら気が重い。父さんの死を知ってしまった今となっては、なおさらだ。
クラスメートたちは、気味が悪いほど親切だった。
最初の日、「ドーブリ・デーニ(こんにちは)」とクラス全員がウクライナ語で声をそろえ、一斉にパチパチと拍手をした。担任の女性の先生は、僕を空いた席に案内すると、タブレットの翻訳アプリに機関銃のように日本語を打ち込んだ。
《はじめまして。わたしたちはイーゴリさんを、とても歓迎しています。》
変換されたウクライナ語を見ていると、うれしいというよりお尻がもぞもぞして居心地が悪かった。隣の席の女子が待ちきれないようにタブレットをひったくり、また新たな言葉を打ち込んできた。
《みんなで、翻訳アプリの使い方を学びました。何でもここに書いてください。わたしたちは、もう友達。》
友達? とたんに心がすうっと冷えた。教室中の人が僕を見ている。興味しんしん、という目もあれば、かわいそう、という目もある。僕とは全然違う外見で、全く違う言葉を話す人たち。
今戦っているのは、親戚のように思っていた隣の国だ。僕らと同じような外見を持ち、似た言葉を話す人たち。それなのに気がつけば、敵どうしになってしまっていた。
隣の国とでさえそうなるのに、こんな異国の人たちと、友達になんてなれるものか。
父さんがいなくなって、「陽気なイーゴリ」もどこかに行ってしまった。代わりに闇が心に広がっている。僕はタブレットを払いのけ、ただ無言でうつむいた。
けれど、次の日からもクラスメートたちは、何度も翻訳アプリで話しかけてくる。
《好きな食べ物は何?》《好きなスポーツは?》《誕生日はいつ?》
無視しても、またしつこく聞いてくる。ある日、《今、何がしたい?》と聞いてきたやつがいた。闇の心のままで、僕はタブレットを取り上げる。本当に自分がそうしたいのか、よくわからない。ただ父さんのことを思うと、こう言わなければいけない気がした。
《兵士になって戦いたい。早く大人になりたい。》
その場にいた全員の顔がこわばった。困りきったように、タブレットから目をそらす。その日から先生以外、僕に話しかけてくる者はいなくなった。
そうして春は過ぎ、夏も過ぎ、今はもう秋だ。戦争はいつまで続くのだろう?
僕は一学期の途中から、教室ではなく、図書室や保健室で過ごすことが多くなっていた。独りはすっきりさわやかで、同時に心がすうすうした。すうすうした心は、なぜか石みたいに重かった。
《イーゴリさん、一日に一時間でいいです。教室で授業を受けましょう。》
担任の先生にそう勧められて、一日一時間だけ授業を受けた。日本語がわからなくても何とかなる、体育とか音楽、理科の実験なんかを選んだ。
けれど今日はそのどれもがなかったので、しかたなく保健室から図工室へ行き、やる気もないのでただ机にうつぶしている。不意に、頭のてっぺんに風を感じた。
「きゃっ。」
女子たちの声に顔を上げると、何枚かの画用紙が宙に舞い、僕の足もとに飛んできたところだった。風が強く図工室に吹き込んできて、窓付近で描いていた子の画用紙を吹き飛ばしたんだ。
しかたなく、のろのろと手を伸ばしてその画用紙を拾い上げ、僕ははっと息をのんだ。描かれていたのは父さんの畑だった。なつかしい、ウクライナの風景だった。
空の下に広がる小麦畑。上半分は空の青。下半分は、たわわに実った小麦の黄色。
「ごめん。それ、あたしの。」
顔を上げると、女の子がおずおずと僕に向かって手を伸ばしている。最初の日、僕にタブレットで話しかけてきた子だ。《もう友達》と書いてきた子だ。
僕はその絵を返すことができなかった。なぜこの子は小麦畑を描いたのだろう? かわいそうなウクライナ人への同情か?
図工担当のおじいさん先生が、タブレットを片手に近寄ってきた。
《それは、たんぼの絵です。米が実っています。》
これは小麦の絵ではなかったのか。言われてみれば、実った穂先が小麦とは違う。小麦の穂先は空に向かって伸びている。けれどこの絵の穂先は、地面に向かって垂れている。
《米は日本人が、昔から食べている穀物です。イーゴリさんも、給食で食べています。》
確かに日本に来てから、米をよく食べている。特におにぎりはおいしいと思った。マヨネーズであえたツナが入ったおにぎりは、母さんもルダもお気に入りだ。
《来月、学校で図工展があります。》
今度はさっきの女の子が、翻訳アプリに言葉を打ち込んだ。
《六年生のテーマは「わたしの大切な場所」です。六年間の思い出が詰まった、大切な場所。それぞれが写真に撮り、絵に描いています。》
何人かのクラスメートが、自分の絵を僕のほうに向けて見せてくる。
いろんな場所が描かれていた。
校庭のバスケットゴール。丸い時計がはめ込まれた校舎。中庭の小さな池。
町の運動公園。れんが色の図書館。高台から見える海。
《わたしが描いたのは、祖父のたんぼです。通学路のそばにあります。悲しいとき、つらいとき、成長する稲を見ると心が落ち着きました。》
僕はその子の絵や、ほかのクラスメートたちの絵を、ただ見つめた。
ウクライナ人の僕に大切な場所があったように、日本人のこの子たちにも、大切な場所がある。その光景を忘れないよう、こうして絵に描いているんだ。ずっと覚えていたいから。これからも自分の支えにしたいから。外見も言葉も違うけど、僕らは同じ気持ちを持っていた。
《僕も描きたい。》
翻訳アプリにそう打ち込むと、図工のおじいさん先生はぱっと顔を輝かせ、新しい画用紙と下描き用の鉛筆を出してきてくれた。
真っ白な画用紙の上に、僕は鉛筆を走らせる。地平線まで続く、広い広い小麦の畑。その穂先は風になびきながらもすっくりと立ち、まっすぐに天を目指すかのようだ。空には綿をちぎったような雲が、穏やかに浮かんでいる。畑を見守る男の人の後ろ姿。僕の、父さん──。
「ほう。」
図工の先生が、うなずいている。
「イーゴリ、すげえ!」「すげえ、じょうず。」
何人かが、声を張り上げた。「すげえ」がほめ言葉なのは、もう知っている。爆弾で破壊されてしまったけれど、十五歳になったら美術学校に入学するつもりだった。将来は絵描きになりたかった。
なりたかった? いや、今もなりたい。大切な僕の国の風景をキャンバスに描いて、世界中の人に知ってもらえたら。そしていつか、「陽気なイーゴリ」にもどれたら。
クラスメートたちに囲まれながら、僕は鉛筆を動かし続ける。
安田夏菜
児童文学作家。著書に 「むこう岸」 「セカイを科学せよ!」「アナタノキモチ」などがある。