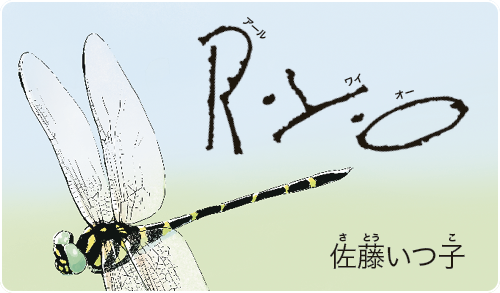少し強い風が吹いて、草がさわさわっ、と波打つ。穂を出したばかりのススキやネコジャラシが、「おいでおいで」と私を呼んでいる。
野原の小道を外れて、胸ぐらいまである草の中に、私は入っていく。
青い、草のにおい。
すると、足もとから、キチキチキチッとバッタが飛び出す。大きなショウリョウバッタだ。小さいのは、一歩足をふみ出すごとに、何びきも飛び出す。
手を伸ばし、葉の上のバッタをさっとつかまえる。とんがった顔、赤い口もと。
「父さんたちは子どものころ、こいつをトンガラシって呼んでたんだ。ほら、口もとが赤いだろう。」
父さんの声が、耳の奥に響く。
キチチチチッ。
ひときわ大きな音を立てて、トノサマバッタが飛び出した。追いかける。だめだ、トノサマバッタは、簡単につかまらない。父さんと二人がかりでつかまえようとしても、難しかったんだ。
どうして今、私は一人でバッタを追いかけているんだろう。どうして父さんは、いなくなってしまったんだろう。あんなに元気だったのに。
去年の十一月、父さんは倒れて病院に運ばれ、そのまま帰ってこなかった。
私は四年生になって、夏休みが終わっても、どうしたらいいか、分からないまま。
母さんは、パートから正社員になって、洋服を作る会社の仕事を頑張っている。私も、今は毎日学校に行っているし、カナエやリナとも、笑ってしゃべっている。
でも、前とはちがう。景色が、どれも何だか白っぽく見えてしまう。
大好きだった山や野原や、川釣りにも行かなくなった私に、母さんは「市のたより」で見つけた、この「矢神川自然観察会」をすすめてくれた。
「私は虫とかヘビとかいやだから行かないけど、風子は生き物にくわしいから楽しいかもよ。電話で申し込んであげるから。」
行ってほしそうな顔だったので、私は「じゃあ行く。」と答えていた。
さっきまでは、みんなといっしょに観察しながら歩いていたのに、一人で草の中にいる私。
あれ、涙がだあだあ流れてる。たまに、こんなふうになる。止まらないよ。
ざざざざざっと、草がゆれた。目の前に、男の子が飛び出してきた。
「おい、おまえ、どこまで入っていくんだよ。みんなとはぐれちまうぞ。」
髪の毛がつんつん立って、日に焼けて真っ黒な顔。やけにぎらぎら光る目。......イノシシ太郎?
「何だよ、迷子になって、泣いてたのか。しょうがねえなあ、ほら、これ、やるよ。」
男の子が差し出した右手の指の間には、大きなトノサマバッタがはさまっていた。
「え、つかまえたの。すごい......。」
私は、親指と人差し指で、バッタの頭の後ろをつかんだ。じっと、顔を見る。四角い顔だ。
二本の指の間に、バッタの「飛びたい」という気持ちがじんじんと伝わってきて、思わず指をゆるめたとたん、バッタは身をよじって、キチチッと飛び立ってしまった。
「何だよ、逃がすなよ!」
男の子は、があがあした声で怒鳴った。
「ごめん......。」
「ま、いっか。あんまり虫つかまえると、みんなにしかられるな。何たって、観察会、だもんな。」
私は、くすっと笑った。
「んじゃ、行くぞ。もうすぐお昼だぞ。」
「うんっ。」
男の子と私は、かけっこをするように草の中を走って、小道に向かった。
会の代表の沢井さんが、にこにこして小道に立っていた。
「風子ちゃんの姿が見えなくなったから、ちょっと見にきたのよ。でも、テツといっしょだったのね。」
母さんと同い年くらいの沢井さんは、モスグリーンのトレーナーにベージュ色のパンツで、自然にとけこんでいる感じでかっこよかった。
「母ちゃん、こいつ、迷って泣いてたんだぜ。」
「ちょっと、やめてよ。えっ、母ちゃん?」
「うちのテツは、風子ちゃんと同じ、四年生なのよ。」
こんな優しい感じの人が、このイノシシ太郎......テツの、お母さんだなんて。
「野生児だからね、何でもくわしいわよ。学校では、落ち着きがなくて、しかられてばかりだけど。」
「うるせえな。行くぞ。」
私たちは急ぎ足で歩いて、いちばん後ろのおじさんに追いついた。
「八木さん、何か見つけた?」
八木さんと呼ばれたおじさんは、うれしそうに言った。
「今日は、コガネグモのりっぱな巣を見つけたよ。いい写真が撮れたよ。」
大きなデジカメに写っている、黄色と黒のしましまのクモを見せてくれた。
今日の参加者は三十人ぐらいで、小学生の男子はいるけれど、ほとんど大人。おじいさん、おばあさんもいる。みんな、思い思いに足を止めて、虫や植物を観察したり、写真に撮ったりしている。お弁当のときも、自分が見つけためずらしい草や虫、カエルなどを次々に報告し合っていて、聞いているうちに、時間があっというまに過ぎてしまった。
午後は、矢神川のそばまで歩いていって、鳥の観察をするらしい。
この川の、もう少し下流で、父さんとよく釣りをした。私は、クチボソやハヤなどの小物釣り。父さんは、大きなコイをねらっていたっけ。
「おお、いたいた。」
と、があがあした声が聞こえた。
釣りざおを二本かついだテツだった。
「おい風子、釣り教えてやるよ。」
いきなり、何? テツはもう、川に向かって歩きだしている。鳥の観察なんだけど......。
「みんなの見える所にいれば、大丈夫だよ。ほら、これ使えよ。」
「う、ありがとう。でもさ、教えてくれなくても、釣りできるよ。ハヤとか、よく釣ってたもん。」
「そうか、そんなら競争だ。」
流れの中に、しましまの浮きが二つ。どちらも、ちっとも引かない。
「うーん、練りエサじゃだめなのかな。」
「そうかも。赤虫がよかったかな。」
「でも、おまえ、投げ込むの上手だな。おまえの父ちゃん、釣り好きだったのか。」
「え、うん。......テツ、知ってたの? 父さん、死んだこと。」
「ああ、母ちゃんに聞いたよ。おまえの母ちゃんが電話で言ってたって。」
「なあんだ、だから、かまってくれてるの? お母さんに、頼まれて?」
「あほう。」
「あほうって何よ。」
「おれ、母ちゃんの言うこと聞くほど、ひまじゃねえ。おまえ、トノサマバッタつかめたしな、見どころあると思ったんだよ。おっ、引いてるぞ!」
私の浮きが、つんつん動いている。
「もう少し待て、あせるなよ。」
「分かってるよ。」
と、言いつつ、待てなくてさおを上げてしまった。一瞬、ぐぐっと魚の重さを感じたけれど、ぱすんと外れて、逃げてしまった。
「おい! だから言っただろ。」
そういえば、父さんにもよくしかられた。
「風子は、いつも上げるのが早すぎるんだよ。もっと待たなくちゃ。」って。
しまった、泣きそう。私は、小さい子みたいに、両手を目に当てて、「うそ泣き」のまねをした。
「泣きまねすんなよ。お、ダイサギだ。見ろよ、向こう岸。」
目を上げると、白い大きなサギが、水面を見つめている。
サギは、さっと川に頭をつっこんだ。と思うと、二十センチもありそうな魚をつかまえて、かぷっと丸飲みにした。ところが、横向きに魚を飲んだらしく、首が石おのみたいにふくらんでしまった。しかも、そこがぴくぴく動いていて、サギはちょっと困ったように頭を振っている。
「ひゃはははははは。」
「あはははははは。」
私たちは、同時に激しく笑いだし、止まらなくなった。こんなに笑ったの、久しぶり。
笑いつかれて、やっと静まった。どうやら魚は、サギのおなかに入ったみたいだ。
「んじゃ、あっちに戻るか。風子にはもう少し、釣りの修行が必要だな。」
「テツこそ、釣れなかったじゃん。」
「ふん、次は本気で勝負するか。」
「いいよ、私、マイさお持ってくるからねっ。そしたら負けないんだから。」
私たちは、ぎゃあぎゃあしゃべりながら、みんなの所に行った。
「こら、静かに。向こう岸に、カワセミがいるよ。」
お兄さんが、望遠鏡を三脚に立てている。
「お、見せて見せて。」
テツが、のぞきにかけ寄っていった。私もついていった。
望遠鏡をのぞいてみると、茂みの中に、カワセミがいた。
こっちを見ている! 胸が、きゅっとなった。羽に日が当たって、エメラルド色に光っている。
「きれい......。」
二、三秒だったのか、もっと長い間だったのか。カワセミと私の、時間が流れた。
望遠鏡から目を上げた。川の流れも、周りの野原も、何だかきらきらしている。まるで、「おかえり」って、言ってくれているみたいに。
大きく、息を吸い込んだ。体の中に、野原の空気がしゅうっと広がっていく。
(父さん、私はまた、この河原に来ちゃったよ。見てて、今度は、フナ釣ってみせるよ。)
風が、ひゅっと髪をゆらした。父さんの、いたずらみたいだった。
葦原かも
児童文学作家。著書に「まよなかのぎゅうぎゅうネコ」、「うみのとしょかん」シリーズ、「どんなイチゴも、みんなかわいい」などがある。