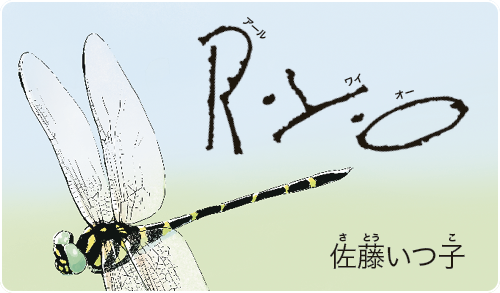「だから、何の絵だっつってんだよ。」
図工室のテーブルで、僕の向かいに座るコウキが隣のハル君をこづいた。コウキがさっきから何度も聞いているのに、ハル君が何も答えないせいだ。
ハル君は眼鏡に手をやっただけで、相変わらず眉ひとつ動かさない。僕も筆を持つ手を止めて、彼の絵をのぞき込む。
ハル君が何を描いているのかは、前回の図工の時間からずっと気になっていた。ひたすら黒い絵の具で画用紙を塗りつぶしていたからだ。今日は紙の真ん中あたりに、赤に黒を少し混ぜたような色の横線が短く描き加えられている。その正体はやはり見当もつかない。
「宇宙とか?」「んなわけないじゃん。」
同じテーブルの女子二人が口々に言う。そう、そんなわけはない。先生に言われた絵のテーマは、「いつかまた見たいもの・いつかまた行きたい場所」だ。
「これは――」ハル君が無表情のまま、ようやく口を開いた。「オーロラ。」
「オーロラ? 見たことあんの?」「どこで? カナダ? ノルウェー?」
目を丸くして矢継ぎ早に質問を浴びせる女子たちの横で、僕はもう一度ハル君の画用紙に目を凝らした。この赤黒い横線が、オーロラだというのだろうか。とてもそうは見えない。オーロラというのは緑色に輝いていて、カーテンのように波打っているはずだ。
どこの国で見たのかとしつこく聞かれ、ハル君は小さくかぶりを振った。
「これは――八王子。」
「は?」コウキが露骨に顔をしかめる。「おまえ何言ってんの?」
確かに。都心からずいぶん離れているとはいえ、ここ八王子市はれっきとした東京都の一部だ。北海道でオーロラが観測されたという話は以前聞いたことがあるけれど、東京でオーロラなんて見えるはずがない。女子二人の口調もとたんに冷たくなる。
「いつ見たの? それが本当なら大ニュースになったはずだけど。」「どうせ夕焼けか何かと見間違えただけでしょ。」
コウキがさっきより強くハル君の肩を押した。
「やっとしゃべったと思ったら、つまんねえうそかよ。マジ訳分かんねえな、おまえ。」
コウキに何度もこづかれて、ハル君の眼鏡がずり落ちる。それでも彼は唇をきつく結んだまま、目の前の奇妙な絵を見つめている。
ハル君には、優しくしてあげなきゃだめよ――。
母さんの言葉が頭をよぎった。コウキを止めたほうがいいだろうか。でも、ハル君が訳の分からないやつだということには、僕も同感だ。おまけにうそまでついたのだから、同情する気にはなれない。
どうしようか迷っているうちに、先生が近づいてきてコウキをひとにらみした。コウキはそしらぬ顔で自分の画用紙に向き直る。ハル君も何事もなかったかのように眼鏡をかけ直し、また筆を動かし始めた。
ハル君が江東区の小学校から転校してきたのは、今年の四月だ。それから半年がたつというのに、クラスには一人の友達もいない。休み時間はいつも自分の席で本を読んでいて、授業などで好きなようにグループを作れと言われたら、最後までぽつんと教室の隅に立っている。
でもそれは、僕たちのせいじゃない。一学期の間はみんながハル君を気づかって、あれやこれやと話しかけた。もちろん僕もだ。なのに彼はこちらと目も合わさず、何を聞いても黙り込んだままか、せいぜい「うん。」か「まあ。」としか答えないのだ。そんな転校生の相手をいつまでも続けるほど、僕たちだって暇じゃない。
ハル君は、僕の家のすぐ近くの古い一戸建てに、父方のおじいさん、おばあさんと三人で住んでいる。家庭の事情――たぶん何か複雑な大人の事情――で両親と離れて暮らすことになり、一人八王子に引っ越してきたらしい。これは、彼のおばあさんと以前から親しくしている母さんから聞いたことだ。
どんな事情かまでは教えてくれなかったけれど、母さんはハル君について「かわいそうな子なのよ。」と繰り返し、僕には怖い顔で「クラスで言いふらしちゃだめよ。」と念を押していた。
夜八時過ぎ、中学生の兄ちゃんといっしょにラッキーの散歩に出た。ラッキーはうちで飼っている柴犬だ。
リードを握る兄ちゃんの後についていつものコースを行き、小高い丘へと続く坂道に入る。丘の上は公園になっていて、八王子の街がよく見わたせる。
階段を上って藤棚のある広場に着くと、すぐ左手のフェンスの際に大小二つの人影がある。ハル君と彼のおじいさんだった。おじいさんがこちらに首を回し、「やあ、こんばんは。」と声をかけてくる。おじいさんとは僕も顔見知りで、道ですれ違えば挨拶ぐらいはする。
「ワンちゃんの散歩かい?」おじいさんが目を細める。
「はい。」と答えながら僕はそちらに近づき、二人の間に立っている背の高い三脚に目を留めた。てっぺんにりっぱなカメラが取り付けてある。レンズはフェンスの上から、北の方角を狙っていた。住宅街の明かりが広がっているだけの、どうってことない景色だ。
「それ、夜景撮ってるんですか?」僕はおじいさんに聞いてみた。
「夜景は夜景だけどね。」おじいさんは言った。「カメラの露光時間をうんと長くしたら、うっすらとでもオーロラが写らないかと思ってね。」
「オーロラ?」今日の図工の時間のことを思い出し、ハル君の方を見やる。ハル君はこちらに目もくれず、じっと正面の低い空を見つめている。
「まあ、可能性はほとんどないと思うけど。」おじいさんが苦笑いを浮かべた。「二日ほど前に、太陽の表面で大きな爆発があってね。その爆風が地球まで届いて、今夜は大きな磁気嵐になっているらしいんだよ。」
方位磁針が北を指すのは、地球が大きな磁石になっているからだ。そんな話は理科の授業で聞いた記憶がある。おじいさんによれば、地球の磁気が乱れるのが磁気嵐という現象で、活発なオーロラを引き起こすのだという。磁気嵐やオーロラの発生に関して予報を出している、研究機関などのサイトがあるそうだ。おじいさんは続けた。
「今回の磁気嵐はかなり規模が大きいんだ。北海道でもオーロラが見られるんじゃないかってことで、今あっちには研究者や写真家が大勢集まってるようだね。」
「でも、だからって、東京でオーロラなんて......。」
「ありえないことじゃない。」ハル君がいきなり言った。「現におじいちゃんは見た。ここで。」
「マジで? いつ?」
そのとき、藤棚のほうで兄ちゃんが僕を呼んだ。ラッキーもせかすようにほえている。がぜんハル君の話に興味が出てきた僕は、先に行ってくれるよう頼んだ。おじいさんも横から、「後でお宅まで送り届けますから。」と言ってくれた。
おじいさんは上着のポケットからスマホを取り出し、一枚の写真を見せてくれた。オーロラが写っているのかと思ったら、色あせた古い絵を撮ったものだ。黒く塗った山影のすぐ上に、赤く短い横線が描かれている。
「昭和三十三年――一九五八年だから、もう六十年以上前のことだけどね。私は君らと同じ五年生だった。忘れもしない、二月十一日の夜八時過ぎ。おふくろにお使いを頼まれた帰り道、何気なく北の空を見ると、山の際の空がぼんやり赤いんだ。山火事かなと思って、この丘に上って眺めていたんだが、どうも様子が違う。その翌朝、新聞を見て驚いたよ。」
その夜、北海道はおろか、秋田、新潟、長野、群馬など、日本の北半分の広い範囲でオーロラが観測され、大ニュースになったのだという。それを知ったおじいさんが記憶を頼りにすぐ描いたのが、この写真の絵だそうだ。
「オーロラを見たと小学校で言っても、誰も信じてくれなかった。」おじいさんは眉尻を下げた。「人にその話をすることもなくなっていたんだけれども、十年ほど前、市の科学館でオーロラ研究者の講演会があると聞いて、参加してみたんだよ。講演会のあと、思い切ってその先生にこの絵を見せたら、なぜか大喜びしてね。」
その研究者は一九五八年二月十一日のオーロラについても研究していて、詳しい計算の結果、オーロラのいちばん高い部分がぎりぎり八王子からも見えたことを突き止めていたという。八王子での目撃証言は当時ほかにも二件ほどあったそうだ。
「研究資料にしたいとその先生が言うんで、絵のコピーを送ってやったりもして。うれしかったねえ。あれが本当にオーロラだったってことが、五十年越しにはっきりして。」
「すげえ......。」
僕は心の底からそう言って、もう一度おじいさんのスマホの画面を見つめた。そういえば、ハル君の絵とよく似ている。つまりハル君は、おじいさんが昔見たオーロラをいつかまた自分も見たいと考えて、あんな絵を描いたわけか。うそをついていたわけではないのだ。
「今夜がだめでも、まだ可能性はある。」ハル君が眼鏡に手をやって、きっぱりと言った。
どういうことかとたずねると、学校での彼からは想像もできないような早口でいくつか教えてくれた。
太陽の活動はおよそ十一年の周期で強まったり弱まったりしていて、活動のピークにあたっている今年は大きな磁気嵐が起きやすいということ。オーロラは下側が緑色に、上側が赤色に光るので、カナダや北欧に比べて緯度の低い日本から見えるのは、上の端に近い赤い部分だけだということ。明治時代には一度、四国や中国地方でも赤いオーロラが見られたこと、などだ。
「ハルは将来、科学者になりたいそうでね。」おじいさんが優しい声で言う。「八王子に越してきたら私とオーロラ観測ができるから、よかったと。以前この子が住んでいたところは、ビルばっかりで空が開けてないからね。」
また北の空に目を向けたハル君の横顔を見つめながら、家に帰ったら母さんに伝えようと僕は思った。ハル君はかわいそうな子なんかじゃない、と。
「磁気嵐ってのがまた起きて、ここでオーロラを待つときはさ。」僕はハル君に言った。「僕も誘ってくんない?」
ハル君は前を向いたまま、小さく、でもはっきりとうなずいた。
参考文献
「日本に現れたオーロラの謎 時空を超えて読み解く「赤気」の記録」片岡龍峰・著 化学同人(二〇二〇)
伊与原新
作家。著書に「宙わたる教室」「八月の銀の雪」「青ノ果テ」などがある。