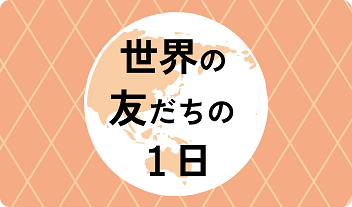目で読むSDGs図鑑⑥だれでも小学校や中学校に行けるってあたりまえ?
SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」では、だれもが公平に、よい教育を受けられるようにしていくことを目指しています。日本の子どもたちには、小学校・中学校で学習する機会が保障されています。しかし、それはあたりまえのことなのでしょうか。
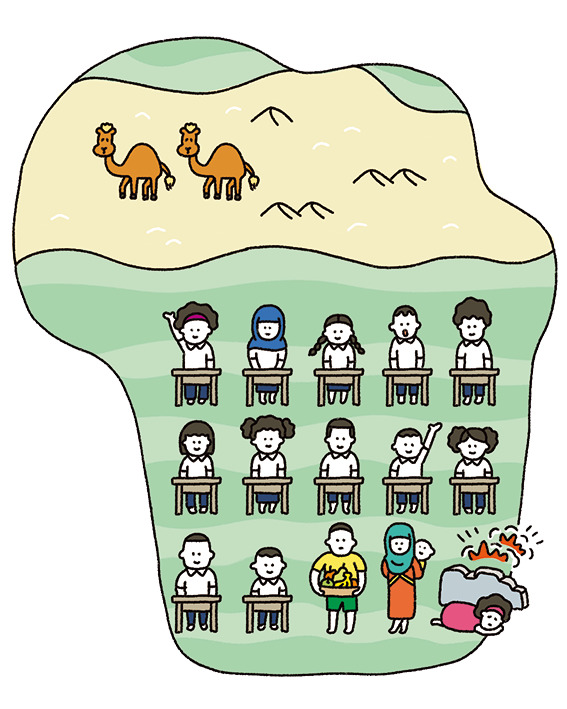
アフリカ大陸のサハラ砂漠以南の地域では、
5人に1人の子どもが小学校へ通うことができません。
出典:公益財団法人 日本ユニセフ協会ホームページ
日本の小学校・中学校
日本では、全ての子どもが小学校に六年間、中学校に三年間、それぞれ通うことができます。小学校や中学校は、もともと、だれもが教育を受けられるわけではなかった時代に、どの子どもにも学習する機会を保障しようという目的で始まったものでした。
小学校や中学校で学習する機会が全ての子どもに公平にあたえられている日本にいると、「だれでも小学校や中学校へ行きたいときに行けるのがあたりまえじゃないの?」と思うかもしれません。でも、世界のほかの国では、教育を受ける機会にめぐまれていない子どもたち、学校へ行きたくても行くことができない子どもたちが大勢いるのです。
世界の子どもたちはどれくらい学校に通っているの?
世界では、どのくらいの割合の子どもが小学校へ通っていると思いますか? 世界全体で見ると、約90%。残りの10%、つまり十人に一人は、小学校へ通うことができません。この十人に一人という数字は、ヨーロッパや北アメリカ、日本といった、ほとんどの子どもが小学校へ通う機会を持つ国も含めた平均です。ヨーロッパや北アメリカでは、小学校へ通えない子どもは2%、つまり百人に二人程度で、割合が小さくなります。それに対して、小学校へ通えない子どもが特に多い地域があります。それは、アフリカ大陸のサハラ砂漠以南の地域です。この地域に限定すると、20%、五人に一人が、小学校へ通うことができないのです。中学校では、学校へ通えない割合がさらに大きくなり、約30%、三人に一人が中学校へ通うことができなくなります。
なぜ、小学校や中学校へ通うことができない子どもたちが大勢いるのでしょうか。さまざまな理由がありますが、①紛争や戦争、②労働や家事、③男女の格差などが主なものとして考えられます。
理由① 紛争や戦争
紛争や戦争が起きて、急に兵士がやってくる、ばくだんが落ちてくるなどの危険にさらされるような地域では、安心して学校へ行くことができません。また、争いが起きている所から遠くににげるため、引越したり、別の国へ行ったりすることがあるので、同じ所へとどまることが難しく、毎日学校へ通うことができないのです。
理由② 労働や家事
家族を支えるために、子どもが働いている場合もあります。ふだん学校があるお昼の時間に、果物やアイスクリームを町へ売りに行かなくてはならないので、学校へ行くことができないのです。チョコレートの材料であるカカオ豆を作るために、農場などで働いている子供もいます。ここには貧困の問題がひそんでいます。大人の労働による収入だけでは、家族を支えることができず、子どもが働いてお金をかせがないと、家族の食料が手に入らなかったり、住む場所を確保することができなかったりするのです。
理由③ 男女の格差
日本では、識字率(注1)という、教育の水準の指標になる数値に男女で差はありませんが、世界には7億7500万人の非識字者がおり、その約三分の二は女性だといわれています(注2)。世界のほかの国では、女性の役割は「結婚して子どもを産み、育てること、家事や介護をすること」という意識を持つ人たちがいて、女性は、学校へ行かせてもらえない場合があります。性別に関わらず、全ての人が教育を受けることができる世界にしていく必要があるのです。
*(注1) 国や地域で、日常生活で用いられる簡単で短い文章を理解して読み書きできる人の割合のこと。
(注2)出典:公益財団法人 日本ユネスコアジア文化センター『用語集』

そのほかの理由
教科書は、日本では無料で手に入れることができるものですが、ほかの国ではお金がかかることがあり、貧困のために、教科書を買うことができない子どもたちがいます。また、先生の数が足りず、子どもたちが教育を受けられない地域もあります。
学びの環境を整えることがだいじ
学校に通う機会があったとしても、教科書が買えなかったり、先生が足りなかったりして、教育を受けることができないことがあります。また、病気や障害などさまざまな理由で学校に通うのが難しく、質の高い教育が受けられないこともあります。「学校へ通う機会」を保障するだけではなく、「学ぶ場所の環境」を整え、保障していくこともだいじなことなのです。
今日から私たちにできること
1児童労働をなくす取り組み「フェアトレード商品」について知る

チョコレートやコーヒー豆には、「フェアトレード商品」というものがあります。「フェアトレード」とは「公正な貿易」という意味で、生産者の労働環境や生活水準を守るために、児童労働力を使わずに生産されている商品です。このような商品を購入して、児童労働を減らす取り組みに参加することができます。お金がかかることなので、無理のない範囲で選択してみましょう。
2ほかの国の生活や産業に興味を持ち、自分のこととしてとらえる
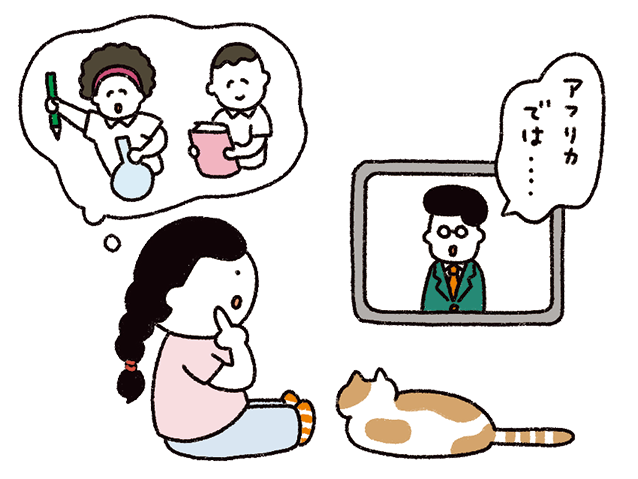
世界で起きていることに関心を持ってみましょう。教育を受けられない地域ではなぜ教育が受けられないのか、原因を調べたり、考えたりして、自分ができることを考え続けるということがだいじです。また、ニュースなどで見聞きしたら、ひとごととして終わらせず、「自分だったら」と考えてみましょう。思わぬところから、日本でできる支援が見つかるかもしれません。
文・「青いスピン」編集部 校閲・出口憲(常葉大学) イラスト・磯田裕子