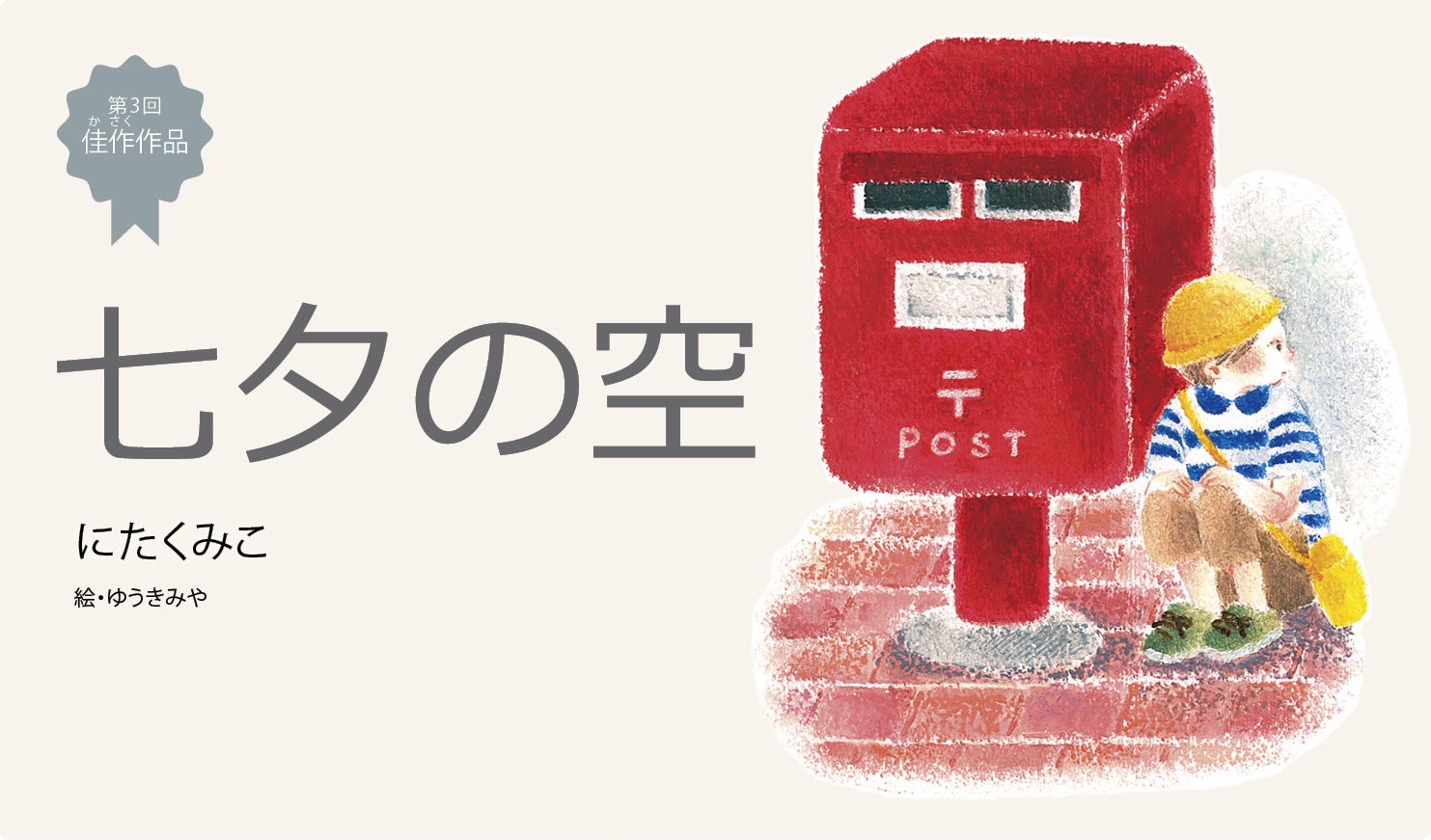梅雨に入り、蒸し暑い日が続く日々。
土曜日の朝、僕は自転車にまたがり、塾へと向かう。少しでも汗をかくまいと、今日もペダルをゆっくりとこぐ。
裏道は嫌いだ。近道にもなるけれど、余計に曲がったり、細かったりする道は窮屈だ。
じめじめとした湿気と、全身に太陽を浴びながら、今日も僕は、大通りをひたすらまっすぐ進む。
通っている塾のすぐ隣には区役所。と、その前にあるのは郵便ポスト。
ふだんは気にならないのだが、どうもこの夏は気になる。
区役所でも、その前にある郵便ポストでもなく、その郵便ポストの隣にちょこんと座っている、黄色い帽子に、黄色い水筒を持った少年。
小学一年生だろう。黄色い帽子はぶかぶかで、肩から掛けた黄色い水筒は少年には大きく見える。
「そこで何をしているの? 最近、土曜日によく見かけるけど。」
「土曜日だけね。日曜日はお休みだから。」
日曜日はお休み? 何のことだろうか。
「何で日曜日はお休み?」
「郵便屋さんは、日曜日はお休みだから。」
「ああ......なるほど。じゃあ、君はいつも郵便屋さんを待っているんだ。」
「うん......そうだよ。」
小学校に通う少年が平日に来ることは難しい。日曜日に郵便物の集荷はない。少年が待つ郵便屋さんとは、土曜日にしか会うことができないのだろう。
程なくして、郵便局の赤色の車が到着した。郵便局員は、僕たちを気にする様子もなく、じゃらじゃらと付いた鍵で、回収口を開けると、大量の郵便物を回収し、車に積んでいく。
手際よく作業を終えると、郵便局員はあっという間に次の郵便ポストへと出発してしまった。
少年はその様子を見届けると、深く息を吐き、水筒のお茶をぐびぐびと飲む。
この少年はこの瞬間を見るためだけに、ここに座って待っていたのだろうか。
僕にとってもあまり目にしない光景だった。
郵便物の集荷の現場なんて、見ようとしなければあまり見ることはない。郵便局の赤い車や、バイクに乗った配達員はたまに見かけるが、郵便ポストから郵便物を取り出す作業なんて、ふだんあまり見ることはない。
「終わったね。」
「終わったね。」
「これを見たかったの?」
「うーん......分かんない。」
分かんない? 確かに目で追っていたはず。郵便局員を凝視していたあの時間は、少年が待っていた瞬間のはず。
「次は二時間後だね......ばいばい。」
少年は帰っていった。
二時間後というのはきっと、次の回収時間のことだろう。郵便ポストの側面に記された次の回収時間は約二時間後。また、来るのだろう。なんで見ているのかは分からないのに、何となく、きっと少年はまた来るのだ。
この日から、土曜日の朝、僕は家を少し早く出るようになっていた。
郵便局員が来るまでの少しの時間、僕は少年の隣に座った。
ときおり、空を見上げる少年は、首をかしげて僕に問いかける。
「お空に住んでいる人に届けたいお手紙って、切手はいるの?」
「お空?」
「おばあちゃんが言ってたんだ。お空に届けてくれる郵便屋さんもいるって......でも、来ないね。朝は来ないのかな?」
「おばあちゃんがそう言ったの?」
「うん。お手紙を書いてね、お仏壇の前に置いてね。ずっとお空に届くまで待ってるんだけどね、お手紙はずっと、そこにあるの。」
「そっか......どうだろうね。お空に配達ができる郵便屋さんか......僕も知らないなあ。」
本当に知らない。僕も知らないんだ。
本当のことを言っただけなのに、何でこんなに胸が締めつけられそうなほどに苦しくなるのだろう。
僕を見つめる少年の切実な眼差しから、僕はそっと目をそらした。
ふと、目に留まる見慣れた掲示物。
区役所の入り口に大きくはられた七夕祭りのポスター。保育園に通っていた頃は毎年参加していた懐かしいお祭り。
「笹燃やし......って知ってる?」
「知らない。なあにそれ?」
七夕の日、僕は少年を誘って、七夕祭りに参加した。着いた頃には夕方で、祭りはすでに終盤を迎えている。
かき氷や焼きそばなどの出店には目もくれず、僕は少年の手を引いて、急ぎ足である場所へと向かう。
人々が大きな輪になって見つめる中央には、何本もの笹が、重なって置かれている。笹の先には願いの書かれた、たくさんの短冊が結ばれている。
「すみません。あの......まだ短冊書いてもいいですか?」
通りかかった運営職員に、僕は一枚の短冊をもらった。
「お手紙ではないけど、短冊もきっと、届けることはできるから。」
少年は半信半疑だったが、じっと僕の目を見ると、深くうなずいてくれた。
少年は短冊を受け取ると、短冊に願い事をつづった。突然渡された短冊に、少年は何の迷いもなくペンを走らせた。
力強くつづられた文字。少年の願いは決まっていた。
笹燃やしが始まった。
笹燃やしは、七夕に、短冊が結ばれた笹ごと燃やし、書かれた願いを天界の神に届けるという、ある風習によるものだ。
パチパチと音を立てながら、少年の短冊もゆっくりと燃えていく。
煙は、ゆっくりと空へと昇っていく。昇っていくにつれ、薄まる煙の色。
その先の空はとても広い。
少年の願いは空まで届くだろうか。
「わあ......きれい。」
目をきらきらと輝かせた少年が見上げた空には、幻想的な夕焼け空が広がっていた。
鮮やかな夕日のあかね色と、入れ替わるように続く群青色の空。
神秘的に混ざり合う幻想的な空の色は、僕らに勇気をくれているようだった。
「届くといいね。」
「うん......きっと届くよ。」
僕らはそれからしばらく、この空に見とれていた。
いずれ通り過ぎてしまう今を、この空を、記憶に、瞳に、焼きつけておこうと、ただ、目をそらせずにいたのだ。
家に帰ると、母は食器棚の整理をしていた。
「おかえり。」
「ただいま。」
「見て? これ、懐かしいわね。こんな所にあったわ。もうずいぶん古いから処分していいわよね?」
懐かしむ母の手には、小さな黄色い水筒。僕が小学生の頃に使っていたものだった。
「昔はあんなに大きかったのに......。」
久しぶりに手にした黄色い水筒は、今の僕には小さかった。
窓の外、すっかり真っ暗になってしまった夜空が見える。
いつもの見慣れた夜空。今日は何だか、少し寂しさを感じてしまう。
ふと、思い出す。
あの頃の僕の願いは届いたのだろうか。
「お空にいても、お父さんが元気でいますように。」
にたくみこ
2025年、第3回「青いスピン」作品募集 佳作。