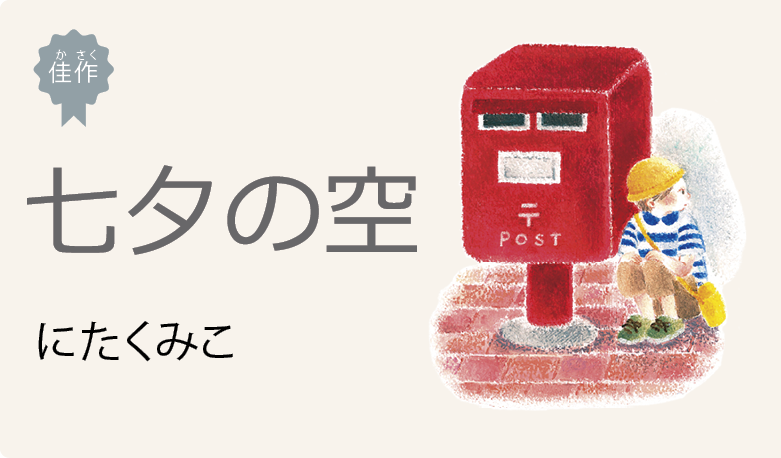何だかこれ、ゆりちゃんに似ている。
色白に黒目がちの瞳のゆりちゃんに。ぼくは店に並ぶレーズンパンを手に取ると買い物かごへ放りこんだ。
運動会の練習が始まった。まずは、クラス対抗の応援合戦の練習だ。ぼくたちは五年二組だから、六年二組の応援団のわき役だ。それなのに、ゆりちゃんは五年生で、一人だけわき役にならなかった。六年生の応援団に仲間入り。だってバトンダンスができるから。
「いいなー。」と、クラスのみんなは口々に言った。ゆりちゃんはピース、ピースとカニのように横歩きをする。
ゆりちゃんのバトンは、鉄棒が縮んだみたいな六十センチくらいの棒だ。両端に白いゴムがくっついている。
「ねえ、バトン見せて。へえ、......さわっていい?」
昼休み、ゆりちゃんの周りに女子が集まってきた。その後、みんなで体育館に行って、ゆりちゃんのバトンの腕前を見ることになった。
ゆりちゃんがバトンをぽーんと高く投げる。バトンはくるくる回転しながら落ちてくる。それを受け止める。また、回して投げる。うす暗い体育館に、紺色の体操服姿のゆりちゃんの色白の肌が、際立って白く見えた。
「うまいねえ。すごいねえ。」と、みんなは言った。
ゆりちゃんはバトンを放り投げた後、上を向いてバトンの行方を確かめた。ゆりちゃんが上を見上げると、色白の顔に目と目、鼻の穴。四つ、黒丸がうかんだ。そのとき事件が起こった。
「あ、鼻の穴。」
だれかが小さな声でつぶやいたんだ。いつもは見えない、ゆりちゃんの鼻の穴。今日はそれが目立って黒い丸に見えた。
ただ、それだけのことだった。ところが別のだれかが「鼻の穴、鼻の穴......。」と、くり返したとたん、笑い声が広がった。
何がおもしろいのか分からない。ぼくは何も言えずにうつむいた。
「あ!」
そのときバトンが思いもしない方向へ飛んでった。ゆりちゃんは、へヘへ、と頭をかき、バトンを拾いに走った。
帰り道、雨が降ってきた。だけど、ぼくはかさを差さない。これはバトンだ。右手でくるりと、一回、回す。左手に持ちかえ、また回す。右手、くるり。左手、くるり。交互に持ちかえて回す。もっと速く。もっとなめらかに。だけどゆりちゃんのように、うまく回せない。
「くそっ。」
ぼくは大きく息をはいた。そのとき、後ろから走って近づく足音が聞こえた。
「ちがう、ちがう。手をね、こう使うんよ。」
ゆりちゃんだ。ゆりちゃんは大股で歩いてぼくの横に立つと自分のかさを閉じて、回してみせた。ゆっくり、ゆっくり。だんだん速く。かさは、まるで黄色いバトン。回るたびに水滴が横ヘぴゅっ、ぴゅっと飛び散る。
ゆりちゃんは、ときどき真面目な顔をして、こんなふうに一生けん命になる。かけっこもドッジボールも、それからバトンも。ゆりちゃんが真面目な顔になると、ぼくは、ちょっと困る。おどけた顔のゆりちゃんのほうが話しやすいから。
ぼくは、ゆりちゃんと並んで歩く。ゆりちゃんはだまったまんま。ぼくも話すことがうかばない。
ぼくはかさを放り投げた。かさはいろいろな方向へ飛んでいき地面に落ちる。拾って、また投げる。上へ、高く。また落ちる。
「真上に投げるんよ。」
ゆりちゃんが歩きながら空を指差した。
ぼくはだまって放り投げた。かさは、ゆりちゃんの方へ飛んだ。
「あっ。」と、ぼくが言うと、「ほい。」と、ゆりちゃんが手を出してつかんだ。
「ぼくが投げて、ぼくが受け取るから。」
ぼくはかさをもういちど上に高く放り投げた。その瞬間だ。ゆりちゃんが、上を向いたぼくの顔を指差してつぶやいた。
「ほら、鼻の穴。」
「えっ。」
ぼくはどきんとして、鼻を手でかくした。ばさっ、とかさが地面に落ちた。ゆりちゃん、あのとき聞こえていたんだ。
「見えたらいかんのよね。」と、ゆりちゃんは言いながらぼくのかさを拾った。
「な、何が。」
「こう、バトンを上に投げると、顔を上げてバトンを見たくなるんだけどね。顔はまっすぐにしておくの。だから鼻の穴は見えちゃ、いけないの。」
「へ、へえ。」
ぼくは、うつむいてかさを受け取った。やっぱり、聞こえていたんだ。何て言おうか。白い顔に黒丸四つなんて、レーズンパンっぽくていいじゃないか......とは、言ってはいけない気がする。
「き、気にすることないよ。」
ぼくにしては、精いっぱいの言葉だったと思う。それなのにゆりちゃんは、怒ったような顔をして「別に、鼻の穴は気にしてない。」と言った。
「じゃ、何で鼻の穴の話なんかするんだよ。」
「バトンを投げたら、上を見上げるなってこと。」
「ああ......そっか。てっきりみんなに笑われたことが気になったのかと思った。」
ぼくは口に出した後、しまった、と思った。だってゆりちゃんの顔がぐにゃりと、ゆがんだんだ。やばい、泣きだしそうな雰囲気だ。ぼくが固まっていると、ゆりちゃんは顔をゆがめたままつぶやいた。
「......ずるいって、思われている気がする。」
「へ? 何で、ゆりちゃんがずるいんだ?」
「だって、六年生といっしょに......しているから。」
それを聞いた瞬間、のどのおくがきゅうって痛くなった。どうして痛くなったのかは、分からない。
「そ、それは、バトンがうまいからだろう。」
その言葉は、ぼくの口から出た言葉なのに、まるで別の人が言ったみたいにぼくの耳にひびいた。
ぼくが口ごもると、ゆりちゃんはふざけだした。
「そう。私はバトンがうまい!」
そう言ったゆりちゃんの声は、もういつものおどけた声にもどっていた。ほっとして、ぼくもふざける。
「ぼくのな、鼻って、変な音鳴るんだ。ほら。」
鼻を上に向け、大きくふくらませると、ゆりちゃんに向かってブーッと息をはいた。
「きったないなあ。」
ゆりちゃんは、けたけた笑って走りだした。
次の日の三時間目。また応援合戦の練習だ。ぼくたちは一列に並んで体育座りをした。
たいこが鳴った。音楽に合わせてダンスが始まった。ゆりちゃんが音楽に合わせてバトンをくるくる回し始めた。バトンを高く投げ、側転を一回してバトンを受け取る。それをくり返していたときだ。音楽とゆりちゃんの動きがずれてきた。
ゆりちゃんは、音楽に合わせるためにバトンをさらに高く投げて、回転するバトンを心配そうに見上げた。
あ、鼻の穴が見える。ぼくがそう思った瞬間、となりに座っていた女子がくすりと笑った。だめだ。くすくすは、伝染する。ぼくはとっさに声を上げた。
「上向くな、ゆりちゃん。鼻の穴、見えるぞ。」
思ったより大きな声になった。
びっくりした顔でとなりの女子がふり返った。みんながぼくの方をちらっと見た。
みんな、何でそんなにびっくりするんだろう。ぼくは、つばをごくんと飲みこんだ。ああ、これは、あのときと似ている。
給食の時間、「余ったレーズンパン、いる人。」って声をかけられたとき、周りの人はだれも手を挙げない。ぼくは挙げそうになった手を下ろしかけて......、やっぱり挙げる。すると、みんながちょっと笑いを含んだ驚いた顔で、ぼくを見るんだ。
ゆりちゃんは離れた所から、ぼくを見た。そして、ぼくに向かって右腕をのばすと親指をぴんと立てた。いつものおどけた顔じゃない。真面目な顔をして。
ゆりちゃんは、バトンを回しだす。リズミカルに高く放り投げ、側転を一回。さらに高く放り投げ、側転を二回。そして走り、ぴたっと足を止めると、背筋をぴんとのばす。あごを下げ、前を向いて落ちてくるバトンを静かに受け取った。まるでそこにバトンが落ちてくるのが、初めから分かっていたように。
「おおー、かっこいい。」
だれかのそんな声が聞こえた。
すると、ゆりちゃんは、腰に手を当てると、おどけた顔で、鼻を上に向けフンッと鳴らした。みんな、ゆりちゃんを見て笑ってる。
やったな、ゆりちゃん。ぼくは体育座りのひざの下で親指をそっと立てた。
ふと、窓の外に目を向けると、いつのまにか雨はやみ透き通るような青空が広がっていた。
文月レオ
2025年、第3回「青いスピン」作品募集 入選。